なぜ13歳で結婚? 古代中国の驚きのルール
古代中国では、女性が13歳や14歳で結婚することが一般的であった。
現代の感覚では驚くべきことだが、当時の社会ではそれが「当たり前」とされていた。
これは単なる風習ではなく、古代の法制度が婚姻年齢を定め、社会全体がそのルールに従っていたためである。

画像 : 周の儀式に関する指示を与える玄文夫人(陳紅書)public domain
紀元前に編纂された儒教経典のひとつ『周礼(しゅらい)』地官司徒には
「令男三十而娶,女二十而嫁」
とある。
これは、男子は三十歳、女子は二十歳で結婚すべきだという規定である。
『周礼』の編纂時期については諸説あり、紀元前11世紀に周公旦が制定したとする説、戦国時代末期や前漢の時代に成立したとする説がある。いずれにせよ、紀元前の遥か昔から早婚が奨励されていたことがわかる。
しかし、実際の社会ではこれよりも早い年齢での結婚が一般化していた。
特に、戦乱や人口減少の影響を受けた時代には、婚姻年齢はさらに引き下げられる傾向にあった。
結婚しないと罰金!?
結婚は単なる個人の選択ではなく、国家によって強く推奨される義務の一つであった。
特に女性に対しては、一定の年齢までに結婚しなければ罰則が設けられ、重税を課される制度も存在した。
この政策の背景には、国家の人口増加政策や社会の労働力確保の意図があった。
『漢書・恵帝紀』には次のような記述がある。
「女子年十五以上,至三十不嫁,五算。」
これは、「女子が十五歳を超えても結婚しない場合、三十歳に至るまで五算の税を課す」という法律である。
ここでいう「五算」とは、通常の五倍の賦税を指す。当時の算賦(人頭税)は基準額が約120銭とされていたため、未婚女性は5倍の600銭もの税を支払わなければならなかったのだ。
これは当時の庶民にとっては非常に大きな負担であり、結婚を避けることはほぼ不可能だったといえよう。
つまり、この制度は事実上の「強制結婚」制度であった。
国家は結婚を遅らせることを認めず、女子が適齢期に達すると、速やかに婚姻を成立させるよう圧力をかけたのである。戦乱や人口減少が続いた時代には、さらに厳格な規定が適用されることもあった。
こうした政策の影響で、女性たちは15歳を迎える前に結婚するのが一般的となり、13歳や14歳での婚姻が「普通のこと」とされるようになった。
結婚しなければ重い税負担を強いられるため、家族にとっても早婚を選ばざるを得なかったのである。
親の都合? 女子が早く嫁がされた家庭の事情
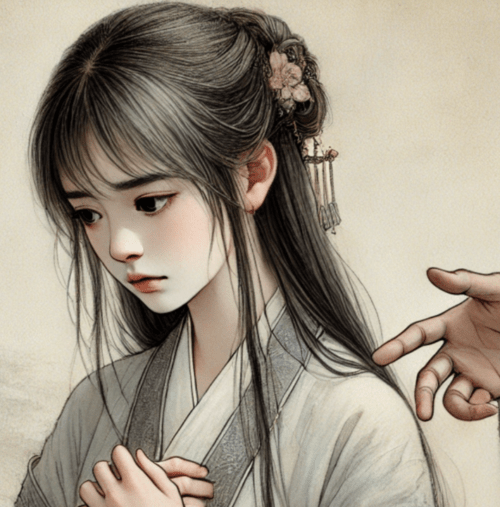
画像 : 早婚を促される女性 イメージ 草の実堂作成
女子が13歳や14歳で結婚することは、家族の経済的な事情も大きかった。
特に庶民階級では「早婚」が一家の生計を支える手段であり、親の都合によって娘が若いうちに嫁がされることが常態化していた。
古代の婚姻は、単なる男女の契約ではなく、家の結びつきとして扱われた。
『儀礼』士婚礼には、「納采・問名・納吉・納徴・請期・親迎」と記され、婚姻が厳格な手順を経て成立することが示されている。
ここで特に重要なのが「納徴」、すなわち結納金の授受である。
経済的に困窮する家庭では、娘を幼いうちから結婚させ、結納金を受け取ることで生計を立てることが一般的だったのだ。
また、男子の結婚には多額の費用がかかるため、妹を先に嫁がせ、その結納金を兄の結婚資金に充てるという「負担の分散」も行われていた。
さらに、戦乱や飢饉が発生した際には、女子の人身売買も公然と行われるようになった。
明代の『大明律』には「饑饉に際し女子を売るは刑に処さず」との特例規定があり、経済的に困窮した家族は、娘を「商品」として扱わざるを得なかった当時の事情も見える。
つまり、13歳や14歳での結婚は、「親の都合」によって決められることが多く、娘本人の意思はほとんど尊重されなかったのである。
「子どもを産むこと」が最優先
また、女性の結婚が早まった理由の一つに、子どもを産むことが何よりも重視されていたことがある。
当時における結婚の目的は「家の存続」と「労働力の確保」であり、女性は早く結婚し、多くの子どもを産むことを求められた。
儒教の教えでは、孝行の中でも「子を産み、家系を絶やさないこと」が重要視されていた。

画像 : 元代に書かれた孟子の想像図 public domain
『孟子・離婁下』には「不孝有三,无后为大」とあり、「孝行には三つの大事な要素があるが、その中で最も重い不孝は子を残さないことである」と説かれている。
これは、家系の存続が最優先される価値観を反映したものであり、結婚は「個人の幸せのためのものではなく、家のために果たすべき義務」と見なされていた。
また、農村では多くの子どもが労働力として期待されていた。
農業中心の社会では、人手が多ければ多いほど生活が安定すると考えられていたため、女子は早く嫁がされ、できるだけ多くの子を産むことが求められたのだ。
このように「子どもを多く産むこと」が女性の価値と直結していた。
そのため、13歳や14歳での結婚は「自然なこと」とされ、社会全体がそれを当然のものと見なしていたのである。
皇帝も民衆も同じ? 若い花嫁が求められた
また、国や家庭の事情に加え、皇帝から庶民に至るまで相手側も若い花嫁を望んだ。
その背景には、美的理想や宮廷文化の影響があった。
まず、皇帝の後宮では、若い少女が特に重視された。

画像 : 紂王と妲己 public domain
最も古くは、夏の桀王の側室とされる妹喜(ばっき)や、殷(商)の紂王に仕えた妲己(だっき)は、いずれも若くして後宮入りしたと伝えられる。
春秋時代には、斉の桓公の妹である文姜が、若くして魯の桓公に嫁いだ記録がある。
漢代の孝恵皇后張氏は、13歳から14歳頃に後宮入りしたとされる。また、前漢の高祖・劉邦の正妻である呂雉も、若い年齢で結婚したと考えられている。
唐代になると、武照が14歳で太宗・李世民の後宮に入り、のちに武則天として権力を握った。

画像:武則天 public domain
また、武則天に仕えた女詩人・上官婉児(じょうかん えんじ)は13歳で後宮に入り、文才を評価されて宮廷政治に関わるようになった。さらに、唐の昭宗の側室である郭氏も13歳で入内し、14歳で寵愛を受けた。
多くの場合、皇帝の側室は13歳から15歳の年齢で後宮入りし、その若さが美徳とされたのである。
この風潮は皇室だけでなく、貴族や庶民にも広がった。
詩や文学においても、「豆蔻年華」と呼ばれる13、4歳の少女が理想の美とされ、この風潮を後押しした。
唐の詩人・白居易は「娉娉嫋嫋十三余,豆蔻梢頭二月初」と詠み、13歳の少女の魅力を描いており、当時の美的価値観をよく表している。
このように、皇室の習慣、美的価値観、社会制度のすべてが相まって、13歳や14歳の少女が理想の花嫁とされていたのである。
現代の感覚では違和感を覚えるかもしれないが、当時の社会ではこれが当然とされ、庶民の間でも早婚が受け入れられたのは、こうした上流階級の影響が民間に波及した結果だったといえよう。
参考 : 『周礼』『漢書』『孟子』『史記』 他
文 / 草の実堂編集部
























この記事へのコメントはありません。