女中はいくらで雇えたのか?時代別にみる相場

画像 : 学者たちに仕える女僕 北斉期(550~577年)の宮廷画巻『北齐校书图』public domain
古代中国で女中として働いた女性は、丫鬟(アーファン、あかん)と呼ばれた。
秦、漢時代では婢や婢女、唐から宋には小鬟などと呼ばれ、宋以降になると丫鬟(アーファン、あかん)が広く使われるようになった。
本記事では分かりやすさのため、呼称を丫鬟に統一する。
まずは、女中を迎えるのに必要だった費用を、史料に基づいて整理していく。
当時の貨幣価値は現在とは大きく異なるため単純な比較は難しく、以下の数字はあくまで目安の一つとして捉えていただきたい。
秦漢の頃には、奴婢制度が法的に整えられ、女子は婢として扱われた。
史書や出土資料の記録から、成年女性は4300銭、未成年は2500銭ほどで取引されたと推測されている。
現代の価値にざっくり換算すると約1000元(約2万円台前半)ほどで、主に家事労働や雑役に使われる身分として見られていた。
当時は庶民の生活が逼迫し、売買の価格が極めて低く、食糧と交換される例すらあったとされる。
唐代の頃になると貨幣経済が発展し、丫鬟の価値も上昇する。
唐の法制をまとめた『唐律疏議』には奴婢の扱いが詳しく記され、この時代の丫鬟の買い取り価格はおおむね3万文前後と推定される。
現代換算では約110万円ほどになる計算だが、当時の体感でいえば「庶民が家財を売り払ってようやく用意できるレベルの大金」であり、丫鬟が家の中で大きな資産として扱われていたことが分かる。
宋代に入ると経済が発展し、丫鬟を買い取るだけでなく、契約を交わして雇う制度が並行するようになる。
買い取り価格は依然として数万文規模だったが、契約雇用では期間や待遇を文書で定める方式が広まり、料金は一律ではなく個別交渉で決まるようになっていった。
明代になると記録がより具体的になる。
粗使いの丫鬟は3両前後で売買され、当時の銀相場に換算すると約4〜11万円に当たる。
唐代の約110万円と比べると桁が違うように見えるが、唐は銅銭(文)、明は銀(両)と貨幣単位がまったく異なっており、単純比較はできない
体感でいえば、明の3両は「貧しい農家が一年分の生活費に匹敵する金をかき集めて娘を売る」イメージで、やはり庶民にとっては非常に重い金額であった。
容姿や技能に優れた丫鬟は十数両に達し、この時代の小説にも、生活苦から娘を3両で売ったという描写が見える。
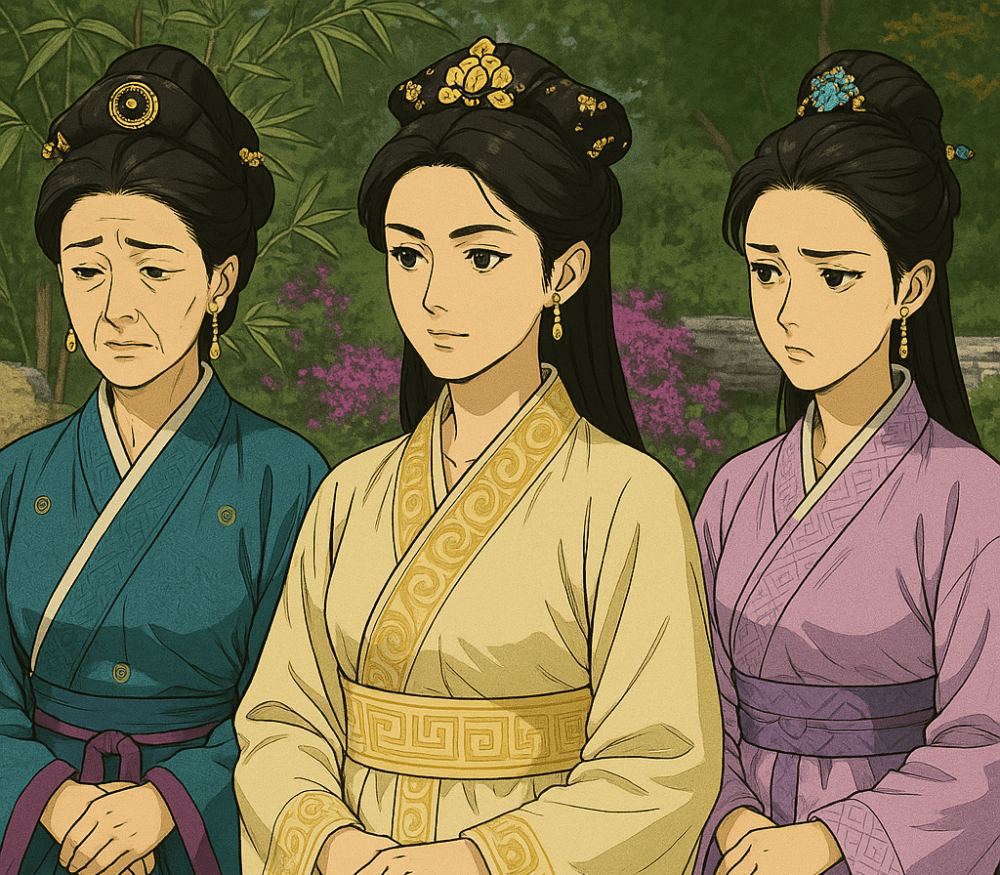
画像 : 丫鬟たち イメージ 草の実堂作成(AI)
清代に入ると、相場は時期によって大きく揺れる。
清代前半の康熙から雍正にかけては、一般的な丫鬟が5両前後で取引され、乾隆期には25両で一家四人をまとめて買った例もあった。
さらに災害が続いた道光や咸豊年間には庶民の経済が逼迫し、相場が3両台にまで下落した。
こうした数字からも、丫鬟の価格がそのまま当時の経済を映すバロメーターだったことがうかがえる。
また清代後期には、契約制の給金体系も整えられていた。
三等の丫鬟は前金10両(約3万〜5万円)と月給1両(約3000〜5000円)、二等は前金25両(約7万5000〜12万5000円)と月給1〜2両(約3000〜1万円)、一等や通房といった上級の丫鬟になると前金50〜2000両(約15万〜1億円超)、月給も5両以上(約1万5000〜2万5000円)が一般的であった。
当時の銀1両は150〜220元、約3000〜5000円と換算され、上級の丫鬟にはかなりまとまった額が動いていたことになる。
このように丫鬟の相場は、時代ごとの経済事情が色濃く反映されていたのである。
丫鬟と主人の距離 〜許される範囲と越えてはならぬ一線
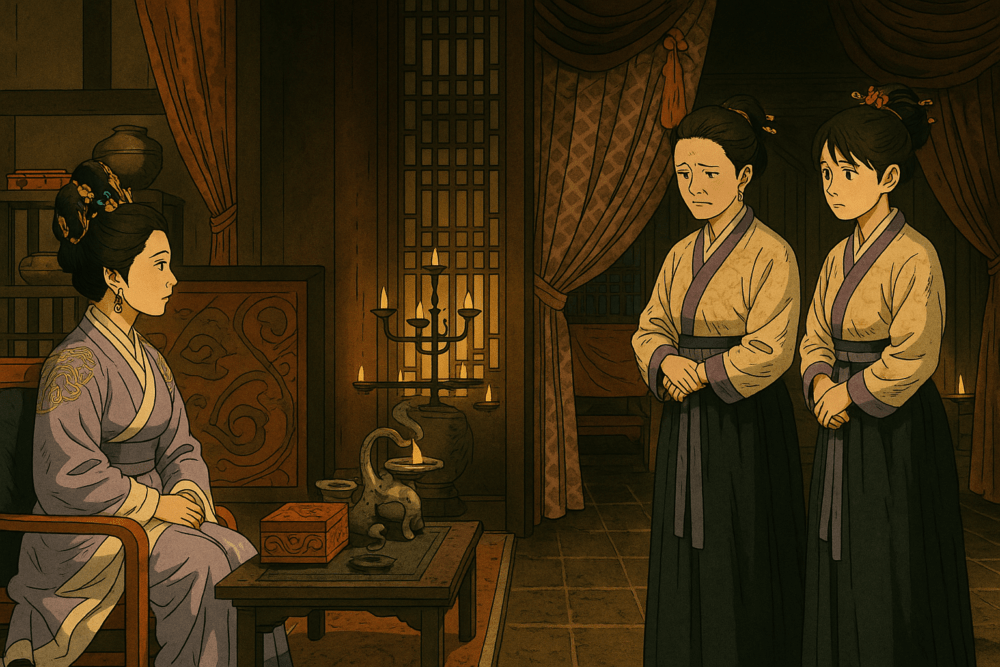
画像 : 妃と丫鬟たちイメージ 草の実堂作成(AI)
丫鬟は、家の中で多くの役割を担っていたが、その仕事の範囲は単なる家事にとどまらなかった。
主人の生活は昼夜を問わず丫鬟の働きに支えられており、時には家庭内の「境界」に触れるような業務も含まれていた。
まず日中の仕事であれば、大きな制限はなかった。
掃除、洗濯、食事の準備、客の応対などはすべて丫鬟の担当であり、主人が座を移せば茶を運び、書斎では筆墨を整え、散歩では傘を差すなど、生活全般を支える役目が期待された。
これは身分に関係なく広く行われていたもので、主家にとっては「家族労働力」の延長であった。
しかし境界がはっきりし始めるのは、主人の私的な領域に近い仕事である。
たとえば寝室の世話はその代表で、夜具の準備、温度の調整、夜中の飲み水や薬の用意など、信頼された丫鬟だけに任される役目であった。
主人夫妻の寝室に出入りできる丫鬟となると、選ばれるのはさらに一部であった。
慎み深さ、体調管理、家の秩序を乱さない姿勢が求められ、家事の技能だけでなく人格的な信頼も重視された。
ここで問題となったのが、主人と丫鬟の身体的な距離である。
明清の礼法では、主人が若い丫鬟に強引に手を出すことは禁止され、告発されれば「民女を辱めた」として処罰される規定も存在した。
とはいえ、両者の力関係は大きく、丫鬟が訴えることはほとんど不可能で、建前と現実には深い隔たりがあった。
こうした事情の中で、主人の寝所に正式に仕える特別な役目として、通房丫鬟が置かれるようになる。
通房丫鬟とは

画像 : 通房丫鬟(つうぼうようはん)イメージ 草の実堂作成(AI)
丫鬟の中には、通房丫鬟と呼ばれる特別な役目が存在した。
一般の丫鬟が家事全般を担うのに対し、通房丫鬟は主人の寝室に仕え、夜間の世話、寝具の準備、飲み水や薬の用意など、きわめて近い距離で生活を支えた。
役割の性質上、主人の私生活に深く関わるため、選ばれるのは容姿や気立て、忠誠心において特に信頼できる者に限られた。
通房丫鬟は、必要に応じて主人の夜の相手を務めることも認められており、妊娠すれば妾に昇格することもあった。
清代の小説『紅楼夢』(乾隆期の貴族社会を描いた長編)では、賈宝玉(か ほうぎょく)の丫鬟として仕えた襲人(しゅうじん)が、通房丫鬟として描かれ、寝室の世話を通じて特別な存在になっていく。
この描写は創作ながら、当時の制度や価値観をよく反映する例としてしばしば引用される。
ただし、特別な立場であるとはいえ、通房丫鬟の人生は決して安定していたわけではなかった。
主人に気に入られれば身分上昇の道が開ける一方、正妻の嫉妬を買えば遠方に売られたり、家から追放されたりすることも珍しくなかった。
立場が高いほど失うものも大きく、常に不安定な場所に立たされていたのである。
女中たちが解放へ向かった道のり
このように、長い歴史の中で、丫鬟は家内労働の担い手として、時に財産の一部として扱われてきた。
しかし、時代が近代へ進むにつれて、彼女たちを取り巻く環境は大きく変化していった。
清末になると社会の近代化が進み、家内の人身売買を問題視する声が知識層の間から上がり始める。
状況が大きく動いたのは、辛亥革命後である。

画像 : 孫文率いる中華民国臨時政府の面々 public domain
1912年の中華民国成立を受け、臨時政府は封建的な身分制度の廃止を宣言した。
とはいえ、各地では依然として旧来の習慣が広く残っていた。
都市部の家庭には「養女」として迎えられながら実質的には丫鬟として扱われる少女がおり、見かけ上の改革と実態の乖離が問題となった。
香港では19世紀後半から国際的な批判が高まり、20世紀初頭には廃止運動が盛んになった。
1923年に女傭服務条例が制定され、丫鬟の新規受け入れや売買が厳格に制限されたものの、取締りは不十分で実態は容易に消えなかった。
1926年には中華民国が国際連盟で奴隷制度禁止条約に署名し、世界から旧来の人身売買習慣が非難されるようになる。
これを受けて、中国本土や香港、東南アジア華人社会でも改革が急速に進んだ。
1930年代に入ると、買い取り女中の制度は名実ともに消滅へ向かった。
こうしてみると、丫鬟の存在は古代から清末まで続いた人身売買と家内労働の象徴であり、社会の変化とともにその姿も大きく変わっていった。
家の格式を示す存在から、法の保護を必要とする労働者へ。そして近代の改革を経て、ついに自由な個人として扱われるようになったのである。
参考 : 『唐律疏議』『紅楼夢』『里耶秦簡』他
文 / 草の実堂編集部






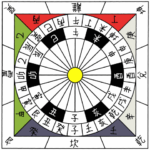

















この記事へのコメントはありません。