三国志以前の大事件

画像 : 宦官イメージ
中国の歴史は宦官の歴史でもあり、彼らは長きに渡って権力を握ろうと暗躍していた。
宦官が中心となった事件は枚挙に暇がないが、三国時代直前に起きた出来事として有名なのが党錮の禁(とうこのきん)である。
知名度という意味では三国時代に起きた戦闘や事件に少し劣るが、中国と宦官の歴史を語る上では欠かせない大事件である。
今回は、党錮の禁と、その中心人物となった李膺(りよう)を解説する。
清流派と濁流派
本題に入る前に、今回の主役となる「清流派」と「濁流派」の解説から入る。
桓帝 「後漢末期の流れを作った皇帝」宦官vs清流派
https://kusanomido.com/study/history/chinese/sangoku/43614/
上の記事でも少し触れているが、もう少し詳しく説明すると、清流派とは前漢の武帝によって制定された「郷挙里選(きょうきょりせん)」という登用システムで選ばれた者の総称である。

画像 : 漢武帝 public domain
郷挙里選とは各地から優秀な人物を推薦するもので、いわゆるコネ採用も少なからずあったが、正規のルートで選ばれて狭き門を突破する事は当時の中国に於いてはエリートの証であり、清流派の看板は彼らの誇りでもあった。
一方の濁流派は宦官の事であり、以降は宦官で統一する。
宦官とは去勢した官吏で皇帝と深く繋がっていたが、去勢はさておき、汚職上等で成り上がりを目指す「濁流」という名の通り、清流派とは対極に位置する存在だった。
中国史に於いて悪名を残しすぎている宦官に対するイメージはどうしても悪くなってしまうが、「宦官=悪」というイメージは必ずしも正しいわけではなく、立派に政治に貢献した者も少なからず存在した事は、中国の長い歴史が伝える事実として述べておきたい。
清流派のトップだった 李膺
一応宦官に対するフォローはしたが、党錮の禁の発端は「宦官の汚職」を清流派が摘発した事であり、党錮の禁が起きた166年当時の政治は宦官による汚職が横行していた。
ここで登場するのが、清流派のトップとしてこの事件の中心となった李膺(りよう)だ。

画像 : 李膺(りよう) public domain
李膺は絵に描いたような高潔な人物であり、文字通り宦官の天敵だった。
李膺の人柄と宦官の関係を示すエピソードがある。
宦官・張譲の弟の張朔は、数々の悪事を働いていた。
張譲は宦官でもかなりの高位の中常侍であり、張朔は兄の元に匿われていたが、李膺は構わず張朔を逮捕し、斬首した。
弟を殺された張譲は「弟は無罪なのに殺された」と桓帝に訴えて李膺を罪に問うが、桓帝から呼び出された李膺は「罪を犯した公族を許せと言われても、役人は許さなかった」と、かつて孔子が魯の司寇になって7日目に少正卯を死刑にした例を出した。
それを聞いた桓帝は「これはお前の弟が悪いと」張譲の訴えを却下したのである。
ただでさえ水と油の宦官と清流派に加え、個人間でもゴタゴタがあったのだから、更なる事件が起きるのは時間の問題だった。
第一次党錮の禁
166年、宦官の汚職に耐えかねた李膺を中心とした清流派は、罪状を持って宦官を告発したが、宦官も「太学の学生や有力者達と党派を作り、朝廷を誹謗している」と反撃に出て、李膺を初めとした清流派200人を逮捕した。
李膺たちへの起訴状は清流派である太尉の陳蕃(ちんはん)の元に送られたが、陳蕃は「この者達は憂国忠義の臣であり、罪があったとしても、10代後まで恩赦すべきである」と署名を拒否した。(細かいところまで突き詰めれば清流派内部にもコネや賄賂があっただろうが、李膺自身に汚職を働いた証拠はない)
桓帝は怒って陳蕃を免職するが、李膺が取り調べの度に宦官たちの汚職を告発したため、ついに宦官は根負けして桓帝に李膺の恩赦を願い出た。
李膺は晴れて釈放されて故郷へ帰るが、この件で逮捕された者達は禁錮刑(現在の禁錮刑とは違い、宮中追放)という軽くない処分を受けた。
結局、クビは切られても本当の首までは斬られなかった事と、自分が清流派であると証明されたとして喜ぶ者がいたなど、第一次党錮の禁はかなり平和なものだった。(基本的に桓帝は宦官寄りではあったが、悪事を働いていた張朔を処刑した李膺の主張の正当性を認め、罪は罪とする真っ当な判断力を持っており、人事に於いても宦官を重用する一方で清流派の人間も要職に据えるなど、両者のバランスを取るよう努力していた)
第二次党錮の禁
李膺の釈放から程なくして桓帝が崩御すると、霊帝こと劉宏が即位する。(当時10歳)
皇太后の竇妙(とうみょう、以後竇太后)により太傅 兼 録尚書事となった陳蕃は、竇妙の父親である大将軍・竇武(とうぶ)とともに宦官たちの排除を画策した。
そして竇太后から「除くなら罪のある者だけ」という条件を受け、宦官の管覇と蘇康を誅殺したのである。
その後も陳蕃と竇武は、宦官の更なる排除と自分達の権力強化を進めようとしたが、計画が露呈して宦官に反撃の隙を与えてしまう。
その後、宦官の曹節と王甫が協力して詔勅を偽り、陳蕃、竇武討伐の軍を出した。
竇武は自殺、陳蕃も殺されて竇太后も幽閉となり、宦官粛清計画は失敗に終わった。
そして宦官は処罰の対象を広げ、清流派は一掃されてしまったのである。
これを第二次党錮の禁という。
李膺の最期と党錮の禁のその後
第一次党錮の禁が「宦官による清流派追放」だったのに対し、第二次党錮の禁は「清流派による宦官粛清失敗」と、その内容は大きく異なる。
第一次党錮の禁は、清流派と宦官のバランスを取っていた桓帝が存命だったために軽い処分で済んだが、第二次党錮の禁では宦官を止められる者がおらず、ありとあらゆる清流派が逮捕、処分された。

画像 : 党錮の禁 イメージ
逮捕された者の中には李膺の姿もあり、拷問の末に獄死している。
第一次党錮の禁の中心人物であり、清流派のトップとして名を馳せた名士の悲しい最期だったが、宦官の暴走は止まらなかった。
172年、宦官の曹節と王甫をなじる落書きが発見されると、1000人にも及ぶ太学生が逮捕された。(太学は儒教の教育機関であるとともに、清流派の拠点でもあった)
第二次党錮の禁の逮捕者に対しても一族にも及ぶ徹底的な弾圧が行われた。
霊帝は政治に興味を持たず、この時代は間違いなく宦官の時代であったが、自らの贅沢しか考えない宦官の世が長続きするはずもない。
流れが変わったのは184年の黄巾の乱である。

画像 : 清代の書物の黄巾の乱、劉備関羽張飛の三人 public domain
黄巾の乱が起きると、宦官たちは追放した清流派が乱に加わる事を恐れ、投獄していた者たちを解放した。(黄巾の乱が起きた理由の一つが宦官の暴走である)
これによって本当の意味で党錮の禁の終結となるが、黄巾の乱の混乱によって各地の群雄が力を得るようになり、宦官の時代は一旦の終焉を迎える事になる。
清流派と宦官の争いは宦官の勝利であったが、権力を手にした結果黄巾の乱を招き、自らの身を滅ぼす事になるのは因果応報と言うしかない。
今回の主役の一人であり、後漢末期の宦官の代表格となった張譲は、189年に可進大将軍を暗殺するが、それに怒った袁紹が宦官殲滅のため宮中に討ち入る。
張譲は少帝と陳留王(献帝)を連れて逃げ出すが、追撃を受けて入水自殺した。
取り残された少帝と陳留王は董卓に保護されるが、董卓が帝を手に入れた事によって党錮の禁も黄巾の乱も及ばない、後漢最大の暴政と混乱の幕開けとなったのである。
参考 : 『後漢書』 『正史三国志』














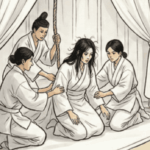










この記事へのコメントはありません。