日本史上でよく知られる「島流しの刑」。
この刑罰は、現代でいえば終身刑や無期懲役に近い部分もあるが、禁錮刑や懲役刑とは違い「追放刑」という特徴を持っている。
罪人は、それまで暮らしていた土地や生活基盤から強制的に離れさせられ、見知らぬ土地へ移住させられた。
形式上はただの追放にも見えるが、実際には生易しいものではなかった。
単に「田舎暮らし」と片付けられるようなものではなく、食料や住居、社会的なつながりのすべてを自ら確保しなければならない、過酷な現実が待ち受けていたのだ。
では、流人たちはどのような罪で島流しに処され、その地でどのような生活を強いられたのだろうか。
今回は、時に「死刑よりも過酷」だったとされる島流しの実態に迫ってみたい。
島流しとは

画像:過酷な流刑地とされた御蔵島 public domain
「島流し」とは、罪人を都や中心地から遠く離れた辺境の地へ追いやる刑罰で、「流罪」や「流刑」の俗称である。
この刑罰は、死罪に次ぐ重罪とされていたが、時代や罪状によってその運用は異なっていた。特に江戸時代までは、皇族、僧侶、大名など影響力のある人物が主な対象となり、多くは政治的理由によるものだった。
「島流し」と聞くと、絶海の孤島へ送られる印象を持つ人も多いが、配流地は必ずしも離島に限らなかった。
交通網が未発達だった当時、本州内の辺境地が流刑地になることもあり、キリシタン大名だった高山右近のように、国外追放としてマニラなど海外へ送られる例もあった。
流罪には「近流」「中流」「遠流」の三段階があり、罪の重さに応じて配流地の遠近が決められた。遠流に科される者ほど都や幕府から遠い地へ送られ、厳しい環境下での生活を強いられた。
また、罪人には財産没収や「縁座」(連座)が科されることもあった。
特に中世以前では、家族も罪人と共に流刑地へ送られることがあったが、江戸時代以降は単身で配流される例が一般的になった。
恩赦による帰還が認められることもあったものの、ほとんどの流人は「故郷へ帰りたい」と切望しながら、見知らぬ辺境の地で生涯を終えたのである。
時代や身分によって変遷する流罪

画像:木梨軽皇子の墓と伝わる東宮山古墳(愛媛県四国中央市)CC Saigen Jiro
日本で初めて流罪が適用されたのは5世紀頃とされ、罪人は皇太子や皇女といった高貴な身分の人物であった。
第19代允恭天皇の第一皇子・木梨軽皇子と第二皇女・軽大娘皇女が、兄妹で関係を持ち、その咎で二人は伊予国に流された。
これが問題視されたのは、二人が皇族であり、国家秩序や倫理に影響を及ぼす立場であったためとされている。
この事件の詳細については『古事記』と『日本書紀』で記述が異なる。
『古事記』では、木梨軽皇子が流罪となり、後を追った軽大娘皇女と共に自ら命を絶ったとされる。
一方、『日本書紀』では、軽大娘皇女が流罪に処され、木梨軽皇子は後に反乱を起こして穴穂皇子の兵に包囲され、自害したとある。
いずれにせよ、皇族という特別な身分ゆえに、重大な問題として扱われた例の一つと言えよう。

画像 : 後鳥羽上皇 public domain
その後、平安時代から戦国時代にかけて、流罪は単なる刑罰にとどまらず、「反対勢力の弾圧」や「邪魔者の排除」という性格を帯びるようになる。
例えば、承久の乱を起こした後鳥羽上皇は、隠岐島に流された。
単に罰を与えるだけでなく、その影響力ゆえに死罪にできない者を再起不能にするには、流罪がうってつけだったのだ。
また、室町時代に活躍した猿楽師の世阿弥は、時の将軍・足利義教に疎まれ、いわれのない罪で流罪にされたとされる。
戦国時代に入ると、交通網が発展したことで遠隔地に追放することの意義が薄れ、代わりに罪人を遠隔地の大名の監視下に置く「大名預け」が主流となった。この時期の流罪は、権力者がその威光を示すためのパフォーマンスに転化したともいえるだろう。
刑罰としての流罪は、江戸時代に再び復活した。この時代には庶民にも流罪が適用される例が増え、特に八丈島や佐渡島といった離島が流刑地として指定された。
さらに、明治時代になると当時未開の地であった北海道への追放が行われ、罪人には強制労働が課された。
なお、流罪が日本の刑罰体系から完全に廃止されたのは、明治41年(1908年)の刑法改正によるものである。この改正により、追放刑は禁錮刑や懲役刑といった近代的な刑罰に置き換えられることとなった。
流人の生活

画像:配流地へ向かう船を見送る人々 出典/国立国会図書館
流人たちの生活について確認できる文献は、江戸時代のものが多い。
江戸時代に入ると、都市の繁栄と共に犯罪が増加し、流罪が多く適用されたのだ。
江戸時代には先述した縁座は適用されず、罪人は家族と離れ、単身で配流地へ赴くことが一般的であった。
配流先は主に離島であり、この頃から「島流し」という呼称が一般化した。
島での生活は非常に過酷だった。
離島は食糧の自給自足が困難で、飢饉が頻繁に起き、さらに火山の噴火や塩害など、自然条件も厳しかった。
流人たちは生き延びるため、地元の農家や漁師の手伝いをして糧を得ることが多かったが、働けない老人や病人の場合はさらに悲惨だった。飢饉の際には、まずそうした弱者が犠牲になったのだ。
島民もまた、流人の存在に頭を悩ませた。
安定した生活を送れない流人たちは、しばしば島でトラブルを引き起こし、治安悪化の原因となることもあった。島民は彼らを厄介者と見なしつつも、再犯を防ぐため、収穫後の余り芋を分け与えるなどの施しを行うこともあったという。
一方で、幕府が罪人を離島に送った理由は現実的なものであった。
収監場所が不足していた上、罪人の生活費を幕府が負担することは財政的にも難しかったのである。
こうして、流人は半ば島に押し付けられる形で配流されていった。離島の住民からはたびたび「罪人を送らないでほしい」と請願が出されたことも記録に残っている。
このようにして島流しにされた流人たちは、社会的にも孤立し、罪を悔い改めたとしても、島民と対等に暮らすことは叶わず、生涯を厳しい環境の中で終える運命にあったのである。
俊寛の最期

画像: 『しゆん寛 五代目市川團藏』西光亭芝國 public domain
ここでは、憐れな流人をひとり紹介したい。
平安時代の僧侶であり、後白河法皇の側近でもあった俊寛(しゅんかん)である。
俊寛は、平氏打倒を企図した「鹿ヶ谷の陰謀」に加担したとして捕らえられ、藤原成経、平康頼とともに薩摩国の鬼界ヶ島に流された。※鬼界ヶ島は鹿児島県の硫黄島とする説が有力。
『平家物語』の記述によれば、鬼界ヶ島は硫黄岳の噴煙が立ち込め、独特の臭気が漂う過酷な環境であったとされている。
また、島民の生活習慣や方言も俊寛たちにとっては異質であり、都での優雅な暮らしを知る彼らにとって、この環境は耐え難いものであった。
どうしても都に帰りたかった成経と康頼は、千本の卒塔婆(墓石の後ろに立てる細長い板)に望郷の思いを込めた歌を書き記し、海へ流した。
俊寛は、高僧としてのプライドもあったのか、これには参加しなかった。
やがて、その卒塔婆が安芸国厳島に流れ着き、これを目にした平清盛は恩赦を決めた。
しかし、俊寛はこの恩赦の対象には含まれていなかった。
成経と康頼を迎えに来た船が鬼界ヶ島に到着すると、俊寛は自分だけが赦されていないことを知る。
彼は「せめて九州まででも」と懇願するが、船に乗ることは許されなかった。
これ以上の処罰を恐れた成経と康頼も、彼の願いを受け入れることができなかったのである。

画像:乗船を懇願する俊寛
俊寛は船が出航しても諦めず、腰まで海に浸かりながら「乗せてくれ!」としつこく頼んだ。
成経と康頼だけを乗せた無慈悲な船を、俊寛はいつまでも見つめ続けたという。
そこにはもはや気高い高僧の姿はなく、ただただ憐れな男がひとり取り残されていただけだった。
その後の俊寛の生活は凄惨を極めた。
食糧を得るのもやっとで、地元の漁師に魚をわけてもらったり、海岸で海藻を拾ったりしながらなんとか食いつないだ。
というのも、鬼界ヶ島では主食となる米がなかったのである。
以前は、成経の舅の平教盛が肥前から必要な衣食を援助してくれていたが、成経はもういない。
ついには庵もボロボロになり、髭も髪も伸び放題で衣服は破れ、身体は痩せ細り、俊寛の身なりは乞食のそれとなんの違いもなくなった。
その後、かつての侍童であった有王が、俊寛を訪ねて鬼界ヶ島を訪れた。
有王は、俊寛の娘から預かった手紙を渡し、都における家族の消息を伝えた。この時、俊寛は妻や息子の死を聞いたともされる。
俊寛は娘の手紙を読みながら涙を流し、家族たちと再び会うという希望が絶たれたことを悟った。
打ちひしがれた俊寛は、深い絶望の末に断食を決意し、その後、二十三日目に餓死したのである。
おわりに
「島流し」は、現代の感覚で捉えると「やや不便」と感じる程度かもしれない。
しかし、当時の未開の地での生活は、現代とは比較にならないほど過酷であった。交通網は未発達で、インフラも整っておらず、衣食住を確保するだけでも困難を極めたのである。
刑罰としては「死罪より軽い」と位置付けられていた流罪であるが、実際には過酷な環境での孤独や苦痛を伴い、生きながらえること自体が試練であった。
耐え切れず自害に至る者も多く、その実情は想像以上に苛酷で残酷な刑罰だったのだ。
参考 : 『平家物語』『流罪の日本史』『我國に於ける流刑に就て』他
文 / 草の実堂編集部
この記事はデジタルボイスで聴くこともできます。















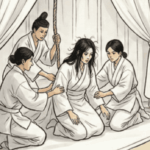









この記事へのコメントはありません。