朝ドラ『虎に翼』では、星航一が自身の暗い過去を語り、戦争を止めることができなかった苦悩を吐露しました。
航一が所属していた機関「総力戦研究所」には、実在モデル・三淵乾太郎が第一期研究生として在籍しています。
「総力戦研究所」に集められた若きエリートたちは、対米開戦となった場合、日本は勝てるのかどうかというシミュレーションを行いました。
彼らの出した結論は「日本必敗」。
原爆投下以外、まるで未来を覗いて来たかのように正確に日本の敗戦を予測していた「総力戦研究所」とは、どのような組織だったのでしょうか。
若手エリートたちの教育機関としての総力戦研究所

画像 旧首相官邸1929年 public domain
総力戦とは、武力だけでなく、思想・政略・経済等、多分野にわたる全ての国力を総動員して戦うことを意味します。
「総力戦研究所」は、総力戦を主導する次世代のリーダーを育成することを目的として、1940年(昭和15年)9月30日に設立されました。
軍ではなく内閣総理大臣の管理下に置かれ、翌年の4月には、35名の研究生の入所式が行われています。研究生は、平均年齢33歳。軍人、官僚、民間と出身母体は異なるものの、全員10年以上の実務経験者でした。
訓練期間は1年間とされ、6月から日本を「青国」と見立てた机上演習が始まりました。模擬内閣を組閣し、日米開戦に至った場合の戦況の推移と結果を詳細に分析するのです。
研究生たちは青国政府を組織し、彼らが実際に所属している組織の閣僚になりました。
たとえば、大蔵省事務官は大蔵大臣、軍人は陸軍大臣と海軍大臣および次官といった具合です。
民間出身者の場合は、同盟通信(後の共同通信)の社員は情報局総裁となり、三菱鉱業と日本郵船の社員は企画院次長のポストにつきました。
ちなみに三淵乾太郎は、当時、東京民事地方裁判所判事でしたので「司法大臣」兼「法制局長官」を任されています。
総理大臣には、産業組合中央金庫参事の窪田角一が就任し、政府と行政に関わる全ての機関を網羅した仮想政府による対米戦のシミュレーションが行われたのでした。
シミュレーション結果は「日本必敗」

画像. バリクパパンの燃える油田を進撃する日本軍 public domain
机上演習では、各大臣が出身組織から資料やデータを持ち寄り、戦局をシミュレートしていきます。
出身母体の利害を越え、事実に忠実に、論理的に幾度も議論を重ねた模擬内閣の出した結論は、「日本必敗」でした。
「開戦後、緒戦の勝利は見込まれるが、その後は長期戦が必至であり、その負担に青国(日本)の国力は耐えられない。戦争終末期にはソ連の参戦もあり、敗北は避けられない。ゆえに戦争は不可能」
彼らの出した筋書きは、その後の日本が歩んだ戦局そのものと言えます。
特筆すべきは、日米戦争の最重要課題である石油について、「必要な量は確保できない」と結論づけていたことです。
「英米仏蘭諸国の経済封鎖に直面した場合、たとえ南方の油田を確保しても、日本まで運ぶ輸送船が米軍の攻撃により壊滅し、補給路は絶たれる」という結論を、彼らは開戦前に出していたのでした。
葬り去られた「総力戦研究所」

画像 第3次近衛内閣. public domain
「総力戦研究所」のシミュレーション結果は、1941年(昭和16年)8月下旬、「第一回総力戦机上演習総合研究会」で、近衛文麿首相をはじめとする政府・軍部首脳陣たちに報告されました。
しかし、彼らの導きだした結論が支持されることはなく、報告を聞き終えた陸相・東条英機は
「これはあくまでも机上の演習で、実際の戦争というものは、君たちの考えているようなものではない。勝てると思わなかった日露戦争で大日本帝国が勝利したように、戦というものは、計画通りにいかない。意外裡なことが勝利につながっていく。」
と発言しています。
また、企画院総裁だった鈴木貞一が後年語ったように、当時の政府や軍部首脳陣の間では、すでに日米開戦必至という暗黙の了解がなされていました。
彼らが欲していたのは、戦争を始めるためにつじつまを合わせるような都合のいい結果だったのです。
「総力戦研究所」の研究生たちが英知とデータを駆使して辿り着いた「日本必敗」という結論は一蹴され、日本は対米戦へと突き進んで行きました。
開戦後、皮肉にも「総力戦研究所」のシミュレーション通りに戦局が動き、日本は敗戦への道をひたすら歩むことになります。
自分たちの描いたロードマップ通りに進む戦局を、研究生たちはどのような気持ちで見ていたのでしょうか。敗戦を予測しながら戦争を止めることも叶わず、さぞ無念だったに違いありません。
1942年(昭和17年)3月、「総力戦研究所」の一期生は卒業を迎えました。
4月には第二期生39名、翌年には第三期生40名が入所し、三期生が同年12月15日に繰り上げ卒業になった後、「総力戦研究所」は研究生を迎えることなく、1945年(昭和20年)4月1日付けで廃止されました。
参考)
猪瀬直樹『昭和16年夏の敗戦』中央公論新社
伊藤隆監修,百瀬孝著『事典 昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館
文 / 草の実堂編集部









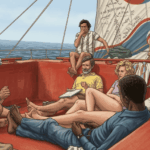






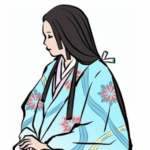







この記事へのコメントはありません。