近年、国際情勢を巡る議論の中で「台湾有事」という言葉が頻繁に語られるようになった。
なかでも注目を集めているのが「2027年」という具体的な年限である。
この数字は単なる憶測や専門家の予測だけではなく、米国防総省の公式評価や軍高官の議会証言に繰り返し登場する、現実的な警戒ラインとして浮上している。
なぜ数ある未来予測の中で、2027年がこれほどまでに強調されるのか。
その背景には、中国の軍事計画と政治的な象徴性が複雑に絡み合っている。

画像 : 台北市街地(市民大道高架道路) Peellden CC BY-SA 3.0
建軍100周年と習近平政権の野心
最大の理由の一つは、2027年が中国人民解放軍(PLA)の建軍100周年という極めて重要な節目にあたるからだ。
中国共産党は、この年までに軍の近代化を加速させ、「世界一流の軍隊」への土台を築くことを国家目標に掲げている。
この見方を象徴するのが、米インド太平洋軍前司令官フィリップ・デービッドソン提督の議会証言である。

画像 : フィリップ・デービッドソン米海軍大将(米艦隊軍司令官、2014年) U.S. Navy Public domain
デービッドソン氏は2021年3月、米上院軍事委員会での証言において、中国の軍備増強や地域での行動を踏まえ、「脅威は今後10年、とりわけ今後6年の間に顕在化する可能性が高い」と述べた。
これは侵攻の期限を示したものではなく、中国が武力行使を現実的な選択肢として行使し得る期間に入る、という警告であった。
この発言は後に「デービッドソン・ウィンドウ」と呼ばれ、2027年前後が危険度の高い局面であるとの認識を国際社会に定着させることになる。
これは、中国が米国の介入を阻止しつつ、武力行使を成功させるだけの軍事能力を完備する目標時期と重なっている。
習近平国家主席にとって、自らの任期中に「祖国統一」という歴史的偉業に王手をかけることは、権力基盤を盤石にするための究極のシナリオと言えるだろう。
軍事バランスの変容と「拒否能力」の構築
これまで台湾海峡の平和を支えてきた最大の要因は、米国の圧倒的な軍事力による抑止だった。
ところが近年、中国は海軍力を急速に拡張し、米空母の接近を阻むA2/AD(接近阻止・領域拒否)能力の整備を進めている。
最新鋭空母「福建」の就役に象徴されるように、台湾周辺での軍事演習も、もはや特別なものではなくなった。

画像 : 中国海軍の空母「福建」の飛行甲板(2025年11月撮影) China News Service / CC BY 3.0
注目すべきなのは、その演習内容だ。
近年は単なる兵器の性能誇示ではなく、部隊の統合指揮や補給体制、長期間にわたる作戦遂行能力まで含めた、実戦を意識した検証へと重心が移りつつある。
米国防総省も、こうした動きを「中国軍が実戦能力を最終的に確かめる段階に入った兆候」と捉えており、大規模上陸や精密火力攻撃、海上封鎖といった複数の軍事オプションが繰り返し演習されていると分析している。
こうした能力整備が進めば、2027年前後には中国が空母戦力や極超音速兵器を組み合わせ、実戦的に運用できる段階に達すると見られている。
一方、米国と同盟国側は、次世代兵器の配備や軍事再編の移行期にあり、その隙を中国が突くのではないかという懸念が現実味を帯びているのだ。
経済停滞とナショナリズムの暴走
また、中国国内の経済状況も無視できない。
不動産バブルの崩壊や少子高齢化により、かつてのような高成長が望めなくなった今、共産党政府は統治の正当性を「経済成長」から「ナショナリズム」へとシフトせざるを得ない状況にある。
国内の不満を外に向けるため、あるいは「強い中国」を演出するために、台湾問題が利用されるリスクは高まっている。
自由を享受する台湾の存在は、統制を強める大陸側にとって「民主主義の成功例」という不都合な鏡であり、これを封じ込めることは体制維持のための至上命令となっている。
平和の維持に向けた日本の役割
2027年という数字は、必ずしも戦争の開始時期を断定するものではない。
台湾海峡の安定は、日本にとっての生命線でもある。地理的に極めて近い日本は、有事の際に「当事者」となることは避けられない。
今、求められているのは、対話による緊張緩和と、武力行使を思いとどまらせるための毅然とした抑止力の構築だ。
2027年を「破局の年」にしないための国際社会の知恵が、今まさに試されている。
参考 : U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2025, December 2025 他
文 / エックスレバン 校正 / 草の実堂編集部












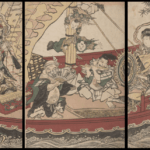











この記事へのコメントはありません。