
画像:ジョン・ポール・サルトル public domain
実存主義とは、人間の存在や自由、そして自由ゆえに生じる不安と責任に焦点を当てた哲学である。
その思想は19世紀のキルケゴールやニーチェに端を発し、20世紀に入りマルティン・ハイデガーらによって展開されたが、ジャン=ポール・サルトル(1905–1980)はそれをさらに発展させ、大衆に広めた人物である。
サルトルの実存主義は、単なる観念的な思弁ではない。特に第二次世界大戦という極限状況を経験した彼にとって、哲学は現実に向き合うための道具であり、生きる上での実践的な態度を示すものでもあった。
戦後の虚無と価値の崩壊が進む中で、サルトルは「西欧キリスト教社会の伝統的な道徳や規範は、もはや拠り所にならない」という事実と向き合うことになった。そして彼は「個人が自らの行動を通じて、人類全体に対して責任を負うべきだ」と主張するに至る。
1946年の講演『実存主義はヒューマニズムである』において、サルトルは「人間は自らを選ぶ」と述べた。
この言葉は、他者や神に指示を仰ぐのではなく、自らの選択によって自らを定義し、その選択が他の人間のあり方にまで影響を及ぼす、という覚悟を説いたものである。
つまり、彼の実存主義とは、自由に生きることの代償として生じる不安や責任を引き受けようとする態度であり、それは同時に、価値なき世界において人間がいかに意味を創出できるかという問いへの、誠実なこたえでもあった。
キリスト教社会の否定としての「自由の刑」

画像 : キリスト(イメージ)
サルトルは主著『存在と無』(1943年)の中で、「人間は自由という刑に処されている(L’homme est condamné à être libre)」と述べている。この衝撃的な命題は、西欧近代におけるキリスト教的世界観の崩壊を背景にしている。
彼が影響を受けたニーチェは「神は死んだ」と宣言し、価値の源泉としての神の権威が失われたことを示した。
キリスト教においては、神が人間に道徳や目的を与え、人間の自由は神の意志という枠内で位置づけられていた。だが、その神が不在となるなら、人間は自己の行動と意味のすべてを自ら決定しなければならなくなる。
このとき、人間はもはや他者や超越的な存在に拠って生きることができず、全面的な自由を引き受けることになる。サルトルは、この状況を「自由への刑」と表現し、逃れることのできない選択の連続、そしてその責任の重さを指摘した。
自由とは解放であると同時に、不安(angoisse)と責任を伴う負荷でもあるのだ。
この思想は、近代以降の西洋社会における個人主義的伝統とも深く関わっている。
啓蒙主義以降、理性や主体性を拠り所とした自己決定の価値が強調される中で、神の死は逆説的に「自己の本質を自ら創造せよ」という過酷な課題を人間に課した。
サルトルの有名な命題「実存は本質に先立つ(l’existence précède l’essence)」は、まさにこの背景から導き出された。
伝統や宗教による意味づけが崩壊した世界において、サルトルは人間を意味の創出者として位置づけたのである。
レヴィ=ストロースからの批判

画像 : レヴィ=ストロース wiki © UNESCO
クロード・レヴィ=ストロースは、20世紀フランスの社会人類学者であり、構造主義人類学の創始者として知られる。
彼は1962年の著作『野生の思考』の最終章「歴史と弁証法」において、サルトルの実存主義に対して明確な批判を展開した。
その批判は大きく二つの柱に分けられる。
1・主体性の過剰な強調
レヴィ=ストロースは、サルトルの実存主義が「自由な主体」をあまりにも重視している点に異議を唱えた。
サルトルが描く人間像は、みずからの選択によって本質をつくり上げる自由な存在であるとされるが、レヴィ=ストロースにとってこの考え方は、西洋的な個人主義に強く依存しており、言語・神話・親族制度といった文化構造の制約を過小評価しているという。
彼は、人間の思考や行動は、個々の意識的な決定によってではなく、無意識の深層にある構造的な要因に大きく左右されると考えていた。
2・歴史観の西洋中心主義
さらにレヴィ=ストロースは、サルトルの歴史理解に対しても批判を加えた。
サルトルは、歴史を弁証法的にとらえ、人間の自由な主体的行為が歴史の進歩を推進すると考えていた。これに対し、レヴィ=ストロースは、こうした歴史観は西洋的な進歩史観に基づいており、非西洋の社会、特に「未開社会」に見られる共時的で循環的な思考様式を軽視していると論じた。
彼にとって、歴史を線形的に捉えるのではなく、構造の中における反復や変奏としてとらえることこそが、人間理解にとって不可欠であった。
このように、レヴィ=ストロースの批判は、サルトルの哲学が置かれている西洋的な前提構造そのものに向けられたものであり、実存主義の根幹を問い直す意図があった。
レヴィ・ストロースの批判に対する考察

画像 : 1967年。サルトル(前列左から2人目)の右側の女性がシモーヌ・ド・ボーヴォワール public domain
レヴィ=ストロースは、サルトルの実存主義に対し、「主体性の過剰な強調」と「歴史観の西洋中心主義」という観点から批判を加えた。
しかし筆者は、こうした批判はサルトルの思想の核心、すなわち「自由への刑」という命題の持つ普遍的な意義を見落としている可能性があると考える。
サルトルが『存在と無』において提示した「人間は自由への刑に処されている」という命題は、西欧キリスト教社会の価値崩壊を背景としている。だが、その主張は特定の文化に限定されたものではなく、人間一般に共通する状況を描写したものとして読むことも可能である。
実際、どの文化圏においても、人間は選択を迫られ、選択の結果に責任を負う場面に直面する。
仏教における「無我」の思想は一見、主体性を否定するようにも映るが、修行や悟りに向かう過程では、個人の意志と選択が不可欠である。また、アフリカの部族社会における神話や儀式にも、個人が共同体の規範に従うか逸脱するかという局面が存在し、そこには明確な選択とそれに伴う不安がある。
サルトルが言う「不安(angoisse)」とは、単なるキリスト教的な罪意識ではなく、自己の行動が世界に影響を及ぼすという自覚から生まれる責任の重みである。こうした感情は、西洋に限らず多くの文化で共有されうるものであり、「自由への刑」という表現は、文化的枠組みを超えて人間の在り方を射抜いていると考えられる。
もちろん、レヴィ=ストロースの批判がすべて的外れであるとは言えない。彼がサルトルの弁証法的歴史観に対して、西洋的な進歩主義への過度な依存を指摘した点には一定の妥当性があるだろう。ただし、それでもなお「自由への刑」は、構造に還元できない人間存在の一側面、すなわち逃れられない選択と責任の重圧、を描いている。
レヴィ=ストロースは、文化や言語構造の力を強調するあまり、個人が構造のなかで行う選択や逸脱の意義を過小評価しているように見える。サルトルの実存主義は、こうした構造の中にあってもなお残る「自由」に向き合い、それを引き受ける覚悟を描いた思想であろう。
構造主義は人間を分析の対象とするには有効だが、人間の主体的な問いや苦悩に対する応答としては限界があるようにも思われる。
おわりに
本稿では、サルトルの実存主義に対するレヴィ=ストロースの構造主義的批判を検討した。
その過程で見えてきたのは、「自由への刑」という命題が単に西洋的主体性やキリスト教的世界観に基づくものではなく、より広範な文化圏に通じる人間存在の普遍的構造を捉えている可能性である。
もちろん、レヴィ=ストロースの批判は、実存主義の限界を問うものとして一定の意義を持つ。だが、構造に還元され得ない人間の内的経験や選択の重み、そして不安の感情は、依然としてサルトルの思想の中核として残り続けるだろう。
サルトルの問い「人間とは何か」は、今日においてもなお、構造と主体、規範と自由のあいだで揺れる私たち自身の問題であり続けているのではないだろうか。
参考 :
ジャン=ポール・サルトル『存在と無』1943年『実存主義とは何か 実存主義はヒューマニズムである』1945年
クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』1962年
文 / 草の実堂編集部






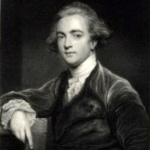


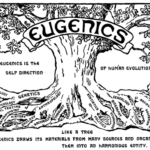















この記事へのコメントはありません。