伝承の中の武将と「千斤の武器」

画像 : 呂布と戦う桃園三兄弟(劉備、関羽、張飛)public domain
古代中国の戦場と聞くと、誰もがまず思い浮かべるのは、巨大な武器を軽々と操る猛将たちの姿だろう。
関羽の青龍偃月刀、呂布の方天画戟、張飛の蛇矛・・・
いずれも人ならぬ怪力で戦場を圧倒し、敵軍をなぎ払う伝説の戦士たちである。
たとえば『三国演義』では、関羽の青龍偃月刀は八十二斤、今の単位に直せば40キロを超えるという。
呂布の方天画戟は四十斤、曹操の配下・典韋の双戟は八十斤、さらに後代の『隋唐演義』では、唐の李淵の三男・李元覇(り げんは)の金槌は八百斤(約480キロ)にまで膨れ上がる。
もはや人間が扱える重量ではない。
しかし庶民の間では、こうした伝承や講談が繰り返し語られ、英雄たちは次第に現実を超えた存在として神聖視されていった。
特に関羽はその筆頭であり「関帝」として神格化されていく過程で、青龍偃月刀は聖なる象徴へと変わった。
赤兎馬と並び、刀そのものが「義と忠の化身」として祀られるようになったのである。

画像 : 関帝廟の前で行われた民俗演舞の様子 Zhexian Zhu CC BY-SA 4.0
しかし、この「千斤の武器を操る英雄」というイメージは、史実から見れば大きな誤解である。
まずは関羽の「青龍偃月刀」を手がかりに、史料の上でどのように誕生し、物語の中でいかに神格化されていったのかをたどっていきたい。
関羽は何を振るっていたのか
『三国演義』の関羽といえば、青龍偃月刀を振るい、敵将を次々と斬り伏せる猛将である。
しかし、史実を記した陳寿『三国志』を開くと、その姿はまったく異なる。
そこには「刀」という文字が一度も登場しないのだ。

画像 : 顔良を斬る関羽(白馬の戦い) public domain
『三国志・関羽伝』によれば、関羽が袁紹軍の名将・顔良を討った場面では「刺」と記されている。
つまり、彼が使っていたのは刀ではなく、槍や戟に近い“突き刺す”武器であった可能性が高いのだ。
当時の後漢末期は、長柄武器が主流の時代であり、刀は主に儀式や近接戦で使われる補助的な役割だった。
青龍偃月刀のような巨大な長刀は、この時代には存在していなかったのである。
それでは、いつから「関羽=青龍偃月刀」というイメージが生まれたのだろうか。
その源とされるのが、6世紀前半ごろに南朝・梁の道士・陶弘景(とうこうけい)が著した『古今刀劍錄(ここんとうけんろく)』である。
この書は、中国で最も古い刀剣の総覧であり、夏王朝から南北朝に至るまでの名刀を年代順に記したものだ。
ここに、関羽に関する次の一文が登場する。
關羽,為先主所重,不惜身命,自采都山鐵為二刀,銘曰「萬人」。及羽敗,惜刀,投之水中。
意訳 :
関羽は劉備に重用され、命を惜しまず、自ら武都山の鉄を採って二口の刀を鍛え、「万人」と名づけた。
敗北した際、その刀を惜しみ、水中へ投げ入れた。『古今刀劍錄』より
この記述は、『三国志』の成立から約300年後に書かれたものであり、史実というよりも「伝説の整理」として書かれたとみられている。
それでも、史料の上で関羽が「刀を持つ英雄」として登場するのは、ここが最初である。
つまり、青龍偃月刀伝説の原型は、この一文にあると考えられている。
その後、宋代に入ると、偃月刀という長刀の形式が実際に登場する。
重く湾曲した刃を持つ偃月刀は、破壊力はある一方で「取り回しにくく、反撃を受けやすい」という欠点があり、主に実戦ではなく訓練用として使われた。
そのため、後世の人々は「関羽の大刀」を視覚的に再現できるようになり、物語や絵画の中で次第に“実在した武器”のように描かれていった。

画像 : 台湾・台南の祀典武廟に祀られる主神・関聖帝君(関羽)の象徴である青龍偃月刀 Candyji CC BY-SA 4.0
また、「青龍偃月刀」という名称が文献上に現れるのは、明代の『三国演義』である。
小説では、関羽が満月の夜に天下第一の鍛冶職人に命じ、刀を鍛える場面が描かれている。
その鍛造の際、天から一千七百八十滴の血が降り、それが青龍の血であったという伝説が加えられた。
こうして関羽は、史実の将軍から、神話と信仰の世界に生きる「刀の聖者」となったのだ。
伝説の武将と現実の武器
前述したように、英雄の物語で語られる武器は、どれも常人には持てぬ重さである。
もし本当にそんな重量であったとすれば、人はおろか馬でも動かせない。
考古学の発掘によって見えてきたのは、物語とはまるで異なる「現実の武器の姿」だった。
その実像を、いくつかの例から見ていこう。
【呂布の方天画戟】

画像 : 赤兎馬に乗って進撃する呂布 public domain
「人中に呂布あり、馬中に赤兎あり」と称された最強の武将・呂布の武器として、とりわけ知られるのが方天画戟(ほうてんがげき)である。
『三国演義』では、その重さ40斤(約24キロ)とされるが、実際に出土した戟を見れば、その数字が誇張であることは明らかだ。
戦国〜漢代にかけての戟の実物は、刃の部分が40〜60センチ、全体の長さが2〜3メートル、重さは3〜5キロほど。
この程度であれば馬上で自在に扱うことができ、機動戦にも耐えうる。
呂布が駆る赤兎馬が戦場を駆け抜ける姿を思い浮かべれば、むしろ軽量武器の方が現実的なのである。
【張飛の蛇矛】

画像 : 清代の書物の黄巾の乱、劉備関羽張飛の三人 public domain
関羽と並ぶ蜀の猛将・張飛。
その愛用の武器として知られるのが丈八蛇矛(じょうはつだぼう)である。
『三国演義』では、その重量を五十斤(約30キロ)と伝えるが、実際の出土資料と比べれば、この数字も明らかに誇張である。
戦国〜漢代に使われた実際の矛は、刃の長さ40〜50センチ、全長2.5〜3メートル、重量は3〜6キロ前後にすぎない。
張飛が長坂橋で曹操軍を一喝し、数千の兵を退けたという逸話も、こうした実用的な武器を前提にすれば、まだ理解しやすいかもしれない。
【典韋の双戟 〜怪力伝説の系譜】

画像 : 典韋 public domain
曹操軍の猛将・典韋は、双戟を振るい「虎侯」と恐れられたが、『三国志』には重量の記載がない。
『演義』では80斤(約48キロ)とされるものの、明代の双戟の実物は片方で3〜4キロほどである。
また、冒頭で紹介した唐の英雄・李元覇は、『隋唐演義』で八百斤(約480キロ)の金槌(きんつい)を操ったとされるが、実際にそのような武器は存在せず、明清期に実物として確認される金瓜錘(きんかすい)でも重さは約1キロ前後にすぎない。
宋代の僧兵・魯智深が振るう禅杖は、62斤(約37キロ)と伝わるが、出土した鉄禅杖の実物はせいぜい2〜3キロだった。
つまり、多くの「怪力伝説」は武勇を強調するための誇張にすぎず、実際には現実的な重量だったと考えられる。
古代中国の武器は効率的に設計されていた
このように、出土した実物の測定や当時の記録を参照すると、古代中国の武器はむしろ軽量で、効率的に設計されていたことがわかる。

画像 : 西漢(前漢)期に製作された同時代の鉄剣。昆明市博物館所蔵の実物(同形式の出土例として掲載)public domain
前漢中期の墓葬から出土した鉄剣は、実測で全長66.2センチ、重さ約620グラム。
北周時代の将軍・李賢とその妻の墓(現在の寧夏回族自治区固原市)から出土した環首刀は、全長94.5センチ、重さ約1.3キログラム。
また、清代の軍制書『皇朝礼器図式』には、正規軍の装備として「双錘」が記されており、その重量は「各一斤三両」(約0.65キログラム)とある。
これらの史料や遺物が示すのは、古代中国の武器が決して「重いほど強い」ものではなかったという事実である。
実際の戦場では、機動力と持久力が勝敗を左右し、それは歩兵から将軍に至るまで例外ではなかっただろう。
だからこそ、武器は長期戦と行軍を前提に、「軽く・強く・扱いやすく」という設計思想のもとで作られていた。
誇張された英雄譚の武器とは対照的に、実際に戦場で使われていた武器は極限まで合理化されていたのである。
参考 : 『古今刀劍錄』陶弘景『三国志』陳寿 『三国演義』『隋唐演義』他
文 / 草の実堂編集部





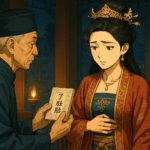



















三国志の時代だと製錬技術が足りず?重かったんだと思うけど
水滸伝の魯智深は、鍛冶屋に百斤とか関羽と同じ八十二斤の杖を注文しようとして断られ、使えなくても知らないぞと言われながら結局六十二斤のものを拵えた、と描かれているから、そんな重いの使えるわけないというのは明代の庶民にもわかっていたことだと思う