エピローグ

画像 : 真田信繁/真田幸村肖像画
しかし、秀吉の死後、事態は急変する。それは、天下人への野望を抱く徳川家康と石田三成ら豊臣家臣団の対立だった。
そして、ついに天下分け目の戦いと称される関ケ原の合戦が勃発。
真田昌幸と信繁は、石田三成らの西軍に味方し、上田城に徳川軍を迎え撃った。
石田三成・大谷吉継も喜んだ真田氏の西軍参戦
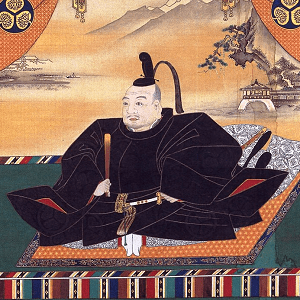
画像 : 久しぶりに大河の主人公となった徳川家康。public domain
豊臣秀吉の死後、豊臣政権で五大老筆頭の地位にある徳川家康は、大坂城西の丸において、諸大名への加増・転封を裁断するなどその権力を強めていった。
これに危機感を抱いた石田三成ら豊臣家臣団は、1600(慶長5)年、家康が会津の上杉景勝討伐に出兵した隙をついて挙兵した。
これが関ケ原の合戦であり石田方を西軍、徳川方を東軍という。

画像 : 石田三成 public domain
この事態に真田昌幸は、信繁が姻戚関係のある三成の西軍へ、信之は家康の養女・小松姫を正妻としていたため東軍につくという決断を下した。
三成は、昌幸・信繁が味方に付くと、「信州の仕置き、彼の人(昌幸)仰せ付けられ候事」(『信濃資料』)と喜び、信繁の岳父・大谷吉継も「御両所(昌幸・信繁)の御内儀、我等預かり分に仕り候事」。さらに三成は「各々御内儀方大刑少(大谷吉継)馳走申され候条、御心安かるべく候」との書状を送り、昌幸・信繁の妻子を保護したことを知らせた。
5千人の寡兵で徳川秀忠4万の大軍を撃破する

画像:上田城大手門(写真:上田市)
昌幸・信繁は、上杉討伐軍から離脱すると急ぎ上田城に戻り、5,000人の兵で守りを固めた。上田城を包囲したのは、中山道を西に向かう徳川秀忠率いる38,000人の大軍だった。
この軍勢は、東海道を行く家康本隊の別動隊で、中山道沿いの西軍勢力を駆逐しながら行軍することが決められていたようだ。
そのことは秀忠自体が「真田表仕置の為出陣せしめ候、此の表隙明け次第上洛せしむべく候」と書状で宣言をしていることでも伺える。

画像 : 徳川秀忠 public domain
昌幸は上田城内から指揮を執り、第一次上田合戦後に整備した城外の居館・寺院などの砦に伏兵を置き、外堀の神川の水を堰止めて徳川勢に対峙した。
この時、信繁は砥石城を固めていたが、兄・信之が同城の寄せ手であると知ると、即座に開城し上田城に入った。
上田城外郭を破った徳川軍は真田勢を小勢と侮り、一気に押し潰そうと城下の三の丸に侵入した。三の丸は複雑で狭い隘路で構成された、上田城防御のための拠点だった。そこに溢れかえった状態で、徳川軍は上田城二の丸に迫った。

画像:上田城三の丸・御屋形跡(撮影:高野晃彰)
その時、突然大手門を開いて信繁隊が突出し、同時に各砦から伏兵が出て徳川勢に突撃した。この攻撃に混乱した徳川勢は、我先に退却した。
昌幸は、徳川勢が神川を渡っているところに、堰止めていた水を一気に落としたたため「我軍大ひに敗れ、死傷算なし」(『烈祖成蹟』)という大惨情をきたした。
またしても昌幸は、巧みな戦術で徳川の大軍を撃破し、真田の武名を天下に轟かせたのだ。

画像:上田城の砦の一つ海禅寺(撮影:高野晃彰)
この戦いにおける作戦の大要は昌幸が立てた。
だが、自兵の突撃や堰の水を落とすタイミングなど、作戦の成否を左右する局面において、信繁は実戦部隊の大将として見事な用兵術をみせた。
徳川秀忠は、この敗戦に大いに悔しがったが、「上方へ急げ」との家康の厳命が届くと、当初の予定を変え中山道を急いだ。しかし、関ケ原に着陣したのは、戦いの決着がついた後で、家康から激しい叱責を受けることになる。
昌幸・信繁は、わずか5,000人の軍勢で、東軍の半分の勢力を足留めするという大戦果を挙げたのだった。
紀州九度山に配流。昌幸の死と失意の蟄居生活

画像:信繁が蟄居生活を送った九度山の真田庵(写真:高野晃彰)
真田氏の奮戦もむなしく、関ケ原の戦いは東軍の勝利に終わった。
大谷吉継は、壮絶な戦いの後に自刃。石田三成は大坂城を目指し戦線を離脱したものの、伊吹山中で捕らえられ、処刑されてしまった。
孤立無援となった昌幸は上田を開城し、東軍に降った。本来ならば死を免れなかった昌幸・信繁だが、信之や本多忠勝(妻小松姫の実父)の必死の嘆願により助命された。
真田父子はその身柄を、高野山の山麓・紀州九度山に移され、蟄居生活を余儀なくされた。そして、昌幸は、1611(慶長16)年に失意のうちに没する。武田氏・徳川氏・北条氏・豊臣氏を手玉に取った稀代の謀将としては、余りに寂しい死だった。信繁もまた、連歌や酒に無聊を慰めながらの生活を続けることになった。
次回は、第5回として信繁の大坂入城と、出丸真田丸での奮戦を大坂冬の陣編として紹介しよう。
※参考文献
高野晃彰編・真田六文銭巡礼の会著『真田幸村歴史トラベル 英傑三代ゆかりの地をめぐる』メイツユニバーサルコンテンツ、2015年12月












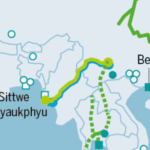











この記事へのコメントはありません。