みすずの結婚と出産

大正十三年、西條八十が突然フランスへ留学する事となり、選者の変わった『童話』にみすずの作品が載る事が少なくなっていくのである。
翌年大正十四年、テルの縁談話が持ち上がる。この年はテルにとって受難の年でもあった。先に述べた「渡邊豊乃代」が亡くなり、泣き伏せる事が多くなり、正祐はテルを少しでも慰めようとして「テルちゃん・テルちゃん」と二人きりになるのである。
「姉と弟で間違いがあったら、どないするんや」
と松蔵。
「正祐は知らんでも、テルは知っちょりますけぇ、間違いなんか絶対にありません」
と母ミチは言う。
職業紹介所を通じて、文英堂に「宮本啓喜(みやもとけいき)」という男が入った。後のテルの結婚相手である。
彼は背丈はすらりとし、切れ長の目が涼し気である。笑顔もいい。仕事っぷりも真面目であった。テルより年齢も二つ上である。熊本人吉に生まれ、実家はかき氷シロップの製造販売を営み裕福であった。継母との折り合いが悪く、十代で生家をで、株式仲買人に奉公する。
13歳の時、第一次世界大戦が始まり株価はみるみる上がっていった。しかし大戦が終わると株価は暴落、啓喜は全財産を失う。そこで実家のシロップを博多で売りさばいたが、売り上げ金を遊女に使い、勘当され辿り着いた場所、そこが「上山文英堂書店」だった。
宮本の「女癖」は、松蔵も知っていた。
しかし若い頃は自分も多少は遊んだものだ・・と、ゆくゆくはのれん分けして『宮本書店』をと、松蔵は秘密裡に話は進めていた。
そんな時、正祐に徴兵検査の通知がきたのである。正祐はこの時、初めて自分の「出生の秘密」を知る事になる、
書面に「松蔵養父」と書かれていたのである。
そんな時、仙崎の兄が「パラチフス」という病気になり、妻のチウサが実家に戻ってしまうという事態が起こったのである。テルは「兄の看病」という事で仙崎に帰されたのだった。
その後テルは手紙で「仙崎に来ないか」と正祐に宛てて書き、正祐は仙崎に飛んでいくのである。回復した兄堅助とテル・正祐。
奥の座敷で三人でテルの結婚問題を話し合った。
テルは「まあちゃん、話したいことがあるけえ、散歩せんかね」二人三条山という小高い丘に立つが、テルは沈黙を続ける。
正祐「テルちゃん本当は誰か好きな人でもおるんじゃないかね」
テル「私がいつまでも上山の家におれば、大将の世話になって迷惑をかける。私が受ければみんな丸く収まるけえ」
正祐「もしかすると、テルちゃんと僕は・・姉と弟、かいね」
テルは一瞬迷うそぶりを見せ、それから無言のままうなづいた。面をあげて弟を見つめた。
大正15年2月17日、テルは宮本啓喜と上山文英堂の座敷で挙式を挙げた。
宮本との結婚生活は決して「幸せ」とは言えなかった。上山文英堂の二階で新婚生活が始まるが、正祐と啓喜の間でテルは繊細な心を傷つけられていた。啓喜の仕事ぶりは、正祐の嫉妬をかい、正祐は自己嫌悪に陥り家出をするのである。
松蔵は店員の前で啓喜に対して「正祐が家出したんは、お前と上手くいかんのを悩んどったんや」を、怒鳴りつけた。
「息子が店を出るくらいなら、お前に出ていってもらいたい。お前はどうするんや、テル。啓喜が店をでたら、わしに従って上山家に残るか?啓喜と出ていくか!」
正祐に何かあれば、松蔵は啓喜に当たる、啓喜は言われのない屈辱を受ける。
啓喜はこの頃から次々と女性問題をおこし、派手な遊びを続けていくのである。
それを知った松蔵と母ミチは「テルは籍を入れちょらんけえ、今のうちに離縁させた方がええかもしれん」と模索するがテルは身ごもっていた。
離婚の話は流れ、啓喜とテルは貸家に移った。文英堂から歩いて20分ほどの小さな平屋であった。
この春、西條八十は帰国し『童話』4月号にテルの作品「露」が特別募集第一席になるのである。
「露」 金子みすず
誰にも言わずにおきましょう。朝のお庭のすみっこで・・
お花がほろりと泣いたこと。
もしも、噂がひろがって、蜂のお耳へはいったら・・
悪いことでもしたように・・密をかえしに行くでしょう。
しかし翌月『童話』の休刊が決まり、そのまま廃刊となる。テルも悲痛な面持ちだったが
「今は詩の事より、おなかの子を元気に産む事を一番に考えたいけえ。先の事は、赤ちゃんが産まれたらまた、考えるわ」
とお腹をさするテルだった。
朗報もあった、童謡詩人会編「日本童謡集」に『大漁』と『お魚』が掲載された。
『童話』は廃刊になったが、西條八十が主催になり『愛誦』に「繭とお墓」と「明るい方へ」が掲載されたのである。
明るい方へ 金子みすず
明るい方へ・・明るい方へ。一つの葉でも 陽の洩るとこへ。
藪かげの草は。
明るい方へ・・明るい方へ。翅(はね)は焦げよと灯のある処へ。
夜飛ぶ虫は。
明るい方へ・・明るい方へ。一分もひろく陽の射すところへ。
都会に棲む子等は。
明るい光に向かってテルも生きていこうと決心する。
大正15年・昭和元年9月テルの出産を前に啓喜は婚姻届けを出した。
11月14日 命名ふさえ誕生である。テル23歳、啓喜25歳の冬の時期であった。その女の子は色白のところはテルから、目鼻たちは父から受け継いでいた。
昭和二年元旦、テルと夫が年始に訪れた。テルは二カ月になるふさえが愛らしく「ふーちゃん・ふーちゃん」と呼び、テルも目に見て以前より明るくなった。
知的だった芸術の友(テル)の変貌ぶりに正祐は落胆するあまり「テルちゃんは、平凡になりましたね」と素っ気なく声をかけ、心満たされぬまま「遊郭」に憂さ晴らしに出る様になる。正祐の遊びはエスカレートし、店の金まで黙って持ち出す様になる。父松蔵と母ミチの間にも正祐をめぐり波風が立っていた。
正祐が無様にのた打ちまわっている間も、テルは乳飲み児を抱えながら、少しづつ詩作を続けていた。西條八十が選を務める『愛誦』昭和二年・二月号に「月と泥棒」三月号に「さみしい王女」四月号には「雲」と「ひな祭り」が掲載された。
さらにテルは編集部を通して西條八十と文通もしていた。その八十が下関に来るというのである。八十はあらかじめ電報で知らせていた。テルは最愛の師に会うために、下関駅に駆け付けた。その時のテルの様子を八十はテルの死後「蝋人形」昭和六年九月号に記した。

※西條八十
・・彼女と短い対面をしたのは、昭和二年の夏と覚えている。ようやくほの暗い一隅に人目をはばかる様に、佇んでいる彼女を見出したのだが、彼女は一見、二十二~三歳に見える女性で、とりつくろわぬ蓬髪に、普段着のまま、背には我が児を負っていた。
作品に於いて「クリスティナ・ローッゼティ女史」におとらぬ華やかな幻想を示していたが、この若い女詩人は初印象に於いては、そこいらの裏町の小さな商店の内儀のようであった。しかし彼女の容貌は端麗で、その瞳は黒曜石の様に深く輝いていた。
「お目にかかりたさに、山を越えてまいりました。これからまた山を越えて家へ帰ります」と彼女は言った。・・・
テルはこの日の興奮を上山文英堂の店員に、嬉しそうに話したのであった。
本当は正祐に聞いて欲しかったが、正祐は「遊郭」の帰りで酔っぱらって寝ていたのである。
昭和二年、この年は訃報も多かった。仙崎の祖母ウメが死んだ。猛スピードの自転車に衝突され大怪我を負い、痛ましい事故だった。
さらに啓喜が店を辞めたのである。
愛娘との別れ

啓喜は上山文英堂を見限っていた。正祐の度の過ぎた花街遊び・そんな男が店主になる本屋に将来性はない。しかも松蔵の払う給金は安く、妻子を抱えた暮らしは苦しかった。
啓喜はテルを連れて熊本へ帰ったが、11月にテルと娘を連れて帰ってきた。
しかし、文英堂には帰らず下関市上新地の借家で「宮田食料玩具店」を開いたのである。
屋号は辰巳屋である。子供の駄菓子やメンコ・ビー玉・おはじき等を大阪の玩具商から買い付けて仲買いに卸すのである。店は軌道にのり山口県内はもとより九州各地にも卸す様になり、熊本の身内を雇った。
テルは商売はせず、家事と子育てをした。文机に向かい童謡を書き「愛誦」へ送る、また本を読み、投稿仲間に手紙を書く、テルは一人の世界に充実する女だった。
啓喜は家に帰ると、一心に机に向かう妻の背中に声をかけずらく、人好きである啓喜は女としてのテルに飽きたらなさを覚えたのである。金回りがよくなった啓喜は、女郎遊びを始め、テルは淋病にかかった。郭遊びの夫からうつったのだ。
昭和二年が終わろうとしていたテル24歳の時だった。
テルは淋病を治すため通院していたが、病状が進み不安な日を送っていた。
女性が感染した場合、子宮の炎症に始まり、悪くすると身体の奥へ菌が広がり、腹膜へ。
また尿道や直腸にも炎症を起こし、出血、排尿の痛み、血便、高熱を発し、腹部の痛みから歩く事も難しくなる。テルは病気が病気だけに正祐には伝えていなかった。
テルは再び夫の浮気を思い悩んでいた。血膿まじりのおりものがあり、もはや夫と接することはなかった。夫が外に女を求めるのは仕方ないと諦めながらも、元はと言えば啓喜がもたらした病気だと思えば心は穏やかではない。啓喜は日が暮れると着物をかえてかすかな後ろめたさを漂わせ出掛けていくのである。
啓喜は自分の事を棚にあげ、テルには
「娘が学校にあがるまではせめて母親がずっと見てやってくれんか!母親がよぉ側にいてほかん事に夢中になっとる寂しさは、ふさえに感じさせんでほしか。詩人は世の中に大勢おる!ばってん、ふさえの母親は一人しかおらんけんな!!」
と、テルの創作と手紙を書く事を禁じるのである。
「私と小鳥と鈴と」金子みすず
私が両手を広げても お空はちっとも飛べないが
飛べる小鳥は 私のように、地面は早く走れない。。
私がからだをゆすっても きれいな音は出ないけど
あの鳴る鈴は 私のように たくさん唄は知らないよ。。
鈴と、小鳥と、それから私・・みんなちがって みんないい。
そんな夫の仕打ちに対して、テルが精一杯の悲しみの抗議をしているかの様な作品である。
みんな違うが、みんなあるがままの尊い存在なのだと、テルは唄うのである。
そしてこの年(昭和四年)テルは結婚してから、今までの童謡を三冊の作品集として清書し始める(一組は西條八十に、もう一組は正祐に託す)
夫から移された淋病の為に、この頃から精神的な疲労も重なり、次第に悪化し入退院を繰り返し、一人娘「ふさえ」の成長だけが慰めであり、生きる支えであった。そんな様子が伺えるハガキがある。テルが母ミチに当てたものである。
「二十日に起きるつもりで、雑巾がけを少ししましたらすぐたたりまして、また五日休みました、ふうちゃんは昨日まで三日ほど、お父ちゃんと熊本へ行きました。割合にお行儀はよかったそうです(略)」
そしてテルは、満三歳になる娘の、まだよく回らない愛らしい言葉をノートにつづった。
テルはこのノートを「南京玉」と名付けた。病気が進んだテルは、我が子といつまで一緒にいられるか、先行きを思いわずらった。「南京玉」は、母がいかに幼い娘を可愛がり慈しんだか、ふさえに遺す愛の記録だった。
『南京玉は七色だ。一つ一つが愛らしい。尊いものではないけれど、それを糸につなぐのは、私には楽しい。この子の言葉もそのように、一つ・一つが愛らしい。人にはなんでもないけれどそれを書いてゆく事は、私には何ものにも変えがたい楽しさだ・・(以下略)』~「南京玉」・巻頭~
昭和五年2月27日 テルと啓喜は正式に離婚する。
テルと娘ふさえは「上山文英堂」に移転、自分の残された時間を今は、ふさえの為だけに使いたい・・テルは考えていた。しかし当時の離婚後の子供の親権は「父親」にあった。
「離婚になったのは申し訳なかとばってんが、テルが別れたい言うもんで。それに結婚はわしが望んだもんやなかと。大将が『のれん分けしてやる』って言われたもんで、一緒になったとです。結局は店ば、出たとです。それで自分で商いば始めたもんの、この不況で儲けばなかとです。ふさえはわしにとっても一人娘ですけん。女房の勝手で別れとって娘ばよこせと言われるなら、それなりのつぐないというもんがいるんじゃなかと!」
何度も何度も、啓喜は「ふさえをよこせ」と言ってくる。テルの元に置くなら、金をよこせと要求する啓喜である。
そして啓喜は「3月10日にふさえを連れにいく」とテルに最終通告をするのである。
まとめ
昭和五年、3月9日テル26歳、昼ご飯を食べふさえを母に預け、上山文永堂書店から徒歩10分、三好写真館へ行き一枚の写真を撮影、帰るすがら「桜もち」を購入する。
夕飯の後、テルとふさえは風呂へ向かう。テルは今まで自分の病気を考え一緒に入る事はしなかった。その日テルは、ふさえをキレイにしてあげたい気持ちで、着物をまくりふさえの身体を丁寧に、優しく洗う。ふさえは裸で、松蔵と母ミチの元へ走っていく。
テルは丁寧にふさえの身体を拭き、着物を着せ買ってきた「桜もち」をみんなで食べる。
「おいしいね」もう一つとねだるふさえ。楽し気に語りあい、普段と変わらないひとときである。
「そろそろ、おねんねしましょうか」ミチに手を引かれ布団に入るふさえ。
テルは、桜もちとお茶の片づけをし、松蔵に「おやすみなさい」と挨拶をし、ふさえの寝顔を見て「かわいい顏して、寝とるね・・」テルの最期の言葉であった。
昭和五十七年、東京西荻窪にある劇団若草、上山雅輔(本名:正祐)から、テルの三冊の手帳の童謡集と写真が矢崎節夫氏に託された事により「詩人・金子みすず」が再びよみがえり、平成3年「金子みすず生誕100年」を迎えるのであった。
「繭と墓」金子みすず
蚕は繭に入ります・・きゅうくつそうな あの繭に。
だけど蚕は うれしかろ。蝶々になって飛べるのよ・・
人はお墓へ入ります・・暗いさみしい あの墓へ。
そしていい子は 羽が生え、天使になって飛べるのよ・・
2







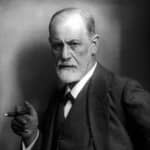










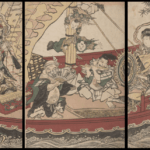





この記事へのコメントはありません。