劉備(りゅう び。字は玄徳)と言えば、戦乱の世を治めるべく立ち上がった仁徳の英雄として知られ、『三国志』の中でも高い人気を誇っています。

聖人君子のイメージから、徐々に変わりつつある劉備。
その一方で、窮していたとは言え次々と主君を変えた挙句、すべて裏切って皇帝にまで成り上がった梟雄でもあるため、最近では従来の聖人君子キャラを脱却、「人を喰ったヤツ」として描かれる作品も増えてきました。
そんな「人を喰った」劉備が、比喩ではなく本当に「人間の肉を喰った」エピソードが歴史小説『三国志演義』にあったので、紹介したいと思います。
地獄に仏……逃亡中の劉備、狼料理をご馳走になる
時は建安元196年ごろ、呂布(りょ ふ。字は奉先)に攻められて逃亡した劉備は、妻子を捕らわれ、義兄弟や家臣たちともはぐれて途方に暮れていました。
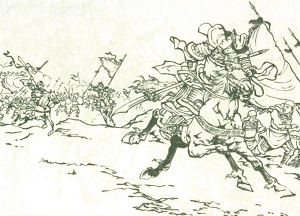
呂布に敗れ、逃げ惑う劉備たち(イメージ)。『三国志連環画』より
「いよいよ俺も、年貢の納め時かも知れねぇな……」
山の中をさまよい歩いていると、前方からやって来た家臣の孫乾(そん けん。字は公祐)と再会。よっぽど心細かったのか、二人は肩を抱き合って泣いたそうです。
「我が君……ご無事で何よりにございまする!」
「あぁ、良かった良かった……さぁ、早く安全なところまで逃げようぜ」
二人が曹操(そう そう。字は孟徳)を頼って落ち延びる道中、一軒の民家を発見しました。
「もうし、御免下され。道に迷ってしもうて、一晩宿をお借り出来まいか」
「はいはい……あぁっ、玄徳様ではございませぬか!」
出て来たのは劉安(りゅう あん。字は不詳)という猟師。この山奥に、妻と老母の三人で暮らしていました。
同じ劉姓のみならず、かねがね劉備の仁政を慕っていたため、喜んで迎え入れます。
「何とおいたわしや……さぁさぁ、こんな粗末なあばら家ではございますが、どうか心ばかりのおもてなしをさせて下され……」
地獄に仏とはまさにこのこと……すっかりくつろいだ劉備たちに、劉安が申し出ました。
「あいにく食材がございませぬゆえ、これより狩りに出て参ります。食事の支度が調いますまで、暫しごゆるりと……」
そう言って狩りに出かけた劉安ですが、それから数刻経っても帰って来ません。
「何かあったのでしょうか……ご無事だといいのですが……」
みんなで心配していましたが、日もとっぷりと暮れた頃、ふらふらになった劉安が帰って来ました。よほどの事があったようで、その顔色も半日前とは別人のようにげっそりとしています。
「……ようやく狼が獲れ申した。これより調理いたしますゆえ、いま暫しお待ち下され……」
劉安が妻と二人で厨房に入っていくと、程なく料理が出来上がりました。
「大変お待たせ致しました。どうかお召し上がり下され……」
「奥方様は?」
「はい。家内は少し具合が悪くなったので、先に失礼させて頂きました」
「そうでしたか。どうかお大事にして下され」
「もったいなきお言葉。家内もすぐによくなりましょう……」
かくして狼料理を腹いっぱいに堪能した劉備たちは、ぐっすりと休んで英気を養ったのでした。
狼と思って食べた肉は……
そんな翌朝。劉備が目を覚ますと、裏庭で野良犬が人間の腕をくわえているのを発見します。
「ギョッ!?」
見ると女性の腕らしく、血痕を辿っていくと厨房で劉安の妻が死んでいました。その遺体は片腕と片脚が切断され、内臓も抜いたようで、腹も割かれています。
「「いったい、誰がこんな事を!?」」
「……それがしにございまする」
劉安が涙ながらに語るところでは、実は狩りに出たものの一頭も獣が獲れず、それでも劉備をもてなしたい一心で、泣く泣く妻を殺して狼の肉と偽ったという事です。

『絵本通俗三国志』より。「劉安妻の肉を煮て玄徳に献ず」
「敬愛する玄徳様を欺いてしまったこと、お詫びの致しようもございませぬ!」
「いや、そこまでせんで良かったのに……」
ともあれ、殺してしまったものは仕方ありません。せめて妻の死を無駄にせぬよう、劉安の忠義に報いようと自分に仕官するよう誘った劉備ですが、「老母を残してはお供できない」と辞退されてしまいました。
現代人の感覚からすれば人肉を提供する時点で既にアウトですが、それでも誰かを犠牲にしなければならない極限状況だったとして、劉安の立場であれば老い先短い母親を殺しそうなものです。
しかし、儒教においては親のために子が死ぬのはむしろ推奨される孝行であり、また男尊女卑の価値観が根強い事から、妻が殺されたのでしょう。
それが当然の選択として受け入れられていたことは、後にこのエピソードを聞いた曹操のリアクションからも明らかです。
「おぉ、何と健気な……それほどまでに忠良な人民に恵まれて、玄徳殿は羨ましいのぅ」
さっそく曹操は孫乾に命じて金百両を届けさせたのでした。
終わりに
以上は『三国志演義』第19回からのエピソードですが、劉安は架空の人物であり、その妻が殺されたという記録(史実)も存在しません。

イメージ
なーんだ、良かった……と思う一方で、わざわざフィクションのエピソードを盛り込んででも「ここまでのもてなしを受けるほど、劉備が人々から慕われていた」ことをアピールしている訳で、
「敬愛する主君のためなら、妻を殺した肉を提供する行為が忠義として評価される」
「夫婦と母親(姑)がいた場合、夫≧母親>妻の優先順で保護すべき」
という価値観があったことには変わりません。
現代日本人には到底理解しがたいものですが、作家の吉川英治氏は小説『三国志』の執筆に際して異例の註釈を入れ、「いざ鎌倉(鉢の木)」のエピソードに喩えています。
しかし、いくら大切なものを犠牲にするのでも、妻と盆栽を比較するのはいささか苦しいのではないでしょうか(もちろん、吉川氏も両者が「狼肉の味と梅花の香りほど違う」旨を述べています)。
他にも『三国志』では人間の肉を食ったエピソードがあるので、もし「怖いもの見たさ」で興味が湧いた方は、調べてみると面白いでしょう。
※参考文献:
羅漢中『奇書シリーズ 三国志演義 上』平凡社、1972年7月
吉川英治『三国志(三) 草莽の巻』新潮文庫、2013年2月








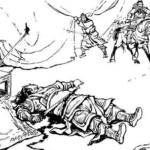












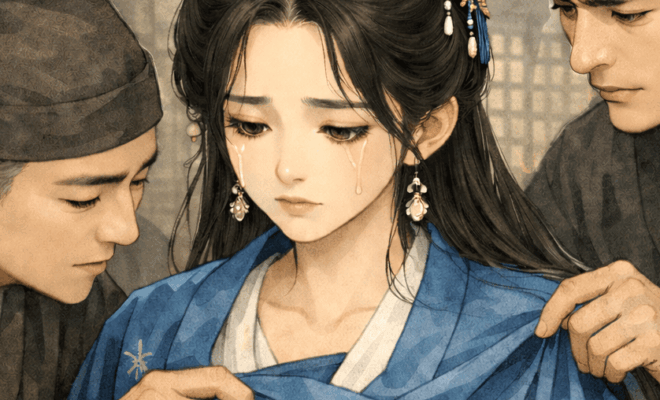



この記事へのコメントはありません。