幕藩体制の安定と確立を推し進めた徳川家光

画像:徳川家光 public domain
江戸幕府第三代将軍・徳川家光。
第二代将軍秀忠の嫡男でありながら、一時は廃嫡の危機に立たされたことでも知られている。
その理由としては、秀忠の正室であり生母でもある江(こう)が、弟の忠長を偏愛していたことや、家光が吃音であったことなどが挙げられる。
しかし、家光は決して将軍としての資質に欠けていたわけではなく、むしろ政治的手腕においてはなかなかに優秀であったと評価されている。
家康・秀忠と続いた徳川将軍家は、家光の治世に至って、ようやく戦国の混乱から脱しつつあった。
とはいえ、天草・島原一揆をはじめ、家光の死去直後には由井正雪の乱(慶安事件)が発覚するなど、なお幕府体制には不穏な火種が残されていたのも事実である。
そのような時代背景のもと、家光は祖父・父から受け継いだ武断的統治を徹底し、『武家諸法度』に参勤交代を加えるなど、幕藩体制の安定と確立を強力に推し進めたのである。
若気の至り?家光が後悔した出来事とは

画像:青山忠俊 public domain
ところが、そんな家光にも後悔してやまなかった出来事があった。
それが、傅役(もりやく)を務めていた大名、上総国大多喜藩主・青山忠俊(あおやまただとし)を、些細な理由で改易してしまったことである。
その理由として後世に広く語られてきたのが、家光の「女装趣味」を忠俊が厳しく批判したことが、決定的な亀裂を生んだとする逸話である。
戦国乱世における後継者争いに終止符を打つため、家康は嫡男による将軍家の継承を明確に進めていた。
その一環として、家光が12歳になると、三人の教育係が付けられたとされる。
その顔ぶれは、沈着ではあるが寡黙な酒井忠世(さかいただよ/上野国厩橋藩・第2代藩主)。

画像:酒井忠世 public domain
温厚な人柄で、優しく諭す土井利勝(どいとしかつ/下野国古河藩・初代藩主)。

画像 : 土井利勝 public domain
そしてもう一人が、厳しく歯に衣着せぬ物言いをする青山忠俊であった。
この三人のうち、家光に対して最も深い愛情を抱いていたのは忠俊だった、ともいわれている。
それは、幼少期から生母・江に疎まれ、孤独を抱えて育った家光の心情を、誰よりも理解していたからかもしれない。
忠俊はつねに家光に寄り添い、大地震が起きた際もすばやく家光を抱き上げ、我が身を挺して家光をかばったと記録に残っている。
しかし忠俊は、言葉だけでなく、家光への接し方そのものも厳しかった。
自分の教えや意見に家光が反発しようものなら、佩いていた両刀を投げ捨て、もろ肌を脱いで詰め寄り、「言うことが聞けぬのであれば、この青山の首を刎ね、どうとでもなされよ!」と叫ぶのが常であったという。
この態度に、少年家光が憤懣やるかたない思いを訴えると、酒井忠世や土井利勝が駆けつける。
そして家光の話を丁寧に聞いたうえで、
「若様のお気持ちも重々承知しております。しかしながら、やはり青山の言い分には道理があるように思われます。ここはひとつ、青山の申すとおりになさってはいただけませんか」
と、静かに諭したという。
「女装」を咎められ青山忠俊を改易処分に?

画像:出雲阿国による傾奇者のイメージ public domain
しかし、その数年後、ついに事件は起きた。
ある日、いつものように忠俊が出仕すると、家光は周囲に鏡を立て並べ、化粧をしていた。
忠俊が「何をなさっておられるのか」と問うと、家光はこともなげに、近習たちと踊りを楽しむのだと答えた。
当時はなお戦国の気風が色濃く残る一方で、傾奇者(かぶきもの)と呼ばれる者たちの奇抜な風俗が流行していた時代でもあった。
江戸の町中では、傾奇者たちが女性のように化粧を施し、派手な装いで踊り狂っていた。
家光は、当時流行していた傾奇者たちの姿に強い関心を示し、女装して化粧を施し、近習たちと踊ろうとしていたと伝えられている。
もちろん、そのような家光の振る舞いを忠俊が許すはずもない。
伝えられるところによれば、忠俊は激しく憤り、「これが天下を預かる将軍家の御所業か。かようなことに心を奪われるとは、まことに情けない!」と叱責し、化粧台を庭へと投げ捨ててしまったという。
これには家光も大激怒した。
近習たちの前で恥をかかされたとして、「無礼千万なり!」と忠俊を叱責し、所領を減封したのである。
それでも怒りの収まらぬ家光は、1623年(元和9年)に将軍職に就くと忠俊を老中職から解き、さらに寛永2年(1625年)には改易処分としてしまった。
この後、青山家は浜松に縁を頼って蟄居し、蓄えを切り詰めながら、川で魚を獲り、野から菜を得るなどして自活の生活に入った。
食べ物はもちろん、酒すら買えないほどの窮乏に追い込まれ、厳しい日々を送ることを余儀なくされたのである。
そして青山家が再び大名として立て直されるのは、忠俊の死後3年を経た1648年(正保5年)のことであった。
それは、改易から実に20年以上を経てようやく果たされたのである。
参考 : 『徳川実紀』『日本史を暴く』磯田道史著 中央公論新社刊 他
文 / 高野晃彰 校正 / 草の実堂編集部















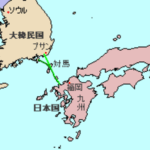








この記事へのコメントはありません。