国家の安全保障において、情報の保全は生命線である。
かつてのスパイ活動といえば、軍事機密の奪い合いが主たる戦場であったが、高度情報化社会となった現代においては、先端技術や経済情報の窃盗が新たな主戦場となっている。
世界各国は自国の国益を守るため、スパイ防止法制を強化しているが、その運用実態は国によって大きく異なる。
民主主義国家における法と、権威主義国家における法。
その間には、決して埋まることのない深い溝が存在するのである。

画像 : 国家議論となるスパイ防止法 国会議事堂(東京都千代田区)Kakidai CC BY-SA 4.0
欧米諸国における法整備と司法の監視
まず、スパイ防止法制の歴史が長い、欧米諸国の実態を見ていく。
米国には1917年に制定された「スパイ防止法(Espionage Act)」が存在し、国防機密の漏洩に対して極めて厳しい罰則を設けている。
近年では経済スパイ法も整備され、企業秘密の窃取も国家安全保障の問題として扱われるようになった。
英国でも公務秘密法がその役割を担っており、MI5やMI6といった情報機関が国内外の情報収集で中心的役割を担い、警察と連携して強力な対スパイ体制を構築している。
しかし、これらの国々において重要なのは、捜査権限が強大である一方で、司法による厳格な監視機能が働いているという点である。
令状なき盗聴や拘束は原則として認められず、スパイ容疑で逮捕された場合でも、公開の法廷で弁護を受ける権利が保障されている。
すなわち、国家の安全を守るための「剣」と、市民の自由を守るための「盾」が、緊張関係を保ちながら共存しているのが欧米のスタンダードである。
恣意的な運用が招く恐怖と不透明さ
対照的なのが、中国やロシアといった権威主義体制をとる国々の実態だ。
特に中国では、2014年の反スパイ法制定、そして2023年の改正により、スパイ行為の定義が極めて広範かつ曖昧なものへと変貌した。
「国家の安全と利益に関わる資料」の提供が処罰対象となるが、何が「国益」にあたるのかは当局の解釈次第である。
現地の風景写真を撮影しただけで、あるいは現地のコンサルタントと市場調査を行っただけで拘束されるリスクが、そこには存在する。
司法の独立性は希薄であり、一度拘束されれば、弁護士との接見も制限される密室での取り調べが待っている。
ここでは法は市民を守る盾ではなく、統制を強めるための武器として機能しており、在中国の外国人駐在員や研究者に萎縮効果(チリング・エフェクト)をもたらしている。
「スパイ天国」日本が直面するジレンマ
翻って日本はどうだろうか。
先進国の中で唯一、包括的なスパイ防止法を持たない日本は、長らく「スパイ天国」と揶揄されてきた。
特定秘密保護法に加え、2024年に成立した安全保障分野のセキュリティ・クリアランス(適性評価)制度により、徐々に穴は埋められつつあるものの、欧米のような包括的なスパイ防止法とは依然として隔たりがある。
これには、戦前の治安維持法への忌避感から、国家による監視強化に対する国民の根強い警戒感が背景にある。
しかし、国際的な共同研究や機密情報の共有枠組み(ファイブ・アイズ等)において、情報の保全措置が講じられていない国は、パートナーとして排除されるリスクが高まっているのも事実だ。
経済安全保障の観点からも、法整備は待ったなしの状況にある。

画像 : 東京のレストランでも外国スパイはいる。redlegsfan21 CC BY-SA 2.0
自由への渇望と政府の統制
スパイ防止法を巡る議論は、究極的には「国家の安全」と「個人の自由」のバランスをどこに置くかという問いに帰結する。
国家の存立なくして個人の自由は守れないが、過度な統制は守るべき自由そのものを窒息させる。
海外の実態が教えてくれるのは、単に法律を作ればよいという単純な話ではないということだ。
重要なのは、その法を運用する権力が暴走しないよう、議会や司法、そしてメディアがいかに監視機能を果たせるかという、民主主義の成熟度そのものである。
日本がこれから進むべき道は、無防備な現状を放置することでも、隣国のような監視社会を作ることでもない。
自由を渇望する精神を保ちながら、現実的な脅威に対峙できる法と監視のシステムを構築することにある。
文 / エックスレバン 校正 / 草の実堂編集部





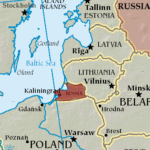

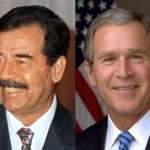







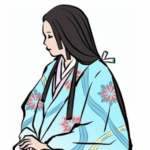









この記事へのコメントはありません。