「比丘尼」の本来の意味は、出家した女性

画像:中世末期の比丘尼像。『職人歌合画本』(国立国会図書館所蔵)
読者の皆さんは「比丘尼(びくに)」という言葉をご存じでしょうか。
比丘尼とは出家した女性、つまり尼さんのことです。
現代では宗派によって差はあるものの、「僧侶」と聞くと男性を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
2017年(平成29年)度の『宗教年鑑』によると、男女比が最も偏っているのは曹洞宗で97対3、最も差が小さい真宗大谷派でも85対15であり、やはり男性僧侶が圧倒的多数を占めています。
ところが歴史を遡ると、記録に残る最初の出家者は女性でした。
それは584年(敏達天皇13年)のことで、善信尼(ぜんしんに)ら、3人の女性が出家したのです。
善信尼は渡来人・司馬達等(しばだっと)の娘であり、有名な仏師・鞍作止利(くらつくりのとり)の叔母にあたります。

画像:鞍作止利が製作に関わったとされる飛鳥大仏 public domain
当時は、百済から仏教が伝来してからまだ30年ほどしか経っておらず、蘇我氏をはじめとする崇仏派と、これに反対する物部氏・中臣氏ら廃仏派が、激しく対立していた時代でした。
『日本書紀』には仏を「蕃神」と称する記述も見られ、朝廷内では依然として倭国古来の神々の力も強かったと考えられます。
そのため、出家した善信尼らは、当時の人々から仏という神に仕える巫女的な存在とみなされていた可能性もあるのです。
聖職者から売春婦へ堕落する
時代が下って鎌倉・室町時代以降になると、比丘尼は尼の姿で諸国を巡り、神仏の功徳を説きながら熊野神社の厄除け護符「牛王(ごおう)」を配り、お布施を得て生活する、いわば布教師のような存在となります。

画像:絵解きを行う熊野比丘尼『籠耳』public domain
こうした女性たちは、熊野比丘尼(くまのびくに)や、勧進比丘尼(かんじんびくに)と呼ばれていました。
当初、彼女たちは熊野の霊験や地獄・極楽の絵巻を解説しつつ念仏を唱えていましたが、やがて「ぴんざさら」という楽器を鳴らしながら歌を歌う形式で勧進を行うようになります。
このため、次第に絵解きよりも歌が中心となり、歌比丘尼とも呼ばれるようになりました。
そして彼女たちの歌は、しだいに卑俗で挑発的な内容へと変化していったのです。

画像:『人倫訓蒙図彙』(国立国会図書館蔵)
この変化について、江戸後期の戯作者・山東京伝(さんとうきょうでん、1761~1816年)は、随筆『近世奇蹟考』の中で次のように述べています。
「昔は脇に挟みし文匣(ぶんこう/ 紙で下張りをし、その上に漆をかけて作った手箱)に巻物を入れて、地獄の絵解きし、血の汚れを忌ませ、不産女(うまずめ)のあはれを泣かするを業とし、年籠りの戻りに烏牛王くばりて、熊野権現のこと触れめきしが、何時の程よりか白粉(おしろい)薄紅をつけて鬢帽子に帯幅広くなし……」
【意訳】
「昔の比丘尼たちは、手箱に巻物を入れて持ち歩き、地獄絵を見せては罪の恐ろしさを説き、不産女(子どもを産めず亡くなった女性)の悲しみを語って人々を泣かせることを仕事としていた。そして年の暮れの帰り道には、熊野三山の護符である牛王を配りながら熊野権現のご利益を説いていた。しかし、いつの頃からか白粉や紅をさし、髪を結い上げ、帯も華やかに装うようになってしまった……」
ここでいう「烏牛王」とは、熊野三山が発行した「牛王宝印」のことで、半紙大の紙に熊野神の神使・八咫烏(やたがらす)が多数刷り込まれた護符です。
熊野の神は虚言を正すと信じられていたため、この護符は起請文にも用いられました。
つまり、山東京伝は「かつては神聖な護符を配布していた勧進比丘尼が、やがて歌をうたい歩く歌比丘尼へと変化し、さらに化粧をして俗化し、遊女のようになっていった」と批判的に記しているのです。
「売比丘尼」を専門に扱う中宿

画像:熊野絵解き比丘尼 public domain
こうして、もとは仏法を説く尼僧であった比丘尼も、江戸時代になると、その姿こそ尼僧でありながら、実際には売春を生業とする「売比丘尼」へと変化していきました。
その出自ゆえか、当初は僧侶相手の遊興を目的とした、僧侶専門の売春宿に身を置いていたともいわれます。
「坊様の 買っていいのは 比丘尼なり」
こんな川柳が残されているように、僧侶たちの女遊びを皮肉る風潮がありました。どうやら江戸時代も下るにつれ、仏教は俗化が進み、享楽に耽る僧侶が少なくなかったようです。
やや余談ですが、僧侶の中には男娼を抱える陰間茶屋を利用する者も多かったと伝えられています。

画像:『盲文画話』(国立国会図書館蔵)public domain
さて、売比丘尼は湯屋や岡場所が幕府による度重なる取り締まりを受けたこともあり、かえって需要が高まっていきます。
というのも、売比丘尼は特定の場所に定住せず、遊行するかたちで寺院や武家屋敷を訪ね歩いたからです。
しかし、こうした流動的な形態も、やがて流行の広まりとともに組織化され、売比丘尼を専門に扱う「中宿(なかやど)」が登場しました。
これらの「中宿」は、江戸の繁華街である日本橋・京橋・赤坂などに設けられていたのです。
遊女とは一線を画した「売比丘尼」

画像:『盲文画話』(国立国会図書館蔵)public domain
売比丘尼は遊女の一種ではありましたが、一般の遊女とは決定的に異なる点がありました。
それは「前借制」に縛られていなかったということです。
そのため、売春行為はあくまで自由意志に基づくものであり、稼いだ収入の中から歩合を「中宿」に納めればよい、という仕組みでした。
こうした売比丘尼の最盛期は、元禄年間(1688年~1704年)の頃とされています。
ところが、江戸市中の私娼の中にも比丘尼に転じる者が現れ、やがて幕府の取り締まりは彼女たちにも及ぶようになります。
それでも需要の大きかった売比丘尼は、表立って活動することを避けながらも営業を続けました。
しかし、1741年(寛保元年)に「中宿」で武士と比丘尼の心中事件が起こり、これを契機に幕府による徹底的な弾圧を受け、次第に姿を消していきます。
もともと比丘尼は、飛鳥時代初期に倭国で初めて出家した女性に始まり、鎌倉・室町時代までは純粋に仏法を説く聖職者でした。
ところが江戸時代に入ると、その姿は大きく変わり、一般の遊女とは異なる独自の売春形態を持つ存在へと転じていったのです。
※参考文献
永井義夫著 『江戸の売春』河出書房新社刊 他
文 / 高野晃彰 校正 / 草の実堂編集部




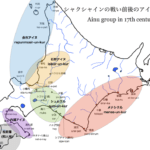















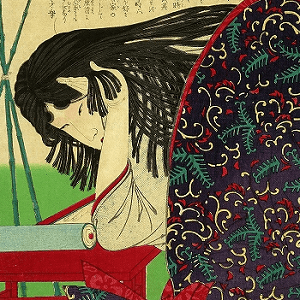
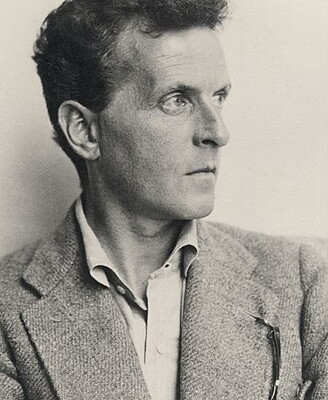


まあ、西洋化された現代人にはそう見えるわな。そういう話だけをまとめるわな。