
画像:第二次ポエニ戦争開戦時のローマとカルタゴの勢力図。赤がローマ、青がカルタゴ。緑はシラクサ(ローマの同盟国)。Grandiose CC BY-SA 4.0
北アフリカ、現在のチュニジアにかつて存在していた国、カルタゴ。
紀元前264年から紀元前146年にかけて、カルタゴとローマは三度にわたり、古代地中海世界、とくに西地中海の覇権をめぐる大規模な戦争を戦った。
この戦争は「ポエニ戦争」と呼ばれる。
最終的にカルタゴはローマに敗れ、滅亡した。
しかし、カルタゴ滅亡後も戦争の記憶はローマに残り続けた。
特に第二次ポエニ戦争(紀元前219年〜201年)の将軍、ハンニバルの脅威は、ローマ人の間で語り継がれたのである。
ハンニバルは、現在のスペインから進軍し、アルプス山脈を越えてイタリア半島に侵入した。
迎え撃ったローマ軍は、ハンニバルと対峙するたびに壊滅的な打撃を受けた。
それにもかかわらず、なぜローマは最終的に勝利できたのか。
歴史家ポリュビオスは、その理由の一つとして両軍の構造の違いに注目した。
すなわち「市民によるローマ軍」対「金で雇われた寄せ集めのカルタゴ軍」である。
陸上の軍事力に関しては、カルタゴよりもローマの方がはるかに強力な軍隊の養成に成功している。(中略)この違いの原因は、カルタゴでは外国人を傭兵として雇っているのに対して、ローマでは国内の市民で軍隊を編成していることにある。したがってこの点でも、カルタゴの国制と比べてローマの国制の優秀さが認められる。カルタゴの方は傭兵の士気に独立維持の希望を託するのが常であるが、ローマの方は同胞の勇気と同盟国の応援に支えられているからである。
ポリュビオス『歴史』第6巻52章より
一見するとポリュビオスの説明には説得力がある。しかし、近年の研究はこのイメージに疑問を投げかけている。
カルタゴ軍は本当に「寄せ集めの傭兵部隊」だったのだろうか。
実際にはその内側に、意外なほど強い結束が存在していたのである。
カルタゴ軍は本当に「寄せ集めの雑多な集団」だったのか?

画像 : ハンニバルのイタリア進軍を描いたフレスコ(カピトリーニ美術館) José Luiz Bernardes Ribeiro CC BY-SA 4.0
カルタゴ軍が多民族・多言語の集団であったことは事実である。
カルタゴ軍には、ヌミディア人(現在のアルジェリア)、ガリア人(ハンニバル軍の場合は北イタリア出身が多い)、イベリア人(スペイン)、他にもさまざまな出自の兵士が従軍していた。
しかし、兵士たちの間には戦友意識が十分に存在していた。
彼らの戦友意識は、兵士たちが共有する社会的な背景と、報酬を得るという目的、この二つの要素によって支えられていたのである。
同族単位で編成されたカルタゴ軍
「多民族」といっても、カルタゴ軍は、雑多に混ざり合った集団ではなかった。実際には、同族単位で部隊が編成されていた。
そのため、兵士たちは言語や戦闘方法、文化的な価値観を共有していた。すなわち、「仲間」としての強い絆が、最初から存在していたのである。
「同族単位の部隊」の代表として、現在のアルジェリア周辺を故郷とする、ヌミディア人によって構成された騎兵部隊が有名である。
ヌミディア人の装備は革の鎧、円形の盾、投槍といった簡素なものだった。
彼らが乗る馬も一本の縄を首にかけただけであり、裸馬同然だった。しかしそれでも、どの民族よりも巧みに馬を操ったと伝えられている。

画像:石碑に描かれたヌミディア騎兵(アルジェリア、国立考古学博物館・イスラム芸術館)
ファイル投稿者 Meriam Cherif CC BY-SA 4.0
ヌミディア騎兵の場合、「仲間」としての絆は、脱走を防ぐための枷として機能した。
彼らの社会は部族社会であった。そしてヌミディア人たちは自らが所属する部族の首長の元で、何十人かずつまとまって参戦していた。
「首長を中心とする数十人の集団」の集合体、それが「ヌミディア騎兵部隊」の正体である。
つまり、「傭兵」と言いつつも、実際には彼らの属する社会自体がカルタゴとの同盟を決めていたのだ。
ヌミディア人にとって軍からの脱走は、故郷の喪失をも意味したのである。
それ故に、ヌミディア騎兵部隊は騎乗技術だけではなく、「忠誠心」によっても、ハンニバルに最も信頼されていたのだ。
「金のため」だからこそ崩れなかった傭兵軍
傭兵は「金の切れ目が縁の切れ目」と言われることが多い。
しかし近年の研究では、報酬や略奪といった要素が、兵士の行動を強く支えていたと考えられている。
兵士たちは「報酬を得る」という、一つの強い目的を共有していた。その目的を失わない限り、彼らは直属の上官に逆らってでもカルタゴに忠誠を尽くしたのだ。
その劇的な例が、第一次ポエニ戦争中、シチリア島で行われたリリュバエウム包囲戦である。

画像 : シチリア島マルサーラの塩田。マルサーラは、かつてリリュバエウムと呼ばれていた。Fedina31 CC BY-SA 4.0
リリュバエウムは、シチリア島西部に位置しており、カルタゴの重要な拠点だった。
紀元前250年、ローマ軍は大軍を率いてこの都市を包囲した。カルタゴ軍は城内に籠もり、長期間の防衛戦を強いられた。
絶望的な状況の中で、一部の傭兵隊長たちはローマへの寝返りを画策した。 しかし、将軍ヒミルコはこれを察知し、兵士たちに直接「追加報酬」を約束したという。
その結果兵士たちは、自分たちの直属の隊長たちが戻ってきたとき、彼らに従うどころか、石や槍を投げて追い返したのである。
報酬や略奪は、適切に利用することで、多民族軍の結束を強めることができたのだ。
多民族軍を統率したカルタゴ軍の指揮システム

画像 : 紀元前3世紀、ポエニ戦争期イベリア兵士の再現写真 Dorieo CC BY-SA 4.0
多言語が飛び交う軍隊を、ひとりの将軍がどうやって指揮していたのだろうか?
そこには、将軍と兵士たちの間の結びつきを維持するための巧妙なシステムが存在した。
カルタゴ軍は多民族・多言語の混成軍で、単純に上からの命令を繰り返すだけでは、軍隊を動かすことができない。
これを解決するために、カルタゴ軍はやはり既存の社会を利用した。カルタゴでは特定の民族の部隊の指揮官として、その民族出身の指導者を登用していたのである。
そのような指揮官たちの中で、最も有名なのは、当初ヌミディア騎兵を率いたマシニッサだろう。
彼はヌミディアの王子であったが、カルタゴ軍においては精鋭騎兵部隊の指揮を任されていた。

画像 : マシニッサとカルタゴ出身の妻ソフォニスバを描いた16世紀のフレスコ。ソフォニスバはのちに毒杯をあおいで死ぬことになる。 public domain
指揮官たちは、将軍の命令や戦略目標を、現場の兵士たちが理解できるように「翻訳」して伝える役割を担った。
そして一方的に命令を下すだけでなく、部隊兵士の所属意識や士気に責任を持ち、部隊の状態を上層部に伝える役割も持っていた。
カルタゴ市民ではないにもかかわらず、彼らは将軍やその側近、有力な指揮官が集まる軍事会議の構成員でもあった。そして、ハンニバルのアルプス越えをはじめとした、重要な作戦の立案にも関わっていたとされる。
ただし、このシステムは諸刃の剣でもあった。
指揮官が離反した場合、その部隊が丸ごと離脱する危険があるのだ。
そのため将軍は、彼ら指揮官との結びつきを非常に重視した。
たとえば、ハンニバルの父親、ハミルカル・バルカは、ヌミディアの有力者であるナラウアスを取り込むために、自分の娘を彼に与えるという政略結婚を行っていた。
ハンニバルはなぜ兵士に信頼されたのか?

画像:カルタゴ軍兵士の胸当て(チュニジア、バルド国立博物館) public domain
カルタゴ軍の将軍たちは、単に戦術・戦略の専門家であるだけでは不十分だった。
兵士たちや、部隊指揮官に信頼される人物でなければならなかった。そのために、彼らは二つの側面からリーダーシップを発揮していた。
一つは、将軍としての実力である。
兵士たちは、「この将軍は有能であり、自分たちを勝利(と生存)に導いてくれる」と信じるからこそ命令に従う。
彼らは、将軍が適切な命令を出しているかを常に厳しく評価していた。
もう一つは、兵士への向き合い方である。
多民族・多言語の混成部隊であるカルタゴ軍では、一方的に厳格な規律を押し付けることは有効ではなかった。そうした手法はむしろ反発や誤解を招き、反乱や離反につながるリスクが高かった。
カルタゴの将軍は、このリスクを十分に承知していた。
そのため各民族の慣習を十分に尊重し、時には利用した。「この将軍は自分たちのことを気にかけてくれている」という、感情的な繋がりを構築することにより信頼を得ていたのだ。
リウィウスによるハンニバル描写は、この二つの側面をよく表している。
兵士たちはハンニバルが指揮を執るとこの上なく自信を持ち、大胆になった。彼は危険に臨んでは最高に勇ましく、危険のただ中にあっては抜群の判断力を示した。(中略) 起きている時間と寝ている時間を分けたのは、昼と夜ではなかった。仕事を終えて余った時間を彼は休息にあてた。睡眠を取るのに柔らかい寝床も静寂も不要だった。しばしば彼が番兵や歩哨のたむろする場所で外套にくるまり、地べたに横になっているのを、多くの兵士が目撃した。(中略) 騎兵としても歩兵としても、彼は圧倒的に図抜けていた。まず先陣を切って戦闘に赴き、そしてひとたび戦いが始まるや、退くのは最後だった。
リウィウス『ローマ建国以来の歴史5』21巻4より
戦場における有能さと、兵士と苦楽を共にする姿勢。
ハンニバルは、まさにこの二つを高いレベルで兼ね備えた人物だったのである。
ギリシア・ローマ的な偏見を越えて
このように、多様な出自の兵士たちがカルタゴ軍で戦い続けた背景には、既存の社会を活用する部隊編成、報酬の設定、指揮統制とリーダーシップなどの要素が存在した。
結局、ポリュビオスの見解は、ある種の自文化中心主義に基づいた偏見である。
カルタゴ軍は単なる寄せ集めではなく、れっきとした一つの軍隊だったのだ。
参考文献:
リウィウス、安井萠訳『ローマ建国以来の歴史5』京都大学学術出版会、2014年
ポリュビオス、城江良和訳『歴史2』京都大学学術出版会、2007年
栗田伸子『ヌミディア王国―ローマ帝国の生成と北アフリカ』京都大学学術出版会、2024年
Hall, Joshua R., and Louis Rawlings. “Unit Cohesion in the Multi-Ethnic Armies of Carthage.” In Unit Cohesion and Warfare in the Ancient World, edited by Lee L. Brice and John W. I. Lee, 78–105. London: Routledge, 2023.他
文 / 青汐茉莉 校正 / 草の実堂編集部




















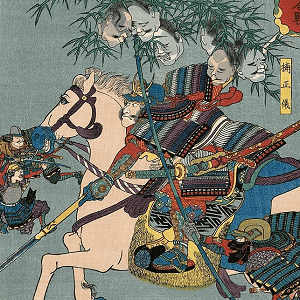
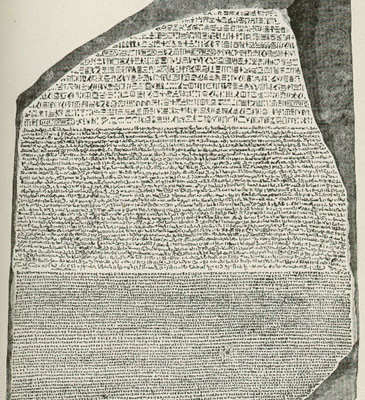

この記事へのコメントはありません。