
イメージ credit by Bing Image Creator
罪を犯していない人が冤罪となり、長い時を経た後に無罪となることがある。
自白は「証拠の王様」と言われ、それは有罪判決と同等であるとされている。
それにも関わらず、何もしていない無実の人々が、自分たちに不利な自白をしてしまうことがあるのはなぜだろうか?
そして、このような理不尽なことは世界各地で頻繁に起こっている。
本稿では、冤罪と虚偽自白について解説する。
自白は強力な証拠だが、虚偽自白も起こりうる
過去60年間に米国で犯罪を自白した300人を超える男女が、何ヶ月、何年、場合によっては数十年の歳月を経て、冤罪であったことが判明している。
この結果は、カリフォルニア大学アーバイン・ニューカーク科学社会センター、ミシガン大学法科大学院、ミシガン州立大学法学部のプロジェクトが運営するプログラム「全国免罪登録簿(以降NRE)」の記録に基づくものだ。
この虚偽自白は、1989年以降記録された2,551(現在は3,474)件の冤罪のうち、約10%を占めているという。
なぜ無実の人が罪を自白してしまうのだろうか?
虚偽自白の理由
ニューヨーク市立ジョン・ジェイ刑事司法大学院の心理学教授ソール・カシン氏は、
「法廷において自白が非常に重要な証拠になることは疑う余地がない。なぜ人が自白するのかを理解する手がかりは、尋問の方法に深く関わっている」
と述べている。
カシン氏によれば、
虚偽自白は多くの場合、「長時間にわたる執拗な尋問の後」に行われることが多いという。
執拗な尋問と虚偽自白 ~ボブ・アダムズ氏のケース

画像: 尋問中のイメージ credit by Bing Image Creator
ニューヨーク州シラキュースに住む男性、ボブ・アダムズ氏の例を見てみよう。
アダムズ氏は2022年5月、自宅近くの路上で男性が刺殺される事件が発生した直後に逮捕された。
警察は、アダムズ氏に強い疑いを持っていたものの、決定的な証拠はなかった。
シラキュース・ポスト・スタンダード紙によると、アダムズ氏が、泥酔状態で長時間にわたって同じ質問を繰り返し受け「虚偽の自白」をしたことが尋問の録音に残っていたという。
カシン氏は、警察は証拠がないにもかかわらず、アダムズ氏に「証拠があるかのように告げる」という、合法だが物議を醸す技法を用いたと指摘している。
疲労とアルコールの影響で判断力が低下していたアダムズ氏は、警察の誘導に答える形で虚偽の自白をしてしまったのだ。
その後、同氏は無実を主張したが、裁判で有罪判決を受け、8ヶ月の懲役刑を宣告された。
しかしその後、真犯人が逮捕され、アダムズ氏の無実が証明された。
カシン氏によると、アダムズ氏のような無実の人は、尋問を受ける際「何も問題ないはずだから弁護士も必要ない」と安易に考えてしまいがちなのだという。
しかし、警察は証拠がないにもかかわらず証拠があるかのように伝え、犯人であると断定して追い詰めるような尋問を行う。
疲弊し、心理的に追い込まれた容疑者は、出口のない状況に陥っていると感じ始めるという。
本来持っているはずの「沈黙する権利」さえ忘れてしまうことも少なくない。
中には、尋問過程で自分が罪を犯したと思い込む「共犯化」という現象が起こる場合もあるようだ。
ボブ・アダムズ氏のケースは、無実の人が虚偽の自白をしてしまう典型的な例である。
虚偽自白のもう一つの理由 ~尋問から逃れたい
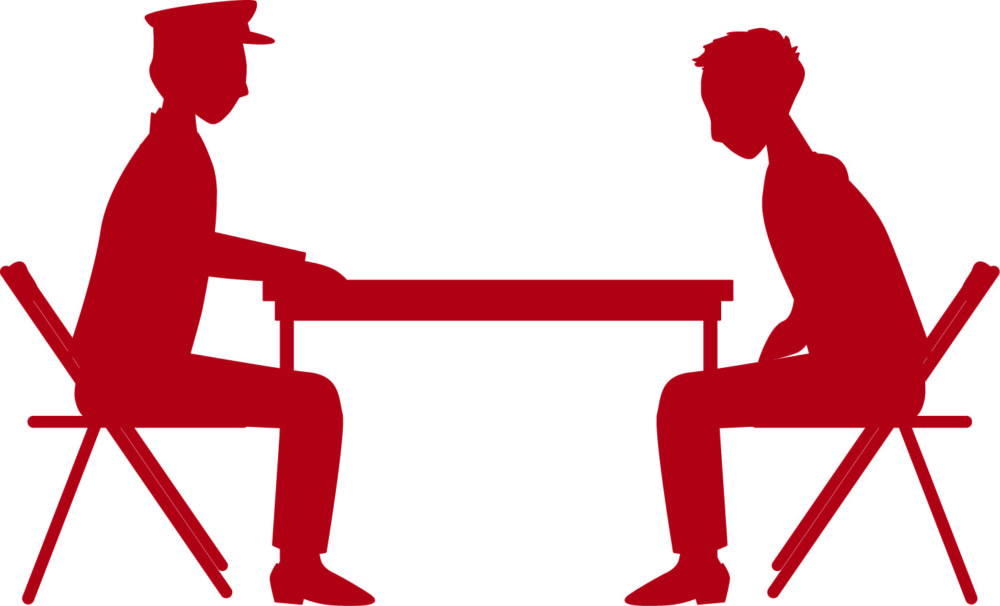
イメージ
別のケースでは、「早く尋問から逃れたい」という理由で、虚偽自白をする人もいるという。
長時間続く尋問は、精神的に大きな負担となる。
疲労やストレスによって判断力が鈍り、事実と異なることを自白してしまうのだ。
真犯人が逮捕されるなど、より多くの事実が明らかになれば潔白が証明され、すぐに釈放されるだろうという考えが、虚偽自白を誘発することもあるのだ。
いずれにしても虚偽自白は、冤罪事件の大きな原因となっているのが現状だ。
虚偽自白しやすい人
全米冤罪登録所によると、虚偽自白は誰にでも起こり得ることだが、若者や精神障害者は特に注意が必要だとされている。
また、イノセンス・プロジェクト(DNA鑑定によって冤罪を晴らす非営利団体)の調査によると、DNA鑑定によって無実が証明された虚偽自白のうち49%が21歳未満の人々だったのだ。
若者や障害のある方は、警察との会話中により強いストレスや疲労を感じやすい傾向があるということである。
なぜ無実の人が詳細な自白をできるのか?

画像: 法廷のイメージ credit by Bing Image Creator
カシン氏によると、通常、無実の人が詳細な虚偽自白を作り上げることは非常に難しいという。
自白というのは、「私がやりました」というような単純なものではなく、「いつ、どこで、どのように犯罪が行われたのか」などを詳細に説明しなければならないからだ。
もちろん無実の人は、そのような情報を持ってはいない。
2010年の研究で、デューク大学のブランドン・ギャレット氏がイノセンス・プロジェクトのデータベースを分析した結果、95%の虚偽自白には警察しか知らないはずの、犯罪に関する正確な事実が含まれていたことが判明している。
しかしカシン氏は、容疑者が犯行に関する詳細な情報を持っていても、驚くようなことではないという。
警察は誘導尋問し、写真提示、犯行現場への同行などを通して、容疑者が自白するために必要な情報を提供している。
そして、疲労やストレスによって判断力が低下している容疑者は、警察の提示する情報に基づいて「もしかすると自分が本当に犯人かもしれない」と思い込んでしまうこともあるというのだ。
容疑者の自白を鵜呑みにするのは危険
容疑者が犯行を詳細に自白すると、その内容を真実だと思ってしまうのは当然のことのように思えるかもしれない。
しかし、実はそこには「認知バイアス」という落とし穴が潜んでいる。
認知バイアスとは、「自分が信じたい情報ばかりを集めてしまう」心理的な傾向のことである。
自白という強力な情報が提示されると、捜査官でさえも、自白内容を裏付ける証拠ばかりを探してしまうようになるという。
その結果、矛盾する証拠を見逃したり、自白に都合の良い解釈をしたりして、誤った結論に至ってしまう可能性が高くなる。
つまり、「自白が真実であるという保証」はどこにもないのだ。
自白が真実とは限らない

イメージ
実は、自白だけでは有罪判決を下すことはできない。
必ず、別の証拠と一致している必要がある。
しかしカシン氏によると、ほとんどの虚偽自白は、誤った証拠によって裏付けられているという。
例えば、オクラホマ州で殺人、強盗、レイプの罪で起訴されたロバート・ミラー氏のケースだ。
ミラー氏が虚偽自白をした後、捜査官は同氏と一致する可能性のある血液と唾液サンプルのみを検証し、他のサンプルは無視したという。
これは、まさに「認知バイアス」による行動だ。
この証拠の誤解釈により、ミラー氏は誤って有罪となり、真犯人は野放しになってしまった。
この事例は、自白だけでなく、捜査官もバイアスの影響を受け得ることを示している。
科学捜査にもバイアスがかかる可能性
カシン氏はさらに警鐘を鳴らす。
自白内容を事前に知っていると、前述したように捜査官も無意識にバイアスがかかってしまう。
その影響はポリグラフ(別名:ウソ発見器)や、指紋などの分析結果にも現れてしまうことがあるのだ。
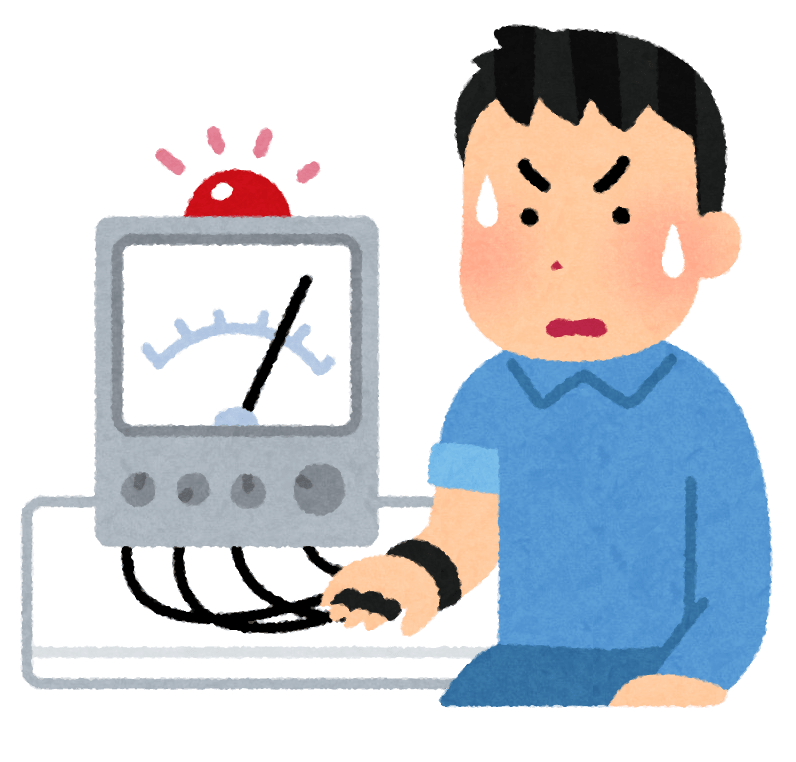
例えばポリグラフ検査では、被疑者を疑えば疑うほど、反応した数値を「嘘」と判断してしまいがちになるという。
同じように指紋の鑑定でも、知らず知らずのうちに自白と合致する方向で証拠を解釈してしまう可能性があるのだ。
虚偽自白を防ぐための対策と課題
近年、数多くの虚偽自白が発覚したことを受け、いくつかの対策が進められている。
アメリカの25の州で「取り調べの全程録画」が義務化され、監視によって取り調べの適正化が期待されている。
また、長時間拘束する取り調べは、陪審員の信用を失うことが示唆された。
カシン氏は、これらの対策で冤罪は減っていくかもしれないと展望しつつも、根本的な課題は残っていると指摘する。
これまでの司法制度では、自白が過度に重視されてきた。
しかし、虚偽自白の可能性もあることを踏まえ、自白の評価方法を見直す必要があると同氏は訴えている。
さいごに
本稿では主にアメリカにおける「冤罪」や「虚偽自白」に関して説明したが、日本においても「冤罪」は少なくない。
一般市民が冤罪を防ぐのは難しいかもしれないが、まずは、疑いをかけられにくくすることが大事だろう。
また、簡単な法律(刑法・民法)を理解しておくことも重要だと思われる。
万が一加害者扱いされた時のために、まずは無料の弁護士相談などで、実際に弁護士さんとの繋がりを作っておくのも良いかもしれない。
参考 :
Cases – Innocence Project
カリフォルニア大学アーバイン・ニューカーク科学・社会センターのプロジェクト、ミシガン大学法学部およびミシガン州立大学法学部
Browse the National Registry of Exonerations
















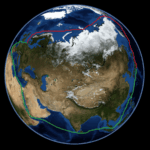



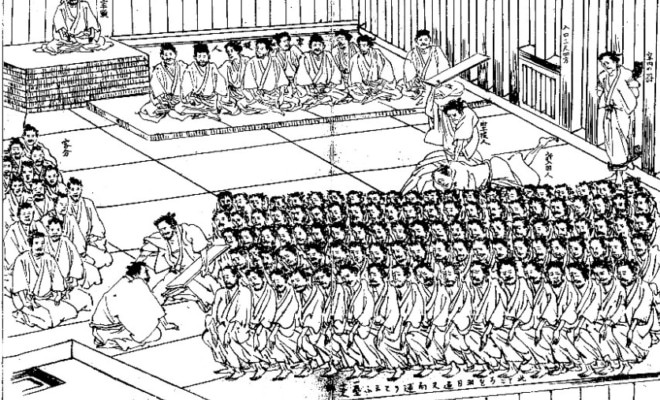



この記事へのコメントはありません。