2024年7月29日、パリ2024オリンピックに湧くフランスから、日本に吉報が入った。
馬術の日本代表チームが、総合馬術団体競技で銅メダルを獲得したのだ。日本が馬術でメダルを獲得するのは、実に92年ぶりの快挙である。
今から92年前、1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの馬術障害飛越競技で、金メダルを獲得した人物こそが西竹一(にし たけいち)だ。

画像:西竹一と愛馬ウラヌス public domain
当時の馬術競技は、オリンピックの花形競技だった。
西竹一は大観衆の前で、愛馬ウラヌス号と共に人馬一体の妙技を披露し、日本のみならずアジア諸国の選手として初めてオリンピック馬術競技で、金メダルを獲得したのである。
男爵の爵位を持っていたことから「バロン(男爵)西」の愛称で国内外で親しまれ、ロサンゼルス市の名誉市民にもなったが、第二次世界大戦時の硫黄島の戦いにおいて、アメリカ軍との激戦の末に戦死した。
今回は、西竹一の生涯や、愛馬ウラヌス号との友情関係に触れていきたい。
西竹一の生い立ち

画像:西竹一の父・西徳二郎(1912年) public domain
西竹一は、1902年7月12日、薩摩藩出身の男爵である西徳二郎の三男として、東京市麻布区麻布笄町(現在の港区西麻布)で生まれた。
生家である西家の広大な本邸は、現在のテレビ朝日本社ビル付近にあった。
竹一の実母は徳二郎の正妻ではなく、西家の女中だった女性で、竹一を出産した後に実家に戻されてしまった。
しかし、徳二郎は死別した前妻と後妻との間に生まれた男児2人を早くに亡くしており、年老いてから生まれた非嫡出子である竹一を、西家の跡取りとして育てることにした。
竹一という名は「西家の将来を担う男子として、竹のようにまっすぐ健やかに育ってほしい」という願いを込めて付けられた名前だった。
徳二郎は下級武士の出身だったが、明治維新後に外務大臣や枢密顧問官などを歴任した人物で、清公使時代には義和団の乱の処理に当たり、その際に清の西太后から信頼され、中国茶の専売権を与えられて巨万の富を手にした人物だ。
竹一は、徳二郎の後妻である義母には冷たく扱われたものの、裕福な男爵家の跡取り息子として経済的に不自由なく育てられ、学習院幼稚園を経て学習院初等科に進む。
実母の愛や家族の暖かさを知らない孤独さからか、少年時代の竹一は良家の子息でありながら、近隣の公立小学校の児童と喧嘩に明け暮れる暴れん坊だったという。
1912年3月13日、竹一が10歳になる年に父・徳二郎が64歳で死去し、竹一は動産、不動産を含む西家の莫大な財産と男爵の爵位を相続した。
1915年に学習院初等科を卒業した後、外交官だった父の遺志を継いで東京府立第一中学校(現・日比谷高校)に進学した。
その後、学習院院長であった乃木希典の言葉に感化され、在学中の9月に広島陸軍地方幼年学校に入校し、それ以降は軍人としての道を歩むことになる。
馬術に目覚め「愛馬ウラヌス」と出会う

画像:西竹一とウラヌスによる「車越え」 wiki c キノトール
少年時代に莫大な財産を手に入れた竹一は、天才肌で学業は優秀だったが、浮世離れした金銭感覚を持つ遊び好きの伊達男でもあった。
街中でアメリカ産の外車を乗り回し、新橋や銀座などの繁華街で大酒を飲み歩き、酔った勢いでチンピラと喧嘩するという荒れた生活を送っていたという。
そんな破天荒な竹一の心の穴を埋めたものが、馬術だった。
乗馬の面白さに目覚めた竹一は、幼年学校修了後に陸軍士官学校予科に進み、騎兵を志望して馬術を基礎から学ぶ。
陸士予科卒業後は士官候補生として世田谷騎兵第1連隊に配属され、隊附勤務を経て陸軍士官学校の本科に入校。
1924年に陸士本科を卒業してからは、見習士官を経て陸軍騎兵少尉に任官され、その年の12月には、かねてから思いを寄せていた川村武子との結婚を果たした。
1927年9月に陸軍騎兵学校を馬術学生として卒業し、翌月には陸軍騎兵中尉に進級する。
竹一が、1932年のロサンゼルスオリンピックで相棒となるウラヌス号と出会ったのは、1930年4月のことだ。
国内の馬術大会で優秀な成績を収め、ロサンゼルスオリンピックの代表選手候補に選ばれていた竹一は、乗馬の恩師である今村安から「大きすぎて誰も乗りこなすことができない暴れ馬を、売りたがっている人物がイタリアにいる」と連絡を受けた。
竹一は、今村の話を聞いてすぐにイタリアに向かった。
日本人離れした容姿を持ち、流暢な英語を話す爵位持ちの紳士であった竹一は、西洋人とも臆することなく交流したという。
この時の船旅の最中に、ハリウッドスターのダグラス・フェアバンクス・メアリー・ピックフォード夫妻と仲を深めている。

画像:フェアバンクスとメアリー・ピックフォード public domain
イタリアに到着した竹一は、件の馬を目の当たりにすると一目惚れし、「自分が乗りこなしてみせる」と決意し、大金を投じて購入する。
フランス生まれのアングロノルマン種のその馬は体高が181cmもあり、「ウラヌス(天王星)」という名の由来になった額の星模様が特徴的な、美しい栃栗毛色の気性の激しい馬だった。
ウラヌス号は元の持ち主は乗りこなせなかったが、竹一とは心を通じ合わせた。
柔道や剣道の有段者であり、身長175cmと当時の日本人としては長身かつ腰幅が広く足も長かった竹一は、大きく力強いウラヌス号を見事に乗りこなし、その後に出場したヨーロッパの馬術大会で次々と優秀な成績を収めた。
帰国した竹一は、ウラヌス号を千葉県習志野市にあった騎兵学校に預け、調教と練習のために麻布の自宅から毎日通うようになる。
竹一とウラヌス号の信頼関係は厚く、ウラヌス号は竹一以外の人間を大人しく背に乗せることはなかった。
竹一は後にウラヌスについて「自分を理解してくれる人は少なかったが、ウラヌスだけは自分を分かってくれた」と語っている。
ロサンゼルスオリンピックに出場し、金メダルを獲得

画像:障害飛越の西竹一とウラヌス public domain
1932年、ロサンゼルスオリンピックが開催され、当時陸軍騎兵中尉だった竹一は、馬術競技の日本代表選手としてウラヌス号と共に出場した。
対日感情が悪化しつつあった当時のアメリカにおいて、在米日本人や日系アメリカ人は人種差別と政治的圧力に苛まれながら肩身の狭い日々を過ごしており、多くの日系人が日本選手団の活躍に期待を寄せ、寄付金や声援を送っていた。
竹一とウラヌス号が出場した「大賞典障害飛越競技」は、ロサンゼルスオリンピックの最後を飾る花形競技で、閉会式が行われるメインスタジアムで行われた。
元々馬術競技は西洋の騎兵文化を競技としてオリンピックに取り入れたものであり、欧米各国の軍人が選手として出場していた。馬術日本選手団は日本陸軍の威信をかけて出場していたものの、活躍はそれほど期待されていなかった。
8月14日、オリンピック最終日の午後、既に9選手のうち6名が未完走という波乱模様の中、最後から2番目の出場者だった竹一とウラヌス号は走り出し、少々のミスはあったものの他の選手たちが失敗した障碍を次々と飛び越えていった。
難関の第10障碍を前にして、ウラヌス号の足が止まった。しかし竹一は諦めない。
会場からどよめきが起こる中、竹一は素早くウラヌス号を反転させて障碍に向かい、ウラヌス号も自ら後ろ足を右にひねって、難関を見事に飛び越えたのである。

画像:ロサンゼルスオリンピックにて 競技中の西竹一とウラヌス public domain
その後の障碍もすべて飛び越えて、竹一とウラヌス号はトップの点数でゴールした。
そして、最後の選手の点数も振るわず、竹一とウラヌス号は堂々たる成績で金メダルを獲得したのだ。
新聞記者からのインタビューに対して、英語が堪能な竹一はただ一言「We won.(我々は勝った)」と答えた。
この時のWeは、自分と愛馬ウラヌス号を示した言葉だった。竹一とウラヌス号はまさに人馬一体となって、輝かしい勝利を掴み取ったのだ。
「バロン・ニシ」の名声と評判は、瞬く間にアメリカをはじめとする世界中に知れ渡った。ロサンゼルス市長は竹一に名誉市民の称号を与え、竹一はロサンゼルス郊外に建設する競馬場の起工式にも、来賓として招待されて歓迎された。
現地で開催された金メダル受賞パーティーでは、ウラヌス号に会いに行くイタリアへの道中で懇意になったフェアバンクスと再会し、友情を深めたという。
ロサンゼルスオリンピックにおける竹一とウラヌス号の活躍は、日本人と日系人に大きな希望と感動を与えたのだ。
硫黄島の戦いで戦死

画像:ベルリンに赴く陸軍騎兵大尉時代の西竹一と見送りの妻子(1936年) public domain
西竹一とウラヌス号は、4年後に行われたベルリンオリンピックにも出場したが、ウラヌスが老いにより衰えていたことに加え、竹一自身も本番前に体調を崩しており、成績は前回の五輪ほど振るわなかった。
その後に日中戦争が開戦し、陸軍騎兵大尉となっていた竹一は陸軍騎兵少佐に昇進するも、軍馬補充部に配属されて北海道に飛ばされ、苦悩の日々を送ることになる。
そして各国の軍備拡大が進んでいく中で、世界的に陸軍の騎兵部隊が削減され、戦争には馬ではなく戦車を使う時代となっていった。
竹一もまた、戦車部隊である第26師団捜索隊長に任命された。
第二次世界大戦中の1943年8月、竹一は陸軍中佐に昇進し、戦車第26連隊の連隊長として満州国北部の防衛につき、その後はサイパンの戦いに参戦する予定となった。
しかし、現地守備隊の早々の玉砕を受けて、1944年6月20日に硫黄島に動員されることが決まる。
硫黄島に入った竹一は、栗林忠道中将率いる小笠原兵団直轄の戦車第26連隊の指揮官となった。
硫黄島においても竹一は自分のスタイルを貫き、愛用の乗馬鞭を持ちながらエルメスの乗馬ブーツを履いて、島内を闊歩していたという。

画像:地下に隠されていた戦車第26連隊の九五式軽戦車 public domain
1944年8月、竹一は戦車の補充のために一時東京に戻った際に、世田谷区上用賀の馬事公苑の厩舎で余生を過ごすウラヌス号に会いに行った。
その時、既に24歳になっていたウラヌス号は、竹一の足音を聞くと大喜びして、最大限の愛情表現で西を歓迎したという。
竹一はその際、ウラヌスを馬場に連れ出し、一周だけゆっくりと回った後に、ウラヌス号のたてがみを1房切り取って懐にしまい込んだ。
アメリカやヨーロッパの国力を自らの目で見て知っていた竹一には、太平洋戦争における日本の行く末や、自らが硫黄島で迎える結末があらかた予想できていたのだろう。
そして硫黄島に戻った竹一は、苦しい戦況の中で兵士たちを励ましながら、自身も戦いに身を投じていく。
翌年3月、激戦を極めた硫黄島の戦いで、竹一は42歳で戦死した。
命日は3月22日とされているが、3月17日以来後方部隊との連絡が途絶えていたため、実際の命日や詳しい死因は判明していない。
ウラヌス号もまた、竹一の死後まもない1945年3月28日に、竹一の後を追うようにこの世を去った。
竹一が最期まで身につけていたウラヌス号のたてがみは、後にアメリカで発見されている。
現在は、竹一と所縁のある北海道十勝本別町の歴史民俗資料館に収められている。
国境と人種の壁を越えて愛された「バロン西」

画像:金メダリストの西竹一は子供の着物の柄にもなった(1932年) wiki c Hiart
複雑な環境で育ち、気性の激しい所があったものの、天真爛漫でスマートな美男子だった竹一は、多くの人々に慕われ愛された。
西洋人とも交流を持ち、華やかな服装や生活を好んだため、軍の上層部からは反感を買うこともあったが、部下から慕われ信頼される人物だったという。
真偽は不明であるが、アメリカ軍が硫黄島に上陸した際に、アメリカでも有名人だった竹一に対して投降を呼びかけたという伝説も残っている。
竹一の墓所は東京の青山霊園にあるが遺骨は見つかっておらず、硫黄島の東海岸には竹一の戦死を悼む石碑が建立された。後に発見された竹一愛用の乗馬鞭などの遺品は、数十年の歳月を経て家族のもとに返された。
欧米列強が集う国際社会へ踏み込もうとする日本にとって、西竹一とウラヌス号は金色に輝く希望の光だった。
1人と1頭が人馬一体となって成した偉業は、92年の時を越えて今も人々に感動と勇気を与え続けている。
参考文献
大野 芳 (著)『オリンポスの使徒―「バロン西」伝説はなぜ生れたか』
文 / 北森詩乃




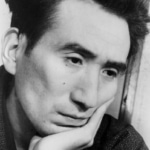



















この記事へのコメントはありません。