明の建国と、朱元璋

画像 : 洪武帝(朱元璋)の肖像画(国立故宮博物院蔵)public domain
明の初代皇帝・洪武帝(朱元璋 しゅげんしょう)が即位した14世紀後半の中国は、長い戦乱をようやく終えた直後の社会であった。
元末の動乱は各地を荒廃させ、農村は疲弊し、治安も制度も崩れきっていた。
明は新王朝とはいえ、実態はまだ不安定で、皇帝の権威が自然に尊重される状況ではなかった。
この不安定さの中で即位した朱元璋は、歴代皇帝の中でも特異な経歴を持つ人物であった。
彼は名門の出ではなく、正真正銘の貧農の子として生まれ、飢饉で家族を失い、托鉢僧や乞食同然の生活を経験し、科挙や貴族的教養とは無縁のまま、頂点に立った皇帝であった。
その出自は、彼に「民を思う皇帝」という一面を与えた一方で、強烈な不信感と猜疑心も植え付けた。
朱元璋が生きた時代、「殉葬」はすでに過去の慣行であった。
殉葬とは、君主が亡くなると、その配偶者や側近の命を奪い、墓に共に収める制度である。

画像 : 邯鄲における春秋戦国時代の殉葬 我乃野云鹤 CC BY-SA 4.0
漢代以降、皇帝の殉葬は急速に廃れ、宋・元を通じて、少なくとも国家制度としては否定されていた。
後宮の女性たちが、皇帝の死とともに命を奪われることは、原則として想定されていなかったのである。
それにもかかわらず、朱元璋の死後、その意向を受けて殉葬が実施され、数十名の側室たちが命を落とすことになった。
後宮に広がった噂と46人の選別

画像 : 明故宮(永楽帝時代に北京へ遷都されるまで皇宮として使用された) Judoschlv CC BY-SA 4.0
洪武31年、朱元璋の病状が重いことは、すでに後宮でも隠しきれなくなっていた。
やがて後宮に、ひとつの噂が広がる。
それは「皇帝が崩御した場合、妃嬪の一部が殉葬される」というものであった。
この噂は根拠のない流言ではなかった。
朱元璋はすでに遺詔の草案を用意させており、その中には明確な条件が記されていたとされる。
それは「皇帝の子を産んでいない側室は、死後に皇帝に従わせる」という規定であった。
この条件は一見すると合理的に見える。
皇子の母となった妃嬪は、将来の皇族と直結する存在であり、政治的にも完全に排除することができない。
一方、子を持たない側室は、皇帝の死とともに後宮に存在し続ける理由を失う。
朱元璋は、そこに一切の情を挟まなかった。
彼女たちに逃げ場はなかった。後宮は高い塀に囲まれた閉鎖空間であり、外に助けを求める術もない。
恐怖は個々の妃嬪の胸に沈殿し、やがて集団的な絶望へと変わっていった。
では、実際にどれほどの人数が犠牲になったのか。
『明史』は太祖の崩御に際して「宮人多從死者」と記すのみで、具体的な数は示していない。
ただし後世の記録や注記を含めると、孝陵に葬られた后妃は46人に及んだとされる。
この中には、朱元璋の死に伴って命を落とした側室たちに加え、生前に亡くなり、のちに合葬された后妃も含まれていたと考えられる。
「殉葬」はどのように実行されたのか
殉葬は、公開の場で行われた処刑ではない。
儀礼の名の下、静かに、そして迅速に進められた。実務を担ったのは太監(宦官)である。
名簿は太監によって管理され、本人たちに事前に告げられることはなかったとされる。
それがかえって恐怖を増幅させた。

画像 : 朱元璋の妃嬪たち イメージ 草の実堂作成(AI)
太監たちは遺詔に基づき、事前に作成された名簿を管理し、対象者を一人ずつ呼び出していった。
側室の妃嬪たちは「皇帝に従う」という名目で後宮を出され、そのまま孝陵へ向かわされた。
そこに待っていたのは「葬られる者」のために用意された空間であった。
殉葬の具体的な方法については、同時代から後世にかけての記録や慣行を踏まえると、多くは絞殺、あるいは密閉空間に閉じ込める形で命を奪われたと考えられている。
いずれにせよ、自ら死を選ぶ余地はなく、国家の意思として命が処理された。
一方、殉葬された者たちの家族は、国家によって一定の処遇を受けた。
『明史』には、殉死者の遺族が「太祖朝天女戶」と呼ばれ、官職や俸給を与えられた例が記されている。
これは悲劇に対する補償というより、殉葬を制度として正当化し、社会に組み込むための措置だった。
こうして数多くの妃嬪たちが、朱元璋の死とともに歴史の表舞台から消えた。彼女たちの名の多くは残されていない。
声を持たず、選択肢も与えられず、ただ制度として消費された存在だったのである。
なぜ朱元璋は殉葬を復活させたのか

画像 : 人々の間で広まった面長の朱元璋の肖像画 public domain
朱元璋の殉葬は、彼が築いた国家観と人間観が、死後にまで及んだ結果である。
彼は生前から「秩序」を何よりも重んじた。
法は絶対であり、情は排されるべきものだった。功臣であろうと容赦なく粛清し、家族であっても法の外に置かなかった。その姿勢は、死後の世界に対しても変わらなかったのだ。
また朱元璋は、生涯を通じて人を信用しきれなかった皇帝である。
極貧の出自、裏切りと猜疑の連続、権力を得てからの粛清。その人生は、他者への不信によって形作られていた。
後宮の側室たちも、彼にとっては例外ではなかった。
殉葬は、朱元璋の死後も惰性のように続き、約60年後、第6代正統帝/第8代天順帝として重祚した英宗の遺詔によって禁止され、ようやく制度として否定されることになる。
つまり殉葬の復活は、明という王朝が完全に成熟する前段階で生じた、歪みの象徴だったとも言えるだろう。
秩序と恐怖によって国家を築いた男が、最後に行き着いた当然の帰結だったのかもしれない。
参考 : 『明史』「列傳第一后妃一」「列傳第二后妃二」『史記』他
文 / 草の実堂編集部








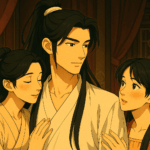
















この記事へのコメントはありません。