戦国武将において石田三成ほど評価が二分する人物も珍しい。
「実直」「傲慢」「天才」「凡人」というように、良いも悪いもかなり幅がある。概ね「生真面目だが融通がきかず、天才だがそれを鼻にかける癖がある」というのが一般的な三成像のようだ。
どのような名将であろうとも、肯定派だけの人物などいない。必ず、否定的な要素も含むものだが、三成はなぜここまでキッパリと評価が分かれるのだろう。
しかし、ここで私はある理由に思い当たった。そこで今回は、ある観点から三成を分析してみようと思う。
スポンサーリンク
石田三成が中間管理職だったら?

※石田三成
「中間管理職」と聞くと、「上からは押さえつけられ、下からは突き上げられる」といったイメージで、ストレスの塊のように思える。さらに、上司には胡麻をすり、部下には厳しい。ブラック企業を体現したような役職に思われてしまう。
しかし、どのような企業においても中間管理職というのは無くてはならない存在であり、その人物の能力によって企業の業績が決まるといっても過言ではない。
もう私の言いたいことは分かるだろう。
石田三成を現代の中間管理職と置き換えて考えてみれば、現代の我々にも彼の評価が出来るのではないか、というわけだ。関ヶ原の戦いでは、毛利輝元を西軍の総大将に据えているが、それも彼が中間管理職のポストであり、社長が豊臣秀頼だったと考えれば「現場を知る人間なりの人事だった」といえる。自分はあくまで裏方に徹しながらも、主君・秀頼の意に添えるよう動いたのである。
ヘッドハンティング

※島左近
豊臣秀吉に小姓として仕え、側近中の側近としてその頭角を現した三成。
秀吉が関白に就任すると、自身も従五位下治部少輔に任ぜられる。三成のことを指す官位である「治部少(じぶしょう)とはこのことだ。
まあ、主君である秀吉もなかば強引に関白の位を手に入れたことから、三成の官位も朝廷より下賜されたものというよりは、天下人の側近として必要な肩書きだったと思えばいい。肩書きが大きくて困ったという話は聞かないのだから。
話を戻すが、その後に三成は名将・島左近を三顧の礼をもって迎え入れたという逸話は有名である。これも、やれ「時期が違う」「知行の割合が違う」「この逸話そのものが創作である」などと話が食い違っている。ここでどれが正しい話だったのかを検証する術はないが、事実だったと考えれば、決して大げさな話ではないと分かる。
通説どおり、三成の当時の禄高4万石のうち、半分の2万石を与えて召抱えたとしよう。しかし、それで少なくとも「島左近」という戦力と名声は敵の手には渡らなくなる。三成はヘッドハンティングも上手かったわけだ。
嫌われ役

※蔚山籠城図屏風
優秀な中間管理職の条件に「経営理念の翻訳ができること」というものがある。
「株式会社豊臣」であれば、社長である秀吉の目的、その手段をよりわかりやすく部下に伝えてゆく役目のことだ。しかし、これがなかなか難しい。社長は叩き上げとはいえ、かなりの気分屋である。機嫌を損ねないように考えを聞きだし、実行可能な形に練り直して部下に伝えなければならない。部下も気の荒い者ばかりならなおさら厄介だ。
文禄の役、すなわち最初の朝鮮出兵では、総奉行を務めて戦いにも参加するが、明との和平交渉の連絡役もこなしており、それが原因で福島正則、黒田長政といった武断派の恨みを買ったとされる。さらに第二次朝鮮出兵である慶長の役でも、兵站などの後方支援を行うなど裏方として豊臣軍を支えた。しかし、蔚山城の戦い(うるさんじょうのたたかい)の後に戦線縮小案を上申した諸大名に対し秀吉が激怒、処分を受けることとなったが、その恨みは三成に向けられている。
これだけでは、単に三成が「経営理念の翻訳ができていない」と思われてしまうが、どちらも三成としては豊臣社長の意向通りに行動しただけであり、諸大名の恨みは「経営理念とは関係のない私情」からきている。事実、文禄の役では兵站を軽視して戦線を広げる諸将を説得しているのだ。それが慶長の役では「戦線を縮小したい」といわれた上、逆恨みされるとはいささか不憫である。いつの時代も中間管理職とは「嫌われ役」ということなのだろう。
チーム作りに頭を悩ませる

※石田三成出生地碑と三成像(滋賀県長浜市石田町)
中間管理職とは「自分が一番優秀でなくてよい」ことを理解しなくてはならない。
人材を適材適所に配し、チームで最高の結果を出すことが求められる。朝鮮出兵後は、秀吉により小早川秀秋の領地であった筑後国、筑前国を与えられることとなったが「大坂での行政が出来なくなるため」といってこれを辞退している。この時点での三成の所領は、近江佐和山の19万4,000石であり、転封に従えば33万石の大大名となるはずであった。
有名な「三成(治部少)に過ぎたるものが二つあり。島の左近と佐和山の城」と揶揄された頃の話である。
当然、石高が上がれば自身の評価も上がり、周囲の態度も変わるのだろうが、三成は自分の「やるべきこと」を選んだというわけである。
とはいえ、チーム作りにおいては秀でていたとはいえない。会社が大きすぎれば末端はおろか、自分の同僚との意思疎通すら難しくなるものである。そうしたことを理解した上で、三成は周囲に対しては対話よりも威圧的な態度で接するように割り切ったのだろう。
裏方に徹した生き方

※大谷吉継
三成の人物像を否定的に捉える要素として、彼が絶大な権限を有したことで傲慢になったというものがある。
関ヶ原の戦いで西軍総大将となった毛利輝元も「大変に気を遣う」と書き残しており、徳川家康に対しても横柄な態度をとったとされている。が、もともと家康は秀吉の没後すぐに、三成と対立関係にあった加藤清正、福島正則、黒田長政といった有力武将と縁戚関係を結んでおり、「反石田派閥」を作ろうとしていた。
朝鮮出兵において、諸将との間に溝ができた結果がこのときになって影響してきたわけだ。
しかし、一方で三成はこれを「やむなし」と考えていた節もある。
関ヶ原の戦いを前にしてのこと。大谷吉継が、病に冒されほとんど目が見えない状態でありながら、親友である三成のため西軍に与すると決めたとき「失礼だがおぬしには人望がない。普段の横柄な態度から、皆が家康に付くであろう。総大将は毛利輝元にせよ」と忠告している。いくら親友の言葉とはいえ、天下分け目の合戦に大将として立てないというのは、豊臣の重臣としては耐え難いことだろう。もし、本当に傲慢であればこれを聞き流すこともできたはずだ。
それを敢えて受け入れ、最後まで裏方に徹したのは、中間管理職こそ自分のポジションであるということを理解していたに違いない。
最後に
三成については、たびたび人望のなさや決断の遅さを指摘されるが、それは上に立つ人間にとって致命的なものだろう。勿論、中間管理職にも必要な能力ではあるが、彼を個ではなく組織の一員として見れば「中間管理職というポジションだからこそ実力を発揮できた」というのが分かった。また、三成自身もそのことを分かっており、不器用ながらも己の信念のままに生きたのである。
関連記事:石田三成
「石田三成は優秀な家臣だったのか調べてみた」
「【戦国の聖女・明智光秀の娘】細川ガラシャについて調べてみた」
関連記事:豊臣秀吉
「天下統一後の豊臣秀吉の政策」










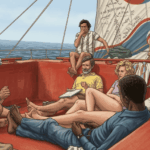





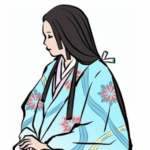





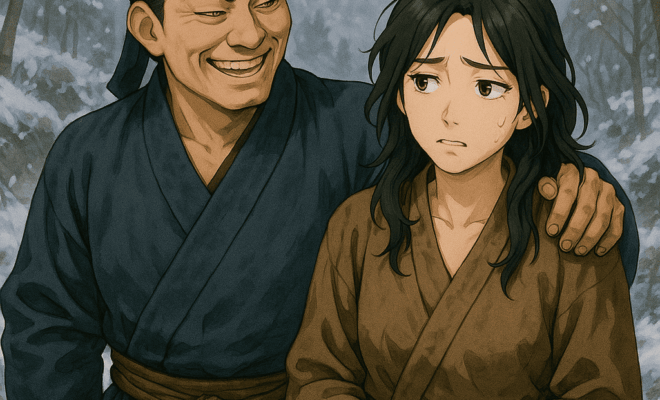

この記事へのコメントはありません。