2度の内閣総理大臣、陸軍大臣、内務大臣、司法大臣など、明治~大正の政府要職を歴任した山縣有朋(やまがた ありとも)。
日本陸軍を創設し「国軍の父」とも称されたにも関わらず、常にダーティなイメージがつきまといます。
存命中でさえ、その人間的な評価がすこぶる悪かった山縣有朋は、特に終戦後は「軍国主義者」と決め付けれ「悪」の象徴のような存在になりました。
しかし、山縣は、近代国家設立のために、愚直なまでに現実主義を貫く政治家でした。
そんな、山縣有朋の真の人物像に迫ってみましょう。

画像:山縣有朋 肖像 publicdomain
明治・大正を代表する政治家

画像:松下村塾 wiki c
第3代、第9代と2度にわたって首相に就任し、内閣を組閣した山縣有朋は、明治・大正を代表する政治家であり軍人でした。先ずは、簡単に山縣の経歴を追ってみましょう。
山縣は、幕末の1838(天保9)年、長州藩に武士と庶民の中間層として生まれました。長じてから吉田松陰の松下村塾に学び、さらに高杉晋作が創設した奇兵隊に入隊します。
周知の通り、奇兵隊は長州藩の正規軍ではありません。その構成は下級武士と庶民がほぼ半分の割合でした。
同隊は、外国船防御のために高杉が創設した混成部隊で、山縣は軍人としての第一歩をこの奇兵隊で踏み出します。

画像:高杉晋作 wiki c
山縣はここで徐々に頭角を現し、軍監に就任。その後、四国連合艦隊との戦い(下関戦争)で、欧米の近代兵器による実戦を経験。
第一次・二次長州征伐を経て、戊辰戦争では新政府軍の北陸道鎮撫総督・会津征討総督の参謀として活躍します。
そして、明治維新を迎えると軍政家として活躍。2度の内閣総理大臣(第3・9代)、陸軍大臣・内務大臣・司法大臣などを歴任します。
中でも、その功績として知られるのは、国軍としての日本陸軍の創設です。さらに、参謀本部と統帥権の独立を行い、後には「国軍の父」とも称されました。

画像:奇兵隊時代の山縣有朋 wiki c
こうした山縣のもつ影響力は軍部だけにとどまらず、政官界にもおよび、その幅広い人脈は「山縣系」「山縣閥」と呼ばれました。
そして、晩年に至っても「元老中の元老」として君臨し、国政に隠然たる勢力を持ち続けたのです。
固定化された「悪」の評価

画像:内務大臣時代の山縣有朋 wiki c
山縣有朋は、とてつもない経歴を持った人物です。しかし、存命中でさえその人間的な評価はすこぶる悪いものでした。その理由は、薩長に権力が集中する藩閥政治を推進させ、超然主義を貫き、独裁者として権力を行使したことによります。
例をあげると、近代初の大掛かりな汚職疑惑である「山城屋事件」にからみ、「陸軍二個師団増設問題」においては第2次西園寺内閣に干渉します。さらに、藩閥以外の政治参加を可能にした政党政治を敵対し、社会主義や労働運動などの民主主義的な社会運動を弾圧しました。

画像:原敬 wiki c
そして、「宮中某重大事件」においては、後の昭和天皇である皇太子・裕仁親王の婚約問題にまで干渉、その取り消しを画策したのです。この山縣の宮中干渉に関しては、伊藤博文とともに山縣のライバルでもあり盟友でもあった原敬も「要するに山県久しく権勢を専らにせ為め」と冷ややかな目線で述べています。
こうした山縣に対して、民衆の評価はとても辛辣でした。山縣の死後、その葬儀が1万人ほどの参列が可能な規模の国葬であったにも関わらず、参列した民衆は僅かに700人程度だったのです。
この状況は、当時の新聞に「ガランドウの寂しさ」と記されています。
約1ヶ月前に亡くなった大隈重信の国葬に、その死を惜しむ多くの民衆が参列したのとは余りにも対照的でした。

画像:護国寺内の有朋の墓 wiki c
しかし、山縣の「悪」としてイメージが定着したのは、終戦後といっても差し支えないでしょう。山縣は、近代日本の軍国主義を体現した「軍国主義者」と決め付けられたのです。
近代日本の破局をもたらしたのは、アジア太平洋戦争の無謀な拡大であったのは歴史的事実ですが、その元凶は、暴走を繰り返した陸軍とされました。その陸軍を創設したのが、他ならぬ山縣有朋だったのです。
こうして、絶大な権力を振りかざし、日本を敗戦国に追い込んだ「悪人・山縣有朋」のイメージが決定付けられました。
山縣有朋の真の人物像とは

画像:晩年の山縣有朋 wiki c
人間には生まれ持った性格があります。しかし、人という生き物はその人生において様々な経験を重ね、その過程で人となりが変化していくものです。では、山縣の生来の人となりはどのようなものだったのでしょうか。
その一端がうかがい知れる話として、征韓論政変で西郷隆盛に対して山縣が中立を守ったことがあげられます。
これは制定までに困難を極めた徴兵令で西郷の協力を得られたこと。さらに「山城屋事件」で失脚という最大のピンチに見舞われた時、西郷に救われたことに対する恩義があったからとされています。
また、自分が一度でも見込んだ人間は、たとえ何があろうと決して見放すことはありませんでした。これらは山縣の生まれついて持っていた人情味あふれる性格を端的に表しています。
こうしたある意味愚直で、優しい性格が、吉田松陰・高杉・西郷らに愛された理由でもあったのです。

画像:西郷隆盛 wiki c
しかし、山縣は権力をほしいままにし、多くの人から蛇蝎の如く嫌われました。それはなぜかと考えれば、山縣が幕末から維新への過程で経験した様々なできごと、そして2度にわたる欧米歴訪の経験により、実地体験をもとにした現実主義者として、そのスタンスを確立していったことに関係があるのではないでしょうか。
明治時代は、基本的には極東の小国日本が近代国家への脱皮のために、官民を問わず必死で苦闘していた時代でした。そうしなければ欧米の列強を向こうに回して、独立国家として自立していくことは不可能だったのです。
こうした時代の中で山縣は政治指導者として国軍を作り、「強兵」を優先させ明治国家の運営に携わります。この「強兵」を優先した国づくりにより、日清・日露戦という難しい対外戦で、日本は生き残りを果たせたのです。
また、山縣が欧米来訪で実地体験した大衆勢力の拡大による社会変動は、発展途上の明治国家に起きてはならないことでした。
現実主義者の山縣にとって、必要なものは日本が存続できるための確固たるものでしかありませんでした。これが、政党政治への敵視や、社会運動の弾圧となって表れたのではないでしょうか。
山縣は、そうした現実主義者的な観点から外交にも慎重姿勢を貫いていました。山縣といえば、軍国主義の権化のようにみられますが、対外戦争には常に慎重な立場をとっています。

画像:京都 無鄰菴の庭園 wiki c
ロシアの朝鮮半島への進出が危惧される状況になると、1902(明治35)年に山縣の京都の別荘・無鄰菴で、山縣・伊藤・桂太郎首相・小村寿太郎外相による無鄰菴会議が開かれます。山縣は開戦に慎重な立場をとり、その後、政府内・世論で日露開戦を唱える動きが強くなっても、日露開戦慎重派を貫きました。
昭和天皇が終戦の後、皇太子へ宛てた手紙には
「明治天皇の時には、山県、大山、山本等の如き陸海軍の名将があったが、今度の時には、あたかも第一次世界大戦の独国の如く、軍人が跋扈して大局を考えず、進むを知って、退くことを知らなかったからだ」
と敗戦の理由とともに、山縣への評価が記されています。
原も生前に「山縣が生きている限り、日米戦争は起こらないと」と発言していました。
大正デモクラシーを推進し、山縣と全く異なった立場にあった尾崎行雄も「三人(伊藤博文・大隈重信・山縣)を評して、その人物を素裸にした値打ちから云ったならば、山縣公が一番優れてゐたと私には感じられた」と述べています。
このように考えると、近代日本を確立・存続するための「必要悪」として、その役目を担ったという、新たな山縣有朋像が見えてくるのではないでしょうか。
※参考文献
藤村道生著 『人物叢書 山県有朋』吉川弘文館 1986年1月
伊藤隆著『山県有朋と近代日本』吉川弘文館 2008年3月










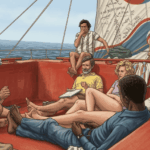






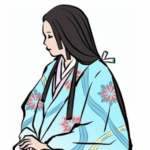







この記事へのコメントはありません。