歴史の文脈においては、「日本は広島県・長崎県に原子爆弾を投下され、さらにソビエトの参戦もあり、ポツダム宣言を受諾し無条件降伏を受け入れた」と、太平洋戦争の締めくくりを紹介するのが一般的であろう。
しかし、ポツダム宣言の受諾をめぐって起こった、日本国内での内乱一歩手前とも言える騒動である「宮城事件(きゅうじょうじけん)」については、あまり語られる機会がない。
宮城事件とはどのような事件だったのか、なぜ宮城事件が起こったのかについて、この記事で解説しよう。
宮城事件とはなにか?事件の背景

太平洋戦争において、1945年8月には広島への原爆投下、9日のソビエト参戦と長崎への原爆投下によって、事実上日本は戦争遂行能力を失っていた。
それでも軍内部には、特に陸軍を中心として、「本土決戦」を主張する参謀・司令官が多く、ポツダム宣言を受諾するという合意は形成されていなかった。
当初、陸軍大臣である阿南惟幾(あなみ これちか)は、ポツダム宣言の要求する「無条件降伏」ではなく、天皇の地位保証を意味する「国体護持」を盛り込み、「有条件降伏」とするべく議論を行っていたが、昭和天皇の「聖断」を受け、無条件降伏を受け入れることを決断した。
しかし、これを良しとしない陸軍省参謀の一部と近衛師団参謀の一部が結託し、ポツダム宣言受託阻止・連合国との交渉継続、徹底抗戦を唱えてクーデターを起こそうとしたのである。
ポツダム宣言への対応:外務省の意向
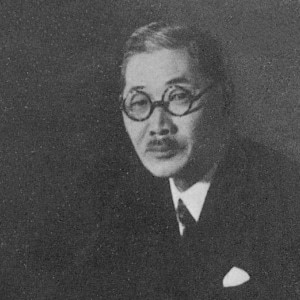
東郷茂徳, 1882 – 1950
外務省では、東郷茂徳外相を中心として、日ソ中立条約にもとづき、ソビエトを仲介役として連合国側との和平交渉を模索していた。
しかしながら、ソ連が日ソ中立条約を破棄し、満州国へ侵攻したことにより、日本にはポツダム宣言受諾しか選択肢が残されなかった。
連合国側が提示している無条件降伏を受け入れるというのが外務省の立場であり、そこに条件を付して「有条件降伏」とすることは、外務省側では困難という見方であった。
ポツダム宣言への対応:鈴木貫太郎の意向

鈴木貫太郎 内閣総理大臣在任時
1945年4月から首相へ就任した鈴木貫太郎は、元海軍大将であり、また予備役編入後には侍従長(天皇に付き従う身分)も務めた経験があった。
鈴木貫太郎が首相へ就任したのは77歳であり、日本の内閣総理大臣の就任年齢としては例をみない、高齢での就任であった。
この内閣は、同盟国であるドイツからも「降伏のための内閣」と評されている(ヨーゼフ・ゲッベルスの日記)ように、当初から終戦のための工作を行っていたとされる。
鈴木貫太郎自身は本土決戦という選択をどのように見ていたかは想像するしかないが、元海軍大将であったことから、海軍最後の希望とも言えた戦艦大和の沈没や、呉軍港空襲により歴戦の艦が沈められていく中での終戦工作には、複雑な思いがあっただろう。
ポツダム宣言への対応:参謀本部・陸軍と阿南惟幾の意向

阿南惟幾(写真は少将時代)
陸軍ではほぼ「本土決戦」の論調で統一されていたといってよい。
また、これまで度々対立してきた海軍との間に、陸海軍の指揮系統を一体化して本土決戦に利用しようとするなどの論もあった。
しかし陸軍も敗色濃厚であり、本土決戦を戦うための装備や弾薬、燃料などが充分にあるとは言い難い状況だった。
本土決戦といえば「竹槍訓練」が有名であるが、陸軍側が国民義勇隊用に用意した武器を鈴木首相とともに閲覧した迫水常久内閣書記官長をして、「狂気の沙汰」と呼ばれるもので、日本刀や火縄銃をはじめとした江戸時代に使われていたような武器や、鍬、鋤、刺叉など、到底近代的戦闘を戦えるものではなかった。
陸軍大臣であった阿南惟幾(あなみ これちか)は、海軍大臣米内光政らとの6相懇談会の場で、「本土決戦にて一撃をくわえ、有利な条件での講和に持ち込む」という、いわゆる「一撃講和論」を主張していた。
しかしながらその後、木戸幸一内大臣の提唱する和平・終戦試案にあっさり賛同した。その内心を秘匿していたとも言われる。
これについては様々な見方があるが、先に日本を震撼させた「二・二六事件」のように、若い者たちが暴走して首脳部が暗殺されるというようなクーデターを防ごうとしたとも考えられる。
昭和天皇の位置づけと「聖断」の意味

昭和天皇
戦時中の日本では、「大日本帝国憲法」に基づき国権が作動していた。
この憲法には「統帥権」があり、統帥権は天皇が有する権限であった。
しかしながらこれを持って、「天皇自身が直接軍に指揮命令できる」と考えるのは早計である。
大日本帝国憲法は「君主」である天皇について、「立憲君主制」を採用しており、各首脳は天皇の意思を「尊重」はするが、天皇が各首脳に「命令」を下すことはありえない。
天皇の実質的な権能とは、各部局の奏上や起案について、それを「勅許」する、つまり許可するというもので、勅許を「しない」という選択は基本的にありえないことだった。
そのような中で、終戦を望むという「聖断(天皇の決断)」という言葉が用いられることがある。
これは、あくまで天皇が「自分はこう考えている」という「お気持ち」を表明したものであり、各部局や首脳陣にはそれに従う義務はなかった。
しかしながら、当時特に外交や国家の最高指導層に近い地位の人間においては、軍関係の部局であっても、戦争遂行能力がすでにないことを悟っていながら、「終戦」を自ら言い出すことができなかったであろうことは想像できる。
それを踏まえたうえで、戦争の終結を模索するべきだ、ということを国家元首たる天皇自身が発言することは、異例ではあるが「お墨付き」として効果的であっただろう。
食い違った翻訳「subject to」

ポツダム宣言の文言を巡っては、非常に不幸な解釈の違いが生じた。
それは、「subject to」という言葉を巡ってのものである。
この「subject to」という言葉は、「管理下に置かれる・制限の元に置かれる」という意味と、「隷属する」という意味がある。
「天皇および日本政府の国家統治の権限は連合国最高司令官に『従う=(subject to)』」という文章の中で使われていた言葉である。
外務省は前者で解釈をしたが、独自に辞典を使って翻訳をしていた陸軍参謀たちは後者で解釈し、天皇の身分保障がなされていないと色めき立った。
これもまた、「宮城事件」が引き起こされた原因であるともいえる。
宮城事件の経過~「決起」

天皇による「聖断」を受けて、ポツダム宣言受諾論に回った(ように、参謀たちからは見えた)阿南陸相の態度の変貌や、ポツダム宣言の文言によって、参謀たちは動揺した。
参謀たちは、竹下正彦中佐、井田正孝中佐、椎崎二郎中佐、畑中健二少佐を中心として、東部軍・近衛第一師団を用いて、宮城(皇居)を占拠して天皇に聖断の変更を迫り、ポツダム宣言受諾を受け入れる選択をしている鈴木貫太郎首相や東郷茂徳外相ら首脳を排除し、連合国側との交渉を継続しようとした。
そして8月12日(玉音放送の3日前)午前9時、近衛歩兵第二連隊第一大隊が完全武装で皇居へ入城した。
折しもこの日、宮内省政務室において、玉音放送の録音が行われた日であった。
8月15日、玉音放送の録音を終えた下村宏情報局総裁や放送協会職員などが、宮城内で、先に入城していた近衛歩兵第二連隊によって拘束された。
クーデターを企てた椎崎・井田の両名は近衛師団長森赳中将に面会し、クーデターへの参加を求めたが、森師団長は否定的な態度を崩さなかったために、遅れて到着した畑中・上原は森師団長を殺害した。
これによって、東部軍・近衛歩兵に偽の命令を出すことができるようになったクーデター首謀者側は、宮中への部隊展開を命じた。
宮城事件の経過~「鎮圧」

旧日本軍の司令官、田中静壱の写真
クーデター側は、宮中を占拠したうえで玉音放送の実行を阻止するという目的も抱いていた。
宮中・宮内省内部の電話線の切断や皇宮警察の武装解除を行い、玉音放送録音盤の捜索を行っていた。
玉音放送録音盤は宮中に保管されており、発見されるのは時間の問題と言えたが、このクーデター鎮圧の芽はすでに出ていた。
それは、東部軍管区司令部の田中軍司令官・高嶋参謀長の存在であった。
クーデター参加を求めるため、田中軍司令官に面会していた井田であったが、すでに田中軍司令官・高嶋参謀長は、クーデターの鎮圧を決定していた。
高嶋参謀長は近衛第二連隊に対して、クーデターの存在と、宮城内に部隊を展開する命令が偽造であることを伝えた。
司令官の田中静壱も自ら皇居に乗り込んで叛乱将校を鎮圧。日本を無事に終戦に導いた立役者と称された。
こうしてクーデター側は、近衛師団へ命令を下すことができなくなり、クーデターは未然に防がれたのである。
クーデターのその後の動き
クーデターが鎮圧されると、椎崎・畑中の両名はそれぞれ皇居内で自決、竹下は戦後、警察予備隊に入隊、井田は在日米軍司令部戦史課に勤務した。
なお、陸軍大臣の阿南惟幾はクーデターの計画を知っており、クーデター首謀者たちに向けては「天皇の意志に反してはならぬ」「クーデターに訴えては、国民の協力は得られない」と、反対の立場を示している。
結局、阿南は玉音放送の日、深夜に割腹自決している。
また、クーデターを鎮圧した田中司令官も8月24日に司令官室で拳銃を用いて自決している。
おわりに
歴史の教科書や、長い日本史の文脈中では、「ポツダム宣言を受諾し、終戦」という短い文章にまとめられてしまうことが多い太平洋戦争の終戦であるが、戦争を終えるということ、そして降伏するということは国家・国民にとって決して容易なことではない。
クーデターを企てるというのは一般的に褒められるものではないことは明らかであるが、これまで最前線で国家のために戦ってきたという自負のある軍人にとっては、なおさら「最後の一撃」を加えずに降伏をするというのは、耐え難い決断だっただろう。
しかし、クーデターや武力によって国家の方針を変えるというのは、陸軍がかつて二・二六事件で築いてしまった「悪い前例」を踏襲したものだった。
降伏を決断した天皇も、その意を汲んでポツダム宣言の受諾のために動いた首脳陣も、そしてそれに反対したクーデター側もまた、日本という国を守りたいという思いは共通していたのだろう。
「宮城事件」は、そうした人々の思いが交錯した、終戦間際という混乱の時代に起こった悲しい事件であった。










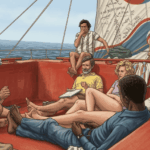






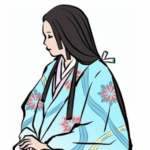







この記事へのコメントはありません。