大きな船体に航空機を載せて海を駈け、敵の艦隊や基地を攻撃するための、まさに「海上基地」ともいえるのが空母だ。
第二次世界大戦・太平洋戦争においては、とりわけこの空母と艦載機という兵器が重要視された。
時代はすでに戦艦中心の「大艦巨砲主義」を脱しつつあったのである。
しかし、太平洋戦争中盤以降においては、日本の空母は次々と撃沈の憂き目を見ていた。
そのような中、特徴的な「重装甲」を施した艦として進水したのが「大鳳」という艦である。
装甲空母 大鳳とは?

タウイタウイに停泊する大鳳(1944年5月)
空母「大鳳」は、1941年に起工された艦である。
空母という艦種は、甲板上に航空機が滑走して離着艦を行うための滑走路を必要とする。
これを飛行甲板というが、「大鳳」はこの飛行甲板を装甲で覆った「重装甲空母」として計画された空母だった。
というのも、巨大な艦体を持つ空母の最大の弱点は、その長大な飛行甲板にあったためであった。

事実、大鳳が実戦投入される2年前、1942年に起こったミッドウェー海戦においては、旗艦赤城を含め加賀、蒼龍、飛龍という4空母がすべて飛行甲板への爆撃で致命的な損害を出し、のちに沈没している。
このような弱点を克服するべく、大鳳は飛行甲板のうち格納庫の天井部分にあたる幅20mの部分に対し、20mmのDS鋼板と75mmのCNC甲板を装着し、その上の表面を木張りにするという装甲が施され、甲板の”弱点”となるエレベータにも50mmの装甲が施されていた。
また大鳳の防御は甲板だけではない。
火薬庫は水平防御・垂直防御双方を実現するための装甲板で覆われ、機関室も”高度3000mからの800kg爆弾に耐えうる「装甲」が施されていた。
大鳳出撃時の日本の状況
さて、大鳳はこのような防御装甲によって、文字通りの「重装甲空母」となったわけであるが、日本海軍の状況はどうだったか。
結論から言えば、この時点ですでに日本海軍の主力空母は相当損耗していたと言うほかない。
1942年5月上旬にあった珊瑚海海戦で空母「祥鳳」を失い、同年6月にはミッドウェー海戦によって空母4隻を失うという大損害を受けていた。
大鳳が実戦投入される段階では、すでに日本海軍側の正規空母は翔鶴・瑞鶴の2隻を残すのみとなっていたのである。
大鳳はこのような状況で、日本海軍が計画したマリアナ・フィリピン・オーストラリア方面にわたる「あ号作戦」へ従事することとなった。
出撃と沈没~ マリアナ沖海戦

アメリカ軍の攻撃を受ける空母瑞鶴と駆逐艦2隻
大鳳は先に触れた空母「翔鶴・瑞鶴」とともに、「第一航空戦隊」を中心戦力とする「小沢起動部隊甲部隊」を組織され、その旗艦としてアメリカ軍との戦いに臨むこととなる。
そして1944年6月19日午前6時30分、軽巡洋艦「能代」に所属する水偵がアメリカ軍機動部隊を発見、第一航空戦隊は128機の攻撃隊を発艦させた(「大鳳」からは42機)。
この攻撃隊はアメリカ軍のレーダー索敵とVT信号弾を活用した対空砲火によりそのほとんどが撃墜されてしまうのであるが、一方、攻撃隊を見送る大鳳にも危険が迫っていた。
それは頑丈な装甲が守る飛行甲板がある空ではなく、水中からの刺客、潜水艦であった。
このアメリカ潜水艦「アルバコア」は潜望鏡から空母に照準を合わせ、6本の魚雷を発射した。
水面下を大鳳に向かって駆ける魚雷を止めようとしたのは、一機の日本軍航空機「彗星」だった。
この彗星は攻撃隊の編隊に加わらず、突如として海へ突入したとされる。
アルバコアから放たれた魚雷の雷跡を発見し、自爆によって魚雷を阻止しようとしたのである。

彗星一二型
しかしその命がけの行動もむなしく、魚雷一本が大鳳の右舷前部に命中した。
この一発の魚雷こそが、大鳳の命取りとなった。
魚雷命中後約4時間が経過した午後2時32分、突如として大鳳はその短い艦歴を終えることとなる。
なぜ「大鳳」は魚雷一発で沈んでしまったのか?
飛行甲板のみならず、機関部や格納庫、火薬庫にも厳重な装甲を施した頑丈な「装甲空母」であった大鳳だが、結果的に一発の魚雷が原因で沈没することとなってしまった。
その原因は、被雷した際にタンクから漏出したガソリンであった。
液体のガソリンは爆発的に炎上することで知られているが、見落とされがちなのは「気化したガソリン」である。
ガソリン「揮発油」というようにすぐに揮発し、さらに静電気などのわずかな火種でも爆発する。
大鳳の場合は、ガソリンタンクから漏出したガソリンが気化し、その気化したガスが艦内に充満しつつあった。
もちろん艦内でも状況は把握されており、格納庫の鋼板を破壊したり扉や窓を開放するなど、文字通り「懸命」の換気作業が行われていた。
しかし、漏出したガソリンを処置することは困難であった。
なにしろガスが充満した揮発油タンクへ侵入することも困難であり、かつ火花を避けるため金属製の工具の使用すらためらわれる状況であったためだ。
乗員の不安をよそに、いや、乗員の不安通りに気化ガスは充満し、そしてとうとう引火・爆発した。
爆発時の光景について、重巡洋艦「羽黒」の艦橋からは、大鳳の側面にある隔壁を突き破って、艦載機・乗組員を巻き込んだ文字通りの「火柱」が吹き出す様子が目撃されたという。
かくして、空からの強力な爆撃に耐え、「多少打たれても耐えられる前線基地としての空母」の役割を期待された大鳳は、あえなく沈没してしまったのである。
おわりに

大鳳の沈没については、ガソリンタンクの部品強度に問題があったとか、被雷直後に破損したエレベータを塞いでしまったことに問題があったとか、あるいはそもそも対潜警戒が疎かになっていたなど、様々な指摘がある。
確かに、熟練工の手で部品まで完全な形で大鳳が建造され、米駆逐艦が魚雷を放っても直ちに発見・回避することが可能なほど緻密な対潜警戒が行われていれば、大鳳は沈没しなかったかもしれない。
とはいえ、それができなかったのが当時の日本の限界であったともいえる。
大鳳に期待を寄せた首脳や、大鳳建造に携わった関係者の心情は察するに余りある。
さらに残酷なことであるが、もし運良く大鳳が生き延びたとしても、大鳳の甲板には発艦した攻撃隊の「ほんの一部」しか帰還することができなかったであろう。
大鳳の存否にかかわらず、「マリアナの七面鳥打ち」とアメリカ軍から評されたこの戦闘は、大鳳のみならず日本海軍側にとって、あまりにも悲惨な戦闘となったのである。













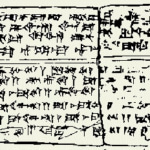











空母大鳳の遺族より、私は京都の福知山市で誕生し、祖父が海軍の軍人であった。と5歳頃に母から聞いて知ったのである。大鳳の艦長は菊池朝三なる名の御人であった。戦況が宜しくない状況になり菊池朝三は本土日本に逃げ帰ったと。米海軍の従兄弟より30年前に聞き及んだのである。菊池は海軍士官学校出身で私の父は招集で戦争に参加したのである。技術畑出身でギアの設計でギアに係る負荷の計算を私の母にさせて主に構造に力点をして構造力学は母が担っていたのである。父が戦死して28年経過した頃に舞鶴の海軍墓地で墓前祭
に参加したが菊池朝三なるごじんは一度も見参列していない。母と二人で墓前祭に参加したが菊池朝三なる者が逃げて本土に帰還していたことを聞き及んだ母はその日より墓前祭に参加しない。菊池が空母大鳳と運命をともにするのが通例であるべきことなのだ。生きて90歳以上長命とのうのうとして横須賀から他の地域に逃げた事も小生は熟知している。高額な年金を何に使ったかは知る由もないが徴兵の名のもとに生活苦でサツマイモで胸が焼ける思いが、戦禍による貧乏のもとに大学を2校を卒業し、ハワイのパールハーバーでの戦死者を祭るアメリカの思いを熟知させられた。日本の職業軍人の浅はかさを目にしたのである。80有余年たった今も、なお
パールハーバーの水面には死んだ人々の無念な気泡が海底から水面に出ている。又、死んだ人々の着衣が展示されている。平和なハワイの真珠湾に日本の空軍が攻撃した悲惨な状態が展示品からも想像されるのである。今なおのうのうとしている戦争をさせた御人は一度参加すべきであろう。日本政府高官もそうすべきである。2025/9/14 デイブ 喜久雄