NHK朝ドラ『あんぱん』で、なにかと話題になっている嵩の母・登美子。
登場のたびに、ネットでは賛否が渦を巻いています。
自由奔放に所かまわず現われ、言いたいことをズケズケと言う彼女。その姿は、戦前の「良妻賢母」とはかけ離れています。
しかし、彼女が子どもを手放し再婚せざるを得なかった裏には、親権の問題や女性が働きたくても仕事がないという厳しい現実がありました。
登美子の再婚という選択は誤りだったのでしょうか?戦前の未亡人の置かれた状況を深掘りしてみましょう。
女性の真の偉さは、未亡人になって初めて現れる

画像 : 沖縄県女子師範学校・英語の授業 public domain
戦前の理想の女性像とは、どのようなものだったのでしょうか。
昭和11年、大阪女子師範学校で行われた「修身」の講義録『女性のための修身教授録』には、「女性の運命」について次のように記されています。
「結婚して人の妻となり、さらにわが子を生むことにより、母となって子どもを育てるということ」
教員を養成する師範学校であっても、女性の理想像は「良妻賢母」だったようです。
なお、「修身」は現在の「道徳」にあたる科目で、この教授録には女性のたしなみや女、母、妻としての生き方など、「女性のあるべき姿」が書かれています。
講師を務めたのは、京都大学哲学科大学院を卒業した森信三氏。当時41歳で、大阪天王寺師範学校と大阪女子師範学校にて「修身科」を担当していました。
森先生は「女性の強さ」と題した授業で、女性の真の偉大さは未亡人になって初めて現れると説いています。
夫と死別し生計の道が絶えても、女手ひとつで子どもを育て上げた女性は少なくなく、それは男性にはできないことだという理由からです。
また、そうした真の強さを発揮できる婦人というのは、常に夫に柔順な人で、
「平生夫を尻に敷いて、勝手気ままをしているような夫人は、ひとたび夫に亡くなられるとしょげてしまって、最愛のわが子がありながら、それを夫の親元などへ渡してしまって、自分は再婚するというような、だらしなくもまた意気地のない結果になりやすいもの」
と記しています。
戦前の日本では、子どもの親権は父親のみが持っていました。そのため、父親が亡くなると、子どもは父親側の家に属することになります。
たとえ夫が長男ではなく、夫の家族と同居していなかったとしても、嫁と子どもは夫の実家の戸籍に入る決まりでした。
そのため、母親が再婚する際には、母親のみが戸籍から抜け、子どもは夫の家に留まり、母親とともに再婚先に移ることは許されなかったのです。
登美子の場合、夫の家の戸主は開業医の柳井寛にあたるため、彼女は寛のもとへ息子の嵩を預けて再婚したのでした。
手に職を付け、女手一つでわが子を育てる未亡人

画像 : メイ牛山の美容室で働く割烹着姿の美容師たち(1928年)public domain
「だらしない結果」にならないようにするには、未亡人は働いて生計の道を得なければなりません。
朝ドラ『あんぱん』で、主人公のぶの母親、羽多子が家計を助けるためにパン屋を始めたように、手に職を付けて一家を支えた女性もいました。
昭和15年(1940年)に発行された雑誌『愛育』の「片親で育てられた子ども時代の回想」という手記には、夫に先立たれ義両親と三人の子どもを養うため孤軍奮闘する母親の姿が書かれています。
中学の教師をしていた夫の死後、7歳、5歳、乳飲み子の三人の子どもを抱えた母親は、義両親の無理解や辛い状況に耐えながら、生計を立てるため保母になる決意をしました。
保母の養成所は一年間。
実家に費用を工面してもらい、二人の子どもを義両親に託し、乳飲み子を連れて母親は上京します。
彼女は努力の末に見事卒業し、念願の職を得ました。贅沢はできないながらも安定した生活を築き、子どもたちを立派に育て上げることができたのです。
義両親に仕えながら、休む間もなく奮闘した母親の姿は、子どもたちにどんな境遇にも耐える強さと愛情の深さを教えてくれたそうです。
保母以外にも、洋裁師や美容師などの学校に通い、専門技術を身につけ働く未亡人の例も見受けられます。
しかし、こうした成功例は、夫の家や実家からの金銭的支援、忍耐強く努力できる性格、さらには健康な体があってこそ実現できるものです。
実際には、多くの未亡人が生活に困難を抱えていました。
経済的、精神的な苦しみから「親子心中」に追い詰められた未亡人

画像 : 関東大震災 半壊した凌雲閣 public domain
昭和初期、日本は関東大震災に端を発する金融恐慌や世界恐慌の影響を受け、深刻な不景気に陥りました。
庶民の暮らしは厳しく、特に未亡人の生活は困窮を極めます。
昭和7年(1932年)の調査では、彼女たちの平均収入は13円85銭で、一般家庭の約三分の一に過ぎませんでした。
仕事は仕立て内職や行商、駄菓子屋など多岐にわたりますが、低賃金のため家族を養うことができません。子どもも働き、部屋を貸し出すなど工夫を凝らしても生活は苦しく、多くの家庭が親戚や知人の援助に頼っていました。
過酷な状況の中、生活を苦にして死を選ぶ者も多く、「親子心中」が社会問題として浮上します。
こうした貧困に苦しむ母子を救うための「母子保護法」が制定されたのは、昭和12年(1937年)3月のことでした。
登美子の本心

画像 : パラソルをさす女性(イメージ)public domain
登美子はどうだったのでしょう。
史実では、やなせたかし氏の母親・登喜子さんは、子どもと実母の三人暮らしを支えるため、習い事をいくつも掛け持ちし、なんとか道を付けようとしていました。
登美子もまた、もがき続けていたのかもしれません。しかし、その手に抱えきれない現実がありました。
自分の力では、子どもに十分な食事も衣服も与えられず、教育の道を開くこともできない‥‥。
そう悟ったとき、嵩にとって最善の選択は裕福な寛のもとに預けることだと、彼女は信じたのでしょう。再婚を決めたのも、子どもの幸福を願ってのことだったのかもしれません。
派手好きで美貌を誇り、流行に敏感な登美子。
奔放で傍若無人に映る彼女は、実は不器用で自分に正直な人なのでしょう。
再婚先との離縁後、柳井医院にシレっと身を寄せたときの「嵩のことが心配で」という言葉。それは、何一つ偽りのない登美子の本心だったのではないでしょうか。
参考 :
森信三 『女性のための「修身教授録」』致知出版社
『愛育』6(2),恩賜財団母子愛育会,1940-02 国立国会図書館デジタルコレクション
流石智子「歴史的にみる母子家庭の政策の変遷とその課題」金城学院大学 2014,p.10-17
文 / 草の実堂編集部












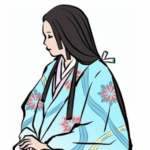









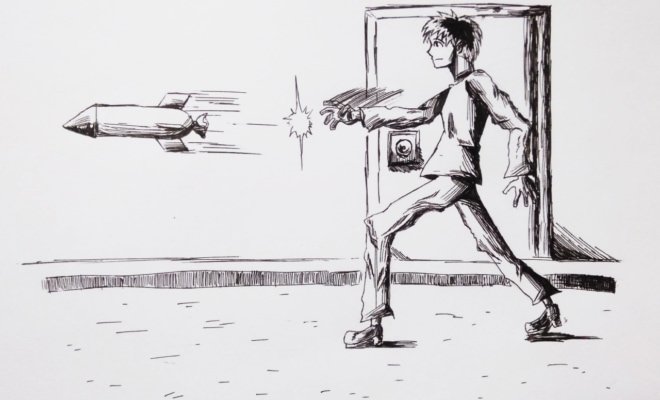


この記事へのコメントはありません。