
画像:フランス王妃イザボー・ド・バヴィエール(1370年頃-1435年9月24日) public domain
14世紀から15世紀にわたる英仏の百年戦争時代、私利私欲に溺れて自国フランスを破滅に導いた亡国の悪妃としてイザボー・ド・バヴィエールは知られています。
絶え間ない権力闘争と権謀術数の中でのイザボーの人生は、王の狂気に翻弄され、血塗られたものでした。
イングランド国王にフランスを売り渡したこの王妃を、後世の人々は長く蔑みました。
ほぼ時期を同じくしてフランスを勝利へと導いたジャンヌ・ダルクと比較して「フランスは一人の女によって滅び、一人の女によって救われる」と評されています。
イザボーは王妃として12人の子をもうけましたが、彼女が庇護を求めた男たちは次々と正気と命を失っていきました。
イザボーの人生とはどんなものだったのでしょうか。
14歳で結婚、当初は幸せだった新婚生活
イザボーは、神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世を曾祖父とし、1370年頃にドイツのヴィッテルスバッハ家のバイエルン公シュテファン3世の長女として生を受けました。
ドイツ・ミュンヘンのリュドウィスブルクの城で申し分ない教育を受け、鳥や花を愛でる少女時代を過ごしたといいます。
1385年、イザボーは14歳で当時16歳のシャルル6世と結婚します。

画像 : フランス王シャルル6世 (1368年12月3日-1422年10月21日) public domain
シャルル6世は11歳でフランス王位を継承しており、当時は彼の叔父達が王の摂政として実権を握っていました。この婚姻もイングランドに対し共闘していたドイツ帝国側と結ぶために、叔父達によって持ち掛けられたものでした。
イザボーはフランス語もままならないまシャルル6世に引き合わされましたが、王は彼女を気に入り、イザボーも若き王として魅力にあふれたシャルルに魅かれ、当初二人の新婚生活は幸せで順調でした。
婚姻から3年を経た1388年には、夫シャルル6世が摂政による支配を終わらせ、有能な顧問団であるマルムゼを復権させて親政を開始します。マルムゼによる補佐を得たシャルル6世の統治は広く支持され、シャルルは「親愛王」の名で呼ばれるほど国民からの尊敬を集めました。
一方で、それまで実験を握っていた叔父達は遠ざけられ、イザボーは王の庇護の元で恵まれた人生を歩んでいくかのように思われました。
発狂したシャルル6世
しかし、そんな幸せな結婚生活に不吉な影が忍び寄ります。
1392年8月、ブルターニュ公国に進軍している最中の森で、馬上にいたシャルル6世が突然剣を抜き、「進め!裏切り者に突撃せよ!」などと叫びながら、自軍の騎士たちを襲い始めたのです。

画像:シャルル6世による味方の襲撃 (15世紀画) public domain
同行していた騎士たちの幾人かが命を落とし、そのままシャルル6世は失神し、ブルターニュへの遠征は中止となったのです。
この後、シャルル6世は生涯にわたって精神異常の発作を繰り返すようになり、かつての「親愛王」は「狂気王」とも呼ばれるようになってしまいました。
この王の発病に乗じたのが、かつて遠ざけられたシャルル6世の叔父達・ブルゴーニュ公とベリー公でした。
再び摂政として権力を掌握した彼らの前でイザボーは成す術もなく、屈指の政治的手腕を持ち「豪胆公」と呼ばれたブルゴーニュ公(フィリップ2世)に与することを選びます。
イザボー主催の祝宴が文字通り炎上 「燃える野蛮人の舞踏会」
1393年1月29日、イザボーはある女官の結婚を祝うために、豪奢な仮装舞踏会を開催します。
舞踏会の呼び物は「森の野蛮人」に仮装したシャルル6世と、5人の貴族たちのダンスでした。
その衣装には、毛むくじゃらに見せるために松脂を染み込ませたリネンに亜麻が張り付けられていたのですが、会場に遅れてやって来たシャルルの弟・ルイが、誤ってその衣装に松明を近づけてしまい「引火」してしまったのです。
会場は大パニックとなりました。

画像:燃える人の舞踏会のミニアチュール public domain
幸い機転を利かせた貴婦人によって、シャルル6世は火の粉から守られましたが、騎士数人が消火に追われて重度の火傷を負い、仮装した6人のうち4人が焼死するという痛ましい大惨事となりました。
この事件は「風紀の乱れた宮廷の象徴」としてパリ市民の反感を買い、支配層の貴族に対する反乱の兆しを生みました。そのためシャルル6世と弟・ルイは市民の怒りを鎮めるために、罪を償うための懺悔や重い負担を強いられざるを得なくなったのです。
この事件の後も、シャルル6世は前述した精神異常の発作を繰り返し起こし、時には自身の名前も分からず、王妃であるイザボーですら認識できなくなることもありました。
国難を招いた義理の弟との不義
この舞踏会での悪評はイザボーの立場を一層危ういものとし、狂気をつのらせるシャルル6世も徐々にイザボーを嫌悪していました。
こうした状況の中で、1404年に「豪胆公」が病死したのと前後して、シャルル6世の弟・ルイが、イザボーの元に頻繁に訪れるようになります。

画像:シャルル6世の弟・オルレアン公ルイ1世 public domain
1405年頃には、イザボーは人目もはばからずにルイと過ごすようになります。
そしてイザボーは、国家財政を身内に流用するなどして金銭欲と権力、ルイとの情事に溺れていきました。
このスキャンダルはフランス国内のみならず、周辺国にまで噂されました。
しかし2人はこれを意に介すどころか、国庫を利用しての放蕩はその後も続いたのです。
血塗られていくイザボーの庇護者たち
イザボーとの仲を深めたルイですが、「豪胆公」の死後、ブルゴーニュ公位を継いだ息子・ブルゴーニュ公ジャン1世(無怖公)と対立し、その配下の者に1407年暗殺されてしまいます。
夫であるシャルル6世は精神を病み、代わりに庇護を求めた豪胆公やルイも亡くなり、ここまでかと思われたイザボーでしたが、次に拠り所としたのはなんとルイを暗殺させた、恐れ知らずで「無怖公」と呼ばれたジャン1世でした。
しかしこのジャンも、パリ南東部のモンロー橋で暗殺されてしまうのです。
亡国の王妃、実の娘を使いフランスをイングランドの手に

画像:ヘンリー5世 (イングランド王) public domain
こうして内戦と内紛に明け暮れるフランスに対し、イングランド王ヘンリー5世は「英仏併合」という野心を抱いていました。
ヘンリー5世は、イザボーの娘で当時18歳だった美しいカトリーヌと婚姻したい様子を露骨に見せていたのです。
たびたび精神を錯乱させる父・シャルル6世と、宮廷費を使い込む悪妃・イザボーとの間に生まれた王女カトリーヌは、まともな養育と衣食にも事欠き、窮状を見かねた宮廷官によって修道院に預けられるほどの幼少期を過ごしていました。
そして、ここにきてイザボーは、この娘を自らの生き残りのための切り札に使うのです。
なんとイザボーは、実の娘カトリーヌを交渉の道具としてイングランドに嫁がせることにしたのです。(※トロワ条約 フランス国王シャルル6世の死後にイングランド国王ヘンリー5世がその後継者になるとされた)
この結婚によってヘンリー5世は唯一のフランス王位の継承者となり、摂政としてフランスの国政に携るとともに、フランスの王位は代々ヘンリー5世の子孫に受け継がれることと定められました。
晩年はひっそりと
こうして一度はイングランドの手に渡ったかのように思われたフランスでしたが、2年後の1422年、ヘンリー5世は34歳の若さで赤痢によって突如亡くなってしまいました。
シャルル6世もその2か月後に亡くなりましたが、ヘンリー5世がシャルル6世よりも早く亡くなってしまったことで、再び不安定な政情へと陥ります。

画像 : シャルル7世の戴冠とジャンヌ・ダルク public domain
シャルル6世とイザボーの息子・王太子シャルルは、こうした長年の抗争によりフランス王として即位することができない状態でしたが、1429年、ジャンヌダルクの活躍でイングランドに勝利したことにより(オルレアン包囲戦)、正式にフランス王・シャルル7世として戴冠しました。
この頃には、イザボーも政治の表舞台からは遠ざけられ、1435年にひっそりと亡くなりました。ノートル・ダム寺院に運ばれた彼女の遺体にはバイエルンの貴婦人がいた他には、フランスからもイングランドからも身分の高い者は付き添っていませんでした。
こうして「稀代の悪妃」との汚名を残し、彼女の生涯はシャルル6世の傍らに埋葬されて終わりを告げたのです。
参考文献:
桐生 操『血まみれの中世王妃―イザボー・ド・バヴィエール (桐生操文庫)』









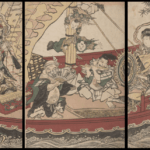








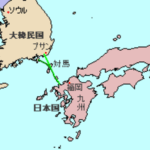
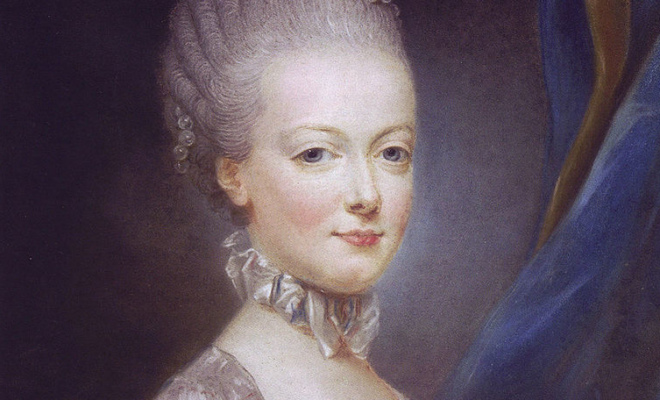




この記事へのコメントはありません。