寄生虫とは、他の生物に寄生し、その生命活動に依存して生き延びる虫の総称である。
人類にとっても非常に身近な存在であり、たとえば「ニキビダニ」として知られるダニは、ほぼすべての人間の顔面に存在している。また、幼少期にぎょう虫検査を受けた経験を持つ人も少なくないだろう。
寄生虫が宿主を死に至らしめるケースは稀であり、大抵の場合は共生関係にあるといえる。
しかし、神話や伝説の中には悍ましい寄生虫たちの言い伝えも存在する。
今回は、そのような寄生妖怪たちをいくつか紹介しよう。
1. 応声虫

画像 : 応声虫イメージ 草の実堂作成
応声虫(おうせいちゅう)とは、中国や日本の伝承に登場する奇怪な寄生虫である。
この虫は、中国の古い文献にたびたび登場し、人間の喉や腹部に寄生することで知られている。
宿主の意思とは無関係に体内から声を発し、他者からの呼びかけに勝手に答えたりするという。
唐代の文人・張鷟(ちょうさく)が著した『朝野検載』には、次のようなエピソードがある。

画像 : 城固県にある張騫像 wiki c 千里走单骑
ある人物が応声虫に寄生され、日常生活が困難になっていたという。
人から話しかけられる度に喉にいる虫が勝手に応答するので、ほとほと困り果てていた。
そこで、彼は高名な医者に相談することにした。
しかし、この医者も前例のない難病に頭を抱え、治療法の研究に日夜取り組み始めた。
ある日、医者はある妙案を思いつき、それを実行することにした。
その方法とは、中国最古の薬物書『神農本草経』に記載されている薬草の名を、患者の前で次々と読み上げるというものであった。
予想通り、応声虫はその名に反応し、ベラベラと喋り始めた。ところが、「貝母(ばいも)」という生薬の名前が出ると、虫は一切の反応を示さず黙り込んでしまったのである。
医者はこれを見て、「貝母」こそが応声虫の弱点であると見抜き、即座に薬を調合して患者に服用させた。
その結果、応声虫はたちまち死滅し、患者は元の健康な状態に戻ったという。
このエピソードは、応声虫が単なる伝説であるだけでなく、古代の人々がどのようにして未知の病に対処しようとしたかを示す一例ともいえよう。
日本の応声虫
日本にも応声虫の伝承が残っている。
元禄16年(1703年)のこと。
とある男が応声虫に寄生され、高熱に苦しんだという。
10日ほどで熱は引いたが、恐ろしいことに、腹に人間の口のような不気味な腫れ物ができていたそうだ。
男が口に話しかけてみると、まるでオウムのように真似して喋り出した。
しかも、この口に食べ物を与えてみたところ、残さずペロリとたいらげてしまう。

画像 : 日本の応声虫イメージ 草の実堂作成
「食べ過ぎは体に悪い」と男は食事を控えたが、そうするとさらなる高熱に襲われた。
そして、腹の口は「メシをよこせ!」と猛烈に罵倒してきたのだ。
こんなことが毎日続くので、男はとある名医に診てもらうことにした。
名医はこれを「応声虫の仕業だ」と即座に見抜き、ありとあらゆる薬を手あたり次第、腹の口に飲ませてみた。
すると、数種類の薬については飲むのを嫌がったので、これらの薬を調合し、毎日腹の口に無理矢理ねじ込むという荒療治を行った。
徐々に腹の口は声が枯れ、口調も弱々しくなっていき、数日後、男の肛門から角が生えたトカゲのような虫が這い出してきたという。
これこそが応声虫の本体なのであろう。
応声虫はその場から逃げ出そうとしたが、即座に撲殺されてしまった。
そして腹の口も消滅し、男の体調も次第に回復していったそうだ。
2. 疳の虫
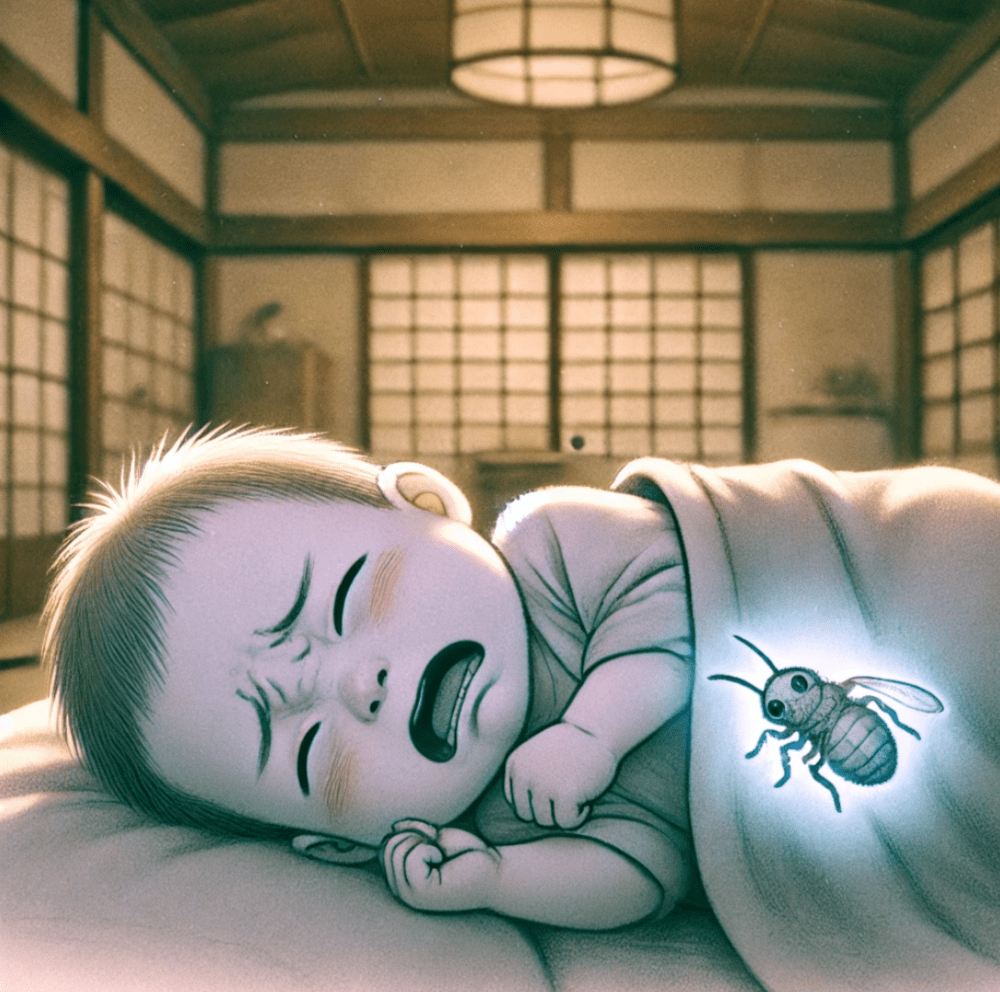
画像 : 疳の虫 草の実堂作成
子育てをする者なら誰しも、「赤ん坊の夜泣き」に悩まされるものだ。
日本では、赤ん坊や幼児が夜泣きをする原因として、古来より「疳の虫(かんのむし)」が原因とされてきた。
これは実際の虫というより、精神的不安や神経過敏を指すもので、夜泣きや癇癪の一因とされ、民間では「疳の虫」を鎮めるために、お守りや祈祷が行われることもあった。
この「疳の虫」を祓うための、いわゆる虫封じの方法としては、赤ん坊の手のひらに呪文を描き、塩で揉んで洗い流すというものがある。
そうすることで、指先から「疳の虫」が這い出し、追い払うことができると信じられていたのである。
3. アンティング

画像 : アンティング 草の実堂作成
アンティング(Bès Anting/Hantu Anting-Anting)とは、マレーシアの先住民族セノイ族に伝わる虫の怪異である。
漫画家・水木しげるの著書では「耳たぶを食べる精」という名で紹介されている。
この妖怪は、老人にのみ憑りつくといわれている。
憑りつかれた老人の耳たぶにはアリのような虫がぶら下がり、そして腫れあがる。
こうなると虫を取り除いても手遅れであり、約1週間で耳たぶが完全に消失してしまうという。
4. 焦螟
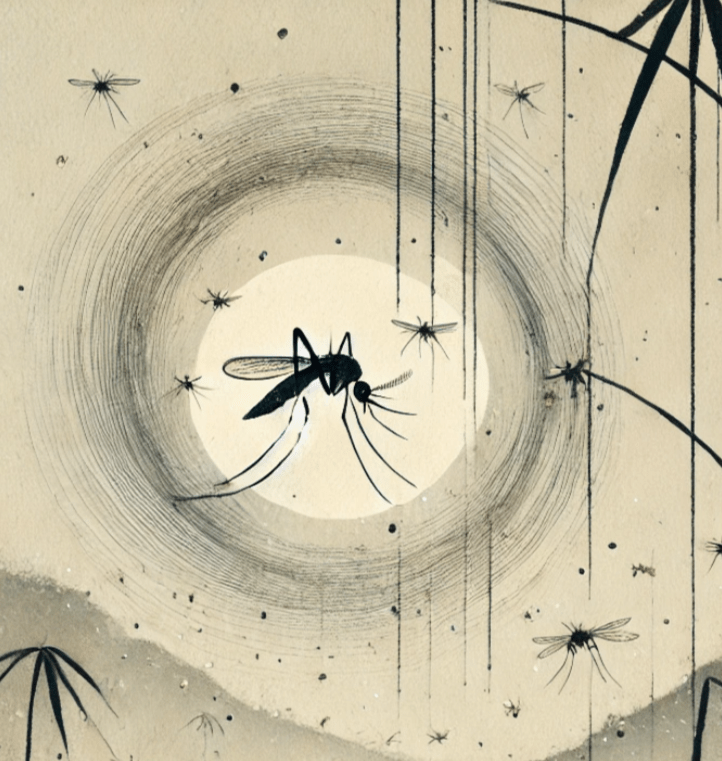
画像 : 焦螟(しょうめい) 草の実堂作成
平安時代の官僚「藤原正光」は、蚊のまつ毛が落ちるほどの小さな音でも聞き逃さない、優れた聴力の持ち主だったという伝説がある。
蚊にまつ毛があるかは不明だが、もしあるとすれば、それは極めて小さな毛ということだ。
そんな蚊のまつ毛に寄生するとされる虫が、焦螟(しょうめい)である。
古代中国の書物「列子」には、次のような説明がある。
川から生じる虫、これを焦螟と言う。
焦螟は集団で飛び、蚊のまつ毛に集まるが、小さすぎるゆえ互いに触れることはない。
蚊は、己のまつ毛に焦螟が住んでいることに気づかない。
もはや肉眼での視認は不可能なレベルである。
現代でも非常に微小で細かいものの例えに、焦螟の名が使われることがある。
俳句においては、夏の季語として扱われることが稀にあるそうだ。
使い所は難しいが、俳句を嗜むなら覚えておいて損はないだろう。
参考 : 『世界妖怪大全』他
文 / 草の実堂編集部




















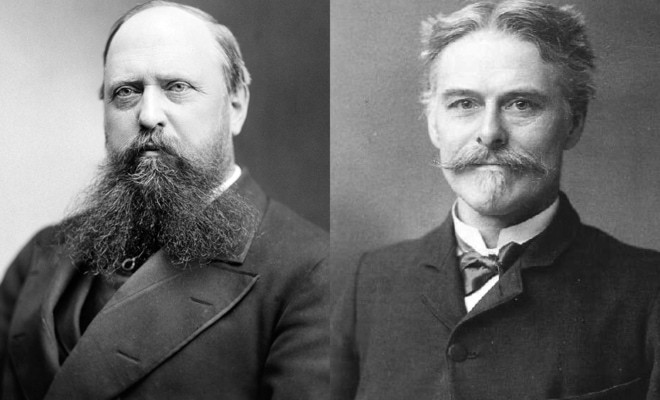




この記事へのコメントはありません。