江戸時代、長きに渡る「鎖国」体制が終わり、日本は諸外国と条約を結んで通商・貿易を行うようになった。
もちろんそれによって日本は後の国際社会の一員としての歩みをはじめたわけであるし、数多くの舶来品や海外との技術的・人的交流への道が開かれることとなった。
しかし物事には必ずプラスの面とマイナスの面がある。
日本の「開国」と呼ばれる出来事においては、それを実現するための諸外国との間の条約に問題点があった。歴史の授業などでも多くの人が耳にしたであろう「不平等条約」がそれである。
この「不平等条約」は、日本が以降に歩む歴史の中で、非常に長い期間にわたって苦しみ続ける案件のひとつとなったのである。
不平等条約のはじまり 開国から条約締結まで

嘉永7年(1854年)横浜への黒船来航
では不平等条約が結ばれる以前はどうだったかというと、日本は「鎖国」体制下にあった。
鎖国という言葉は多くの人が知るとおり、国家として他国との公式な交流を持たず孤立状態になることを指す。その目的は様々なものがあるが、こと日本の鎖国体制においては、まずキリスト教国との間の交流を断つことで日本国内にキリスト教徒が来航することを避けようとしたというものと、諸外国との貿易を幕府が一元的に管理しようとしたことを理由として見出すことができる。
前者のキリスト教の禁止については、1637年に起こった島原の乱が、幕府にとって現在の体制を揺るがしかねない大きな問題と考えられたことがその動機のひとつであったといえよう。
また、貿易の管理については日本が圧倒的な輸入超過国であったことから、国内の貨幣、特に金銀が海外に一気に流出することを避け、コントロール下に置こうとしたという見方が一般的である。
こうして築かれた日本の鎖国体制であったが、よく知られる「ペリー提督の来航」により、とうとう日本はアメリカと条約を締結することになる。これがよく知られた「日米和親条約」である。
ただし日本という国家において、アメリカとの交流が突然降って湧いたように訪れたというわけではない。公式な交流や外交こそなかったものの、1845年4月17日に鳥島・周辺海域で遭難した日本人を救助したマンハッタン号が浦賀に来航しているほか、反対に日本側がアメリカの漂流民を保護した事例もある。
また、アメリカ国内で日本を開国させるべしという議論が行われていたことは、老中首座の阿部正弘がオランダ商館を通じて承知していたし、アメリカで当時盛んだった捕鯨のために日本を開国させるべきだというロビー活動が行われていること、そしてアメリカの蒸気軍艦が日本を訪れる予定であることは幕府内部ばかりでなく、各有力譜代大名、外様の有力藩である薩摩にも知らされていたことであった。
一般民衆は突然の来航に驚いただろうが、当然当時の行政・外交を取り仕切る幕府側は事前にその情報をキャッチしていたわけである。
とはいえ幕府は当時外国との窓口として長崎を想定しており、いわゆる「黒船」の艦隊が武力をちらつかせながら久里浜や江戸湾に接近したことについては、幕府側からすれば肝が冷えたことだろう。
”不平等”な条約は何が問題だったのか?

ペリー像
さて「不平等」条約であるということは「平等でない、一方の要求ばかりが通っている」という状態であるわけだが、ペリーの来航から函館・下田の2港開港に至る「日米和親条約」は、前述の2港を条約港と位置づけ、薪水や食料、石炭といった物資の供給を行うことや、米国船舶が遭難した場合に救助をする必要があるなど、おおむね米国に対する日本側の義務を定めた条約となった。(日本側のみがアメリカに対してのみその扱いを行う「片務的最恵国待遇」もそのひとつといえる)
しかしさらに問題なのはその後、1858年に結ばれた「日米修好通商条約」にある。
この条約によって、日本国内で犯罪を犯したアメリカ人を日本法ではなくアメリカの国内法で裁くことができる「領事裁判権」が認められた。もっともこの領事裁判権は、外国人を外国の法で裁くという慣習がすでにあったため、当時の日本側にとっては疑問にも思われなかったばかりか「外国人を日本の法で裁く」ことの煩雑さから逃れられるとむしろ歓迎する向きもあったようである。
また、この日米修好通商条約の後に調印した「改税約書」によって、外国からの輸入品に対する関税を自主的に設定する「関税自主権」を失った。より正確には輸入品の「価格」に対して課税する方式であったものが、輸入された物品の原価に対して一律5%を課税するという方式に変更された(従価税から従量税への改定)。
これによって日本国内に大量の安価な輸入品が流れこむこととなったほか、大規模なインフレーション、金の流出といった問題が発生した。
日本はこうした不平等条約をアメリカのみならず当時の列強諸国と類似の条約を結ぶこととなる。アメリカ・オランダ・ロシア・イギリス・フランスの5カ国と締結されたこれらの条約を総称し「安政五カ国条約」とよぶ。
条約改正の失敗 「岩倉から大隈・青木へ繋がれたバトン」

岩倉使節団の面々。左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉、伊藤博文、大久保利通。
日本はこうした不平等条約を改正しようと、1871年に右大臣・岩倉具視を全権大使として遣外使節団を派遣し、各国との条約改正のための予備交渉を行うこととなった。
しかし、当時の日本は廃藩置県の最中で国内体制が盤石でなかったことや、アメリカ側のフィッシュ国務長官が交渉にあたって使節団に明治天皇からの委任状を求めるなど難航し、結局成果は得られなかった。しかし、この時の使節団が持ち帰った各国の視察情報、制度研究の成果などは後の交渉に生かされることとなる。
その後、伊藤博文や井上馨が引き続き交渉の準備を行い「鹿鳴館外交」と呼ばれるイメージ戦略も展開した結果、日本は「文明国」とみなされ条約改正の余地を見出す土壌が形成されていった。
また「ノルマントン号事件」が起こったことで、日本国民の間でも不平等条約・人種差別・領事裁判権に対する反発が高まった。
1888年、伊藤内閣の外務大臣に就任した大隈重信は、それまでのように「欧化」「文明国化」をアピールして交渉のテーブルに就くよりも、各国と個別に交渉を行い、領事裁判権については現行条約を厳密に運用することで、現行条約の維持が外国にとってデメリットがあるということを材料に交渉に挑んだ。
こうした努力もあり、1888年11月には当時の駐メキシコ公使・陸奥宗光によって、メキシコとの間に完全な対等条約である「日墨修好通商条約」を締結するに至ったのである。
その後、1889年に外務大臣に就任した青木周蔵は条約改正に向けて行動を開始しようとしたが、その矢先に「大津事件」の責任をとって辞任することになった。これにより条約改正は中断されることになるが、日露関係という外交的重大性のために国内法の運用を捻じ曲げることなく、法治主義の原則に則った判断がなされたことにより、諸外国からはむしろ「日本は司法権の独立が守られている」という印象づけに成功したのである。
日露戦争を経て条約改正へ 「榎本・陸奥・小村の奮闘」

榎本武揚(えのもと たけあき)
青木の後任として外相に就任したのは、かつて「蝦夷共和国」として箱館戦争の指揮をとり、新政府に抵抗した榎本武揚であった。
榎本は概ね青木の残した改正案を用いて精力的に交渉にあたり、1892年にはポルトガルとの間で領事裁判権を撤廃するなどの成果を見せている。このとき、イギリスとロシアとの間には東アジアにおける利益衝突があり、こうした微妙な情勢が日本とイギリスとの間の条約改正には追い風になるかに見えたが、国内法の改正に関する論争が起こり(法典論争)1892年に内閣は総辞職することとなる。
しかし同年、第二次伊藤内閣における外務大臣・陸奥宗光の代にイギリスとの交渉は前進を見せる。
一度は排外主義派の日本人によってイギリス人が暴行されるという事件が起こり、改正交渉の中止が通告されるなど困難もあった。しかし朝鮮半島への日本軍派遣といった大陸への影響力のアピールと、イギリス人が日本国内の土地に対して持っていた「永代借地権」を最大限尊重することを盛り込んだ硬軟を併せ持つ交渉によって、ついに1894年、日英が対等となる「日英通商航海条約」が結ばれることとなるのである。
これにより領事裁判権を完全に撤廃することに成功する。ちなみにこの半月後、日本はイギリスを後ろ盾に日清戦争を起こす。
経済・貿易面での課題である「関税自主権」の回復」は、1911年の「日米通商航海条約」でようやく成し得ることとなる。これは外相・小村寿太郎が当たった条約改正であったが、この改正成功は1904年に起こった日露戦争で日本がロシアに勝利したことで、ようやく国際的地位を認められたことが背景にあるといえよう。
かくして幕末の時代から締結されてきた不平等条約は、日清日露の2度の大きな対外戦争を経て、ようやく改正を迎えることとなったのである。
おわりに

個人間の約束事、会社同士の契約行為など、世の中には「決めごと」がある。最も規模が大きいのが国と国とが決めごとをする「条約」であるといえよう。
条約はお互いの国同士「約束を守ってくれる」という相互信頼が前提となっているわけであるが、それだけに約束事を反故にしたり無視したりといった行動がとりわけ批判されるわけである。
日本は不平等条約から始まったが、その問題に対し代々の政府・外相が乗り出して交渉を行い、ようやく対等な外交関係を作ることができたという歴史を経験している。
一連の条約改正は、歴史的に大きな意義のあるものだったといえるだろう。















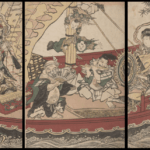








この記事へのコメントはありません。