「世論」という言葉がある。世間一般の人々がどのように考えているかという意見のことだ。
世論は直接国政に反映されるわけではないが、それでも政治家が意思決定をして、国の政策を決めるための重要な指針であることは間違いない。
さて、先の太平洋戦争において、軍部でもなく、政治家でもない「言論人」が、日本国民の世論に大きな影響を与えたという歴史がある。
その「言論人」こそ、徳富蘇峰(とくとみ そほう)という人物だ。
この記事では、徳富蘇峰はどのような人物であったのか、彼はどのような活動を行ったのかについて解説してみよう。
徳富蘇峰とはどのような人物だったのか

(徳富蘇峰, 1863 – 1957)
徳富蘇峰は、1863年に現在の熊本県に生まれた。8歳のころから読書家であり、四書五経、国史略、日本外史など、歴史関連の書物や思想書に造詣が深かったようだ。
また、1875年に入学(再入学)した熊本洋学校では、「新約・旧約聖書」にも触れている。1882年には私塾を開設し、歴史・政治学・経済学の講義を行っている。この頃の徳富蘇峰は、「自由主義・平等主義・平和主義」を唱えており、武力や権力によって個人の人権が侵されることや、巷にまま見られた軍備拡張論や国権主義論に対しては批判的であった。
1882年、言論団体である「民友社」を設立、1888年には「文学会」、1890年には「国民新聞社」を設立し、「國民新聞」を創刊している。このころの世界はすでに列強各国がしのぎを削る帝国主義時代であったが、蘇峰は自愛主義と他者尊重を説いている。
なお、蘇峰には弟がおり、ともに「民友社」を設立した「徳冨蘆花(とくとみろか)」もまた、小説家として高名である。
徳富蘇峰と「三国干渉」

遼東半島の位置 wiki c LERK
1895年、それまで自由や平和、平等を謳ってきた蘇峰を決定的に変える出来事が起こる。
日本が勝利した日清戦争において、日本に割譲された遼東半島を清国へ返還するよう、フランス・ドイツ帝国・ロシア帝国によって要求された、いわゆる「三国干渉」である。蘇峰はこのとき、三国干渉によって遼東半島を返還せざるを得なかった日本政府に対して激怒し、失望した。
自身がこれまで採ってきた平和と対話による融和という論が、列強三国による「力」に屈する様を目の当たりにしたわけである。
蘇峰はこのとき、
”これと言うのも畢竟すれば、力が足らぬわけゆえである。力が足らなければ、いかなる正義公道も、半文の価値もないと確信するにいたった。”
と、蘇峰自伝に残している。
大きく思想を変えた徳富蘇峰

この後、蘇峰は外に対しては「帝国主義」、内には「平民主義」という両者を統合した「皇室中心主義」を唱え始めた。
1931年の満州事変以降は、自らがかつて批判してきた武力の象徴である軍部と結びつきを深め、皇室中心主義を盛んに国民に向けて発信することになる。1941年には、ときの首相、東条英機の依頼により、大東亜戦争開戦の詔書を添削した。
また、後楽園球場で行われた「米英撃滅国民大会」では「日本が”アジヤ”の指導者として太平洋に君臨する秋(とき)で一億国民はこの皇国の国難をアジヤ民族と手を取り合って乗り切らねばならぬ」と演説し、聴衆を熱狂させた。日本の「大東亜共栄圏」建設のためのスローガンである「八紘一宇」との関連も見られる。この演説は、真珠湾攻撃の3日後のことであった。
蘇峰は武力や権力ではなく、自身の思想と言論によって、太平洋戦争に向けて国論・世論をまとめ、導いてきたのである。職業で言えばジャーナリストがそれに当たるが、ときに思想家であり、ときにコメンテーターでもあった。現代の言葉で言えば、SNSで人々の意見を導く「インフルエンサー」や、熱烈なファンと自身の情報媒体を持つ「ユーチューバー」に近い存在とでも言えようか。
徳富蘇峰の最期

太平洋戦争にあたっては、開戦に向けて国論・世論を導き、戦中もまた「挙国一致」の体制を築くべく活動してきた蘇峰であったが、1945年、ポツダム宣言が発せられ、蘇峰の反対意見も虚しく、ポツダム宣言は受諾され、日本は降伏することになる。蘇峰は自らの戒名を「百敗院泡沫頑蘇居士」とした。
世論を先導してきた蘇峰はA級戦犯の容疑をかけられていたが、老齢と持病のために自宅拘禁とされた。1951年には、自身が1918年から執筆を続けていた「近世日本国民史」の執筆を再開、1952年に完成させた。その後も「勝利者の悲哀」や「三代人物史」などを執筆し、1957年に95歳で没した。
それにしても、「百敗院泡沫頑蘇居士」という戒名には、蘇峰の性格の激しさがにじみ出ている。
蘇峰の「近世日本国民史」

蘇峰が執筆した「近世日本国民史」は、全100巻にも及ぶ膨大な情報量を持つ日本の通史書である。
安土桃山時代から西南戦争までを綴っており、多くの貴重な文献を集めて執筆された大作であり、蘇峰はこの業績によって1923年に恩賜賞も授与されている。
この「近世日本国民史」は戦後、日本の教育に直接用いられることはなかった。蘇峰の思想や経歴を鑑み、「民主国家として生まれ変わった」日本にはふさわしくないと判断されたのかもしれない。しかしながら、実に多くの歴史小説が、実はこの「近世日本国民史」を土台として執筆されている。
この「近世日本国民史」は、まさに蘇峰が人生をかけて挑んだ仕事のひとつであったと言えよう。
おわりに

水俣市にある市立蘇峰記念館(旧水俣市立図書館「淇水文庫」)wiki c hyolee2
思想や考え方が変わるのは人の常だ。
しかしながら、対話と平和を重んじてきた人物が、「畢竟すれば(結局)、力が足らぬわけゆえである。力が足らなければ、いかなる正義公道も、半文の価値もないと確信」するほどまでに思想を変えることは珍しい。
それと言うのも、正当な条約という手続きによって割譲されたものを、外国からの圧力によって返還せざるを得なかったという三国干渉が、蘇峰の心に大きな衝撃を与えたのであろう。そして、蘇峰が言論人として活躍できるほどに支持を集めたのは、軍部の「お墨付き」もあったろうが、なにより日本国民が、蘇峰の「力が足らぬ」という論に同意したからである。それほどに、当時の日本人は国際社会における不公平・不平等を感じていたし、諸外国の不正義を感じていた。
蘇峰を指して、「日本国民を戦争に駆り立てた扇動者」とする向きも一部にはある。しかしそうではないだろう。蘇峰が影響力を持つ言論人でありつづけたその足元を支えたのは、蘇峰の論を熱望し、そして蘇峰の言葉を聞いて熱狂した、他でもない日本国民たちだった。そういう時代だったのである。













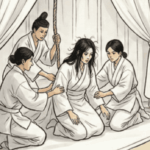






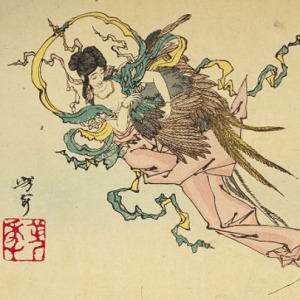




この記事へのコメントはありません。