いよいよクライマックスを迎える「らんまん」。
寿恵子のモデル・壽衛(すえ)は夫の牧野富太郎よりも先に亡くなっているのですが、ドラマではどのように描かれるのでしょうか?
今回は史実を元に牧野壽衛(通称・壽衛子)の生涯をひも解いてみたいと思います。
壽衛の死
この投稿をInstagramで見る
新しい昭和という時代とともに念願のマイホームに移り住んでまもなく、壽衛は体の不調を訴えるようになりました。
昭和2年、牧野富太郎が65歳で理学博士の学位を得たその年、壽衛は1月から7月まで入院生活を送り、退院したのもつかの間、翌年の1月に再び東京帝国大学医学部附属病院に入院しました。
保険のない時代に入院費用をまかなうのは、たやすいことではありません。理学博士となって大学からの月給が12円昇給したとはいえ、牧野家の家計は相変わらず火の車でした。
大学の講師であろうとなんであろうと、金のないものに対する病院の仕打ちは冷たいものでした。
入院費が滞ると「ベッドを待っている患者が大勢いるから」と言って、看護師はシーツで壽衛の頭と足をくるみ、二人がかりでさっと持ち上げて床に降ろしてしまうのです。
2月23日、またもや入院費が支払えず、壽衛は病室の床に降ろされてしまいました。毎朝見舞いに訪れていた家族がその様子に呆然とする中、壽衛の容体が急変。あわてた看護師がすぐさま寿恵をベッドに戻し、医師を呼びに行きます。
看護師たちのバタバタと駆けまわる足音や医師を呼ぶ怒声、娘たちの泣き叫ぶ声が響く中、病室に駆けつけてきた牧野が放った言葉は、
「ああ、いまこそ、われわれはお母さんに心からなる感謝を捧げねばならないのだ」
大げさで芝居がかったこのセリフは少々場違いな感じもしますが、その言葉を聞いた壽衛の最期の様子を小説家・大原富枝は『草を褥に 小説牧野富太郎』で次のように書いています。
“そのとき壽衛子は、いかにも苦しそうに顔をしかめ、最後の力をふり絞って首をくるりと廻して顔を夫から反向(そむ)け、眼を閉じた。そのときが、すなわち臨終であった。”
苦しむ顔を夫に見られたくなかったのか、それとも最後くらい静かに逝かせて欲しいと思ったのか。
昭和3年2月の寒い朝、壽衛は息を引き取りました。55歳でした。
壽衛の結婚生活

画像 : 出典:牧野富太郎著『図説普通植物検索表』第1 (草本),千代田出版社,1950. 国立国会図書館デジタルコレクション
明治21年、壽衛は牧野と結婚しました。牧野26歳、壽衛15歳の時です。当時では珍しい恋愛結婚でした。
牧野は自叙伝で壽衛のことを次のようにしたためています。
“長年の間妻に一枚の好い着物をつくってやるでなく、芝居のような女の好く娯楽は勿論何一つ与えてやったこともないくらいであったのですが、この間妻はいやな顔一つせず、一言も不平をいわず、自分は古いつぎだらけの着物を着ながら、逆に私たちの面倒を、陰になり日向になって見ていてくれ、貞淑に私に仕えていたのです。”(牧野富太郎著『牧野富太郎自叙伝』より引用)
牧野家は莫大な借金を抱え生活は困窮していましたが、壽衛は決して不幸ではありませんでした。
子どもたちから、おいしそうなものが売っているという話を聞けば一緒に出かけて食べさせ、地方に採集に出かけた夫が植物を送ってくると、子どもたちと大騒ぎで植物を乾かす作業に取り組みました。
壽衛はたいへん気前のいい性格で、家に出入りする学生にはいつもご飯を食べていくよう勧めました。学生も牧野家のすさまじい貧乏を知っているので遠慮して帰ろうとするのですが、それを無理に引きとめてでも食事をさせたそうです。
また、牧野の存在も楽しい生活に欠かせませんでした。次女・鶴代さんの回想によると、牧野はもともとユーモアにあふれた人で、常におもしろいことを言っては家族を笑わせ、また非常に子ぼんのうで、病気になった子どもを見守る真剣な顔は忘れられないと述べています。
金もないのに芸者に帯を買ってやったり、見栄を張って汽車の一等に乗ったり。ぜいたくをやめられない牧野のふるまいを「まるで道楽息子を一人抱えているよう」と壽衛は言っています。
壽衛の楽天的な性格とふところの深さによって、牧野家の明るい生活は支えられていたのかもしれません。
自立した女性だった壽衛

画像. 牧野記念庭園 wiki c
牧野家といえば真っ先に思い浮かぶのは借金です。
1万円を定期預金にしておけば利息で暮らせると言われた時代に、牧野家は3万円(現在の価値で6千万円から9千万円)の借金を抱えていました。
こんな莫大な借金を背負って生活する心労は想像を絶しますが、壽衛はただ泣いて暮らしていたわけではありません。
借金取りを追い返し、質屋通いは当たり前。家財道具は競売にかけられ、家賃が払えず30回も引っ越しをするような生活の中、彼女は待合茶屋を経営し、さらに自分で家を建てるという常人には成し遂げがたい人生を送りました。
壽衛の強さ・たくましさは、陸軍で権勢を誇っていた父親が幼いころに没落し、飯田町の大邸宅も財産もお嬢様生活も何もかもを失ったときから育まれていたのかもしれません。
父親の死後、母親は自活のために芸妓置屋や菓子屋をはじめます。そんな母親の姿を見て育った壽衛が貧乏生活から抜け出すために自分の店を持ったのは、自然の成り行きだったのでしょう。
彼女は待合茶屋を二流どころまで成功させます。店の経営が傾き始めるといさぎよく売却し、店を売って得たお金で東大泉の地に終の棲家を建てました。
牧野富太郎を語るとき、糟糠(そうこう)の妻といわれる壽衛。彼女は夫や家族に尽くすだけでなく、人にぶら下がらず自分の足で立ち、自分の人生を生きた人だったのです。
参考文献
牧野富太郎『牧野富太郎自叙伝』
大原富枝『草を褥に 小説牧野富太郎』
関連記事 : 他のらんまんの記事一覧











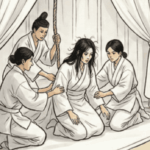











この記事へのコメントはありません。