
エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン(1781年)
ルブラン夫人 (1755年~1842年)は、フランスの画家。
本名はエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン。
パリに生まれ、王妃マリー・アントワネットの肖像画を多く描いたことで知られる、18世紀のもっとも有名な女性画家である。
10代前半頃にはもう絵を描き始め、86歳でこの世を去るまでに多くの作品を生み出した。
今回は、そんなヴィジェ=ルブランの生涯とエピソードについて、詳しく調べてみた。
ルブラン夫人の生涯

麦わら帽子を被った自画像、1782年。
ヴィジェ=ルブランは、1755年、画家である父ルイ・ヴィジェの元に生まれた。
父は娘に絵画教育を施し、ヴィジェ=ルブランの周りには、常に大家の画家たちからの強力なアドバイスと、サポート体制があった。
その中には、ガブリエル=フランソワ・ドワイアンや、ジャン=バティスト・グルーズ、クロード・ジョセフ・ヴェルネなどの名だたる画家たちがいる。
そのように恵まれた環境で育ったヴィジェ=ルブランは、10代前半頃には、すでに職業画家として活躍していた。
主に依頼主の元に出向き、肖像画を描いていたようである。
1776年、21歳の時に画商であり自らも画家として活動する、ジャン=バティスト=ピエール・ルブランと結婚した。
この頃、マリー・アントワネットの肖像画を描くためにヴェルサイユ宮殿に招かれると、その素晴らしい筆さばきで、マリー・アントワネットの心をしっかり掴んでしまった。
マリー・アントワネットはヴィジェ=ルブランを重宝し、自身の肖像画はもちろんのこと、アントワネットの子供たちや王族、その家族の肖像画を数多く依頼した。

モスリンのシュミーズ・ドレスを着た王妃マリー・アントワネット。1783年
マリー・アントワネットとヴィジェ=ルブランは強い友情関係で結ばれ、その後ヴィジェ=ルブランがフランスの王立絵画彫刻アカデミーに入会をする際には、アントワネットの強力な後押しを得たというエピソードが残っている。
やがてフランス革命が起こると、ヴィジェ=ルブランはフランスから亡命し、イタリアやオーストリア、ロシアなどで画家として働いたという。
特にローマでは作品が高く評価されたり、ロシアでは当時の女帝エカチェリーナ2世の肖像画を手がけたという。

ポーランド王、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキの肖像、1797年。ヴィジェ=ルブランは、ヨーロッパ諸国を転々としながら、王族・貴族との交流を深めていった
そして1802年、再びフランスに戻ったヴィジェ=ルブランは、皇帝ナポレオンの妹の肖像画を描いた。
しかし、ナポレオンとは折り合いが悪く、その後はスイスのジュネーブにてジュネーブ芸術促進協会の名誉会員として活動を続けた。
だが、ナポレオンが斃れ、フランスが王政復古を果たすと、ルイ18世には手厚く迎えられ、再びフランスへと帰国した。
フランス革命から王政復古まで、激動の時代を生き抜きながらも、絵を描き続け、その作品は高く評価されている。
ヴィジェ=ルブランの画家としての人生は、順風満帆といえるが、実は家庭運には恵まれなかったと言われている。
夫であるルブラン氏は賭博好きで、常に金銭問題を抱えており、また夫との間に生まれた一人娘・ジュリーも、長じて素行が悪くなり、温かな家庭を築き上げることは出来なかったようだ。
ただ、ヴィジェ=ルブランは女流画家としてはもっとも成功をおさめた人物で、彼女の作品は現在でも、欧米の主要な美術館で観覧することができる。
ヴィジェ=ルブラン夫人と娘ジュリー

《ヴィジェ=ルブラン夫人と娘ジュリー》は、1786年頃に製作された、ヴィジェ=ルブランの絵画である。
上の作品は白いドレスを着たヴィジェ=ルブランが、娘のジュリーを抱きかかえている「母娘の絵」であるが、実はこの作品は、大きな物議を醸すことになる。
絵の中のヴィジェ=ルブランは、歯を見せて笑っている。
歯を見せて笑う表情は、当時は風俗画にのみ見られる表現方法で、ヴィジェ=ルブランが普段描いているような西洋絵画の技法としては、タブー視されるものであった。
だが、ヴィジェ=ルブランは慣習に囚われることを嫌い、その生涯の中で、新しい画法をどんどん開発していったという。
マリー・アントワネットと子供たち

マリー・アントワネットと子供たち
ヴィジェ=ルブランが各国の王族や貴族に人気のあった理由として、「実物よりもほんの少しだけ美しく書く」という画法が挙げられている。
王族の肖像画、というのは、当時の市民階級への重要なアプローチ方法のひとつであった。
1787年に製作された《マリー・アントワネットと子供たち》も、その意図をもって描かれた絵画のひとつである。
当時、「首飾り事件」によって世論から厳しい批判を浴びていたマリー・アントワネットだが、アントワネットに気に入られ、手厚い保護を受けていたヴィジェ=ルブランは、彼女のイメージ回復を図る。
王妃アントワネットのイメージを良くするため、王妃の周りに子供たちを配置し、慈愛に満ちた母親像という姿を演出したものの、世論があまりにも批判的であったため、発表を見送ったという。
この作品はフランス革命の勃発する2年前に描かれ、その後アントワネットは1793年に処刑されている。
現在でもフランスのヴェルサイユ美術館には、この《マリー・アントワネットと子供たち》が所蔵されている。















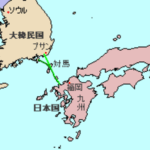








この記事へのコメントはありません。