日本独特のレビュー・少女歌劇。
歌やダンスにお芝居、一糸乱れぬラインダンスなど、華やかで煌びやかな世界は大正時代から現在まで人々を魅了し続けています。
NHK朝の連ドラ「ブギウギ」の福来スズ子は「敵性歌手」と呼ばれ、さまざまな制約を受けましたが、少女歌劇の世界も戦争へ巻き込まれていきました。
戦時下での少女歌劇の活動とは、いったいどのようなものだったのでしょうか?
戦地慰問と挺身隊。宝塚歌劇団の戦時下での変遷

画像. 1943年3月『翼の決戦』(壇上が春日野八千代). public domain
昭和12年、日中戦争が勃発すると、宝塚少女歌劇団では軍国レビューや国策レビューといった時局を反映した作品が上演されるようになります。
『皇国のために』、『少年航空兵』、『軍国女学生』といった演目が、少女歌劇の雰囲気はそのままに、あの手この手で当局の指示に違反しないように演じられていました。
太平洋戦争開戦後、戦局が厳しくなった昭和19年2月「決戦非常措置要綱」によって、全国の19の大劇場が閉鎖に追い込まれます。
宝塚大劇場と東京宝塚劇場を失うと同時に団員や生徒たちは、各地を慰問する「宝塚歌劇団移動隊」と工場で勤労奉仕をする「宝塚歌劇団挺身隊」へと分けられました。
歌劇団員が戦地慰問へ。「宝塚歌劇団移動隊」

画像. 1943年頃、慰問公演の様子. public domain
“兵隊さんたちが駐留しているところで『荒城の月』とか童謡を歌って聴かせるのが私たちの役目でした。ある時、テントの部屋にいたら、兵隊さんが日本刀を抱えて入ってきて、「おまえたちの慰問はそれだけじゃないぞ!」と怒鳴り込んできました…”
宝塚歌劇団に在籍した春日野八千代が自伝『白き薔薇の抄』で綴った、満州での慰問公演の様子です。
この後、男の生徒監が毅然とした態度で「彼女たちの慰問は歌や踊りだ」と言い返し、事なきを得ましたが、春日野は非常に怖い思いをしたと当時を振り返っています。
「宝塚歌劇団移動隊」は、隊長1人、十数人の少女と衣装係、オーケストラの総勢20人で編成され、国内のみならず、昭和17年から3回にわたって満州公演も行っています。
国内の慰問では、病院や炭鉱などで公演を行い、当時のヒット曲『九段の母』や『毬と殿様』などの童謡を歌いました。
凄惨を極めたのは、昭和19年9月から12月に行われた大連、奉天、撫順、新京、ハルビンなどを巡る満州への慰問公演です。前述の春日野のほか、少女たちはさまざまな苦難に見舞われました。
広い荒野を幌のないトラックで走り回り、自分が今どこにいるのかさえ分からない日々でした。
山道では 兵隊がオオカミに殺されるのを目のあたりにし、風呂ではシラミにおびえ、濡れた手ぬぐいはすぐに凍ってしまう。それほどの極寒の地で、慰問公演は外で行われるため凍傷にもなりました。
ただ、そんな過酷な状況の中でも、彼女たちは使命感を持って行動をしており、食事の準備で公演を見ることができない若い兵隊に特別に歌を聴かせてあげたり、兵隊から手紙を預かったりすることもありました。
当時、戦地から出す手紙には検閲があり、兵士たちは思うように手紙を書けませんでした。
そこで、兵隊たちは密かに慰問団員に手紙を託したのです。前線の兵士が、自分が生きていることを家族や親しい人に直接知らせることができる貴重な手段でした。
戦時下における松竹歌劇団(SKD)の変遷

画像. ※松竹歌劇団.日独伊三国同盟を題材とした『フランス起てり』(1941年). public domain
昭和19年、松竹歌劇団の本拠地である東京の国際劇場が閉鎖され、松竹歌劇団と松竹少女歌劇学校は解散。新たに「芸能女子挺身隊」を結成し、希望者がこれに参加する形となりました。
さらに終戦直前の昭和20年には「松竹舞踊隊」を結成。劇場公演を行っています。
「芸能女子挺身隊」の活動は、満州、上海、南京などの前線や病院などの慰問公演で、昭和19年には満州からハルピンの奥地、中支、上海の各地を慰問しています。
慰問団は22名。その中には、当時娘役スターだった並木路子も含まれていました。
昭和20年4月、並木路子は再び中国へ慰問に向かいます。3月の東京大空襲で、母親を亡くしたばかりでした。
団員の移動手段はトラックで、絶対外を見てはいけないと命令されており、慰問先がどこなのかは分かりませんでした。
宿舎は粗末なものでしたが、女性だということで気を遣ってくれたのでしょう。着替え用のカーテンも用意され、兵隊の部屋よりもずいぶんましでした。
ただし宿舎の外にあるトイレは、女一人では怖くて行けず、仲間と連れ立って行ったそうです。
いつゲリラに襲撃されるか分からないような危険な地を転々とする慰問公演でしたが、兵隊たちは非常に喜んでくれました。勇ましい軍歌よりも優しい歌が好まれ、感激のあまり涙を流す兵隊もいたそうです。
並木が驚いたのは、兵士たちの意気揚々とした姿でした。
本土は空襲で破壊され、敗色濃厚となっているにもかかわらず、慰問先の兵士たちは戦争に負けるとはみじんも思っていない。おそらく正確な情報が遮断されていたのでしょう。兵士たちと自分の戦争に対する温度差に並木は違和感を覚えたのでした。
無事に公演を終え慰問団は上海へ戻りました。労をねぎらうためフランス租界で李香蘭のステージを楽しんだのもつかの間、ドイツ降伏の報が流れ、すぐさま帰国するよう命令が出ます。
並木たちは中国人と日本の兵隊でごった返す汽車を何度も乗り換え、船に乗り、九州の小倉からまた汽車に乗りました。
空襲警報が鳴るたびに避難し、昭和20年7月、やっとの思いでたどり着いた東京は焦土と化していました。
終戦後『リンゴの唄』が大ヒット
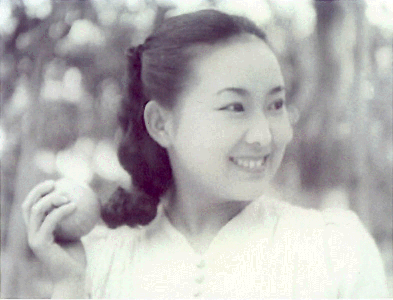
画像. 『そよかぜ」の並木路子. public domain
終戦直後の10月、並木路子主演の映画『そよかぜ』が公開され、並木が歌った主題歌『リンゴの唄』は爆発的なヒットを記録。『リンゴの唄』の明るさと爽やかさは戦争で疲弊した人々の心を癒し、勇気と励ましを与えたと言われています。
映画の撮影中もレコーディングのときも彼女は周りから「明るく、明るく」と指示されました。
後年、「明るくと言われても、そんなに簡単に明るくなんかなれなかった」と並木は述べています。
並木路子は東京大空襲で母親を失い、父と兄は戦死。将来を約束した人は特攻隊員となり、帰ってくることはありませんでした。
戦禍をくぐり抜け生き延びた並木路子。そんな彼女の悲しみを押し殺した明るい歌声だからこそ、人々は心を奪われたのかもしれません。
参考文献
辻則彦『宝塚 幻のラインダンス』.神戸新聞総合出版センター
菊池清磨『流行歌手たちの戦争』.光人社










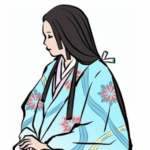








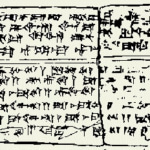



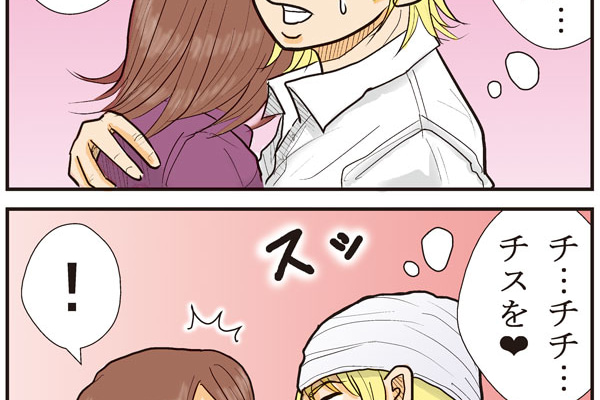

この記事へのコメントはありません。