
画像 : 1963年の映画『クレオパトラ』より、エリザベス・テイラー(クレオパトラ7世)とリチャード・バートン(アントニウス) publicdomain
クレオパトラ7世は、「世界三大美女」として名高く、古代エジプト・プトレマイオス朝の最後の女王である。
しかし、彼女の墓は現在まで見つかっておらず、彫刻などの歴史的史料もほとんど残っていない。
唯一彼女について知る手がかりは、後世にローマの歴史家が残した史料である。
今回はこのローマの記録を基に、クレオパトラ7世(以下、クレオパトラ)の人生と最期について迫る。
ただし、クレオパトラはローマと対立していたため、ローマ側の史料には偏りがある可能性があることを前置きしておく。
実はギリシャ人だったクレオパトラ

画像:ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス「クレオパトラ」public domain
古代エジプトとは一般的に、紀元前3000年ごろから紀元前30年までの王朝時代を指す。
クレオパトラが生まれる約300年前、エジプトはペルシア王国の支配下にあった。しかし、アレクサンドロス大王の侵攻により、エジプトはマケドニアの支配下となる。
アレクサンドロス大王の死後、その後継者となったプトレマイオス1世によって、プトレマイオス朝が建国された。
それから約240年が経ち、プトレマイオス12世の三女として生まれたのが、かの有名なクレオパトラである。
つまり、クレオパトラおよびプトレマイオス朝の王家の人々は、ギリシャ人であったということだ。現代では、褐色の肌におかっぱ頭のイメージがあるクレオパトラだが、実際のところ、彼女は白人で髪もギリシャ風の巻き髪だったと言われている。
クレオパトラの即位
クレオパトラは18歳の頃、弟のプトレマイオス13世と結婚し、共同でエジプト王に即位した。
当時、姉弟が父プトレマイオス12世から引き継いだエジプトは、かなり危うい状況にあった。
紀元前3世紀ごろから政治が腐敗し始め、賄賂や汚職による財政危機、それに伴う農村の貧困などが原因で、かつての栄光を失っていたのだ。
その頃、西方ではローマが力をつけており、国際情勢は揺れ動いていた。
父プトレマイオス12世はローマに多額の賄賂を贈るなどして、首の皮一枚でエジプト王の座を保っている状態だった。常にローマの顔色を伺い、ローマの支持なしでは王位の継承すらも危うい状況だったのである。
しかしクレオパトラは、決して飾り物の女王ではなかった。
美しい声で多言語を操り、教養を身につけ、乗馬を好み軍隊の指揮まで行う、真の王にふさわしい女性であった。
さらに、プトレマイオス朝において、エジプト語を話せるファラオはクレオパトラが初めてであった。このエピソードからも、彼女の勤勉さや統治に対する真剣な姿勢がうかがえるだろう。
ローマの英雄・カエサルとの出会い

画像:ニコラ・クストゥ「ガイウス・ユリウス・カエサル立像」 public domain
クレオパトラはさまざまな仕事をこなし、王として非常に優秀であった。しかし、共同統治を嫌った弟プトレマイオス13世との政治闘争に敗れ、首都アレクサンドリアから追放されてしまう。
クレオパトラはシリアの砂漠にテントを張りながら、「絶対に返り咲いてやる」と意気込み、ひと夏で軍隊を編成した。
一方その頃、ローマでは内戦が起こっており、カエサル派と元老院派の争いが激化していた。(ローマ内戦)
元老院派は名将ポンペイウスが軍を指揮し、兵数や兵站においても圧倒的に優勢であった。しかし、長期戦を強く推すポンペイウスの戦略を元老院は採用せず、結果としてファルサルスの戦いで元老院派は敗北した。

画像 : ミュンヘン・レジデンツにあるポンペイウスの胸像 public domain
カエサルに追われた劣勢のポンペイウスは、旧知の仲であったプトレマイオス朝を頼ってアレクサンドリアに逃げ込む。しかし、プトレマイオス13世はカエサルに恩を売ろうと考え、ポンペイウスを殺害してしまう。
かつての仲間であり好敵手でもあったポンペイウスの無惨な死に涙したカエサルは、クレオパトラと手を組み、共にプトレマイオス13世を排除することに成功した。
そしてカエサルとクレオパトラは、政治的な面だけでなく男女としてもパートナーとなった。このため、二人の関係については「クレオパトラがカエサルを誘惑した」と語られることが多い。
しかし、カエサル自身も資金繰りに困っており、潤沢な資金を持つエジプトを自由に操りたかったのだ。彼にとってクレオパトラと手を組むことは、多くの面で得策だったと言えるだろう。
もちろん、クレオパトラも王位奪還のために、あらゆる手段を使ってカエサルに近づいた。二人の関係は、愛人というよりも政治的パートナーの側面が強かったように思われる。
アントニウスとの生活

画像:フランス・ウーテルス「アントニウスとクレオパトラ」public domain
しかし、カエサルはその後、共和制の復活を望んだ派閥によって暗殺されてしまった。
彼の死後、ローマでは再び三頭政治が敷かれたが、内乱が多発した。この混乱を制圧し、ローマのトップの座に近づいたのが、カエサルの部下であるアントニウスであった。
カエサル亡き後、クレオパトラはエジプトの王座を守るためにアントニウスと手を組むしかなかった。
クレオパトラはタルソス(現在のトルコ)でアントニウスを過剰なまでにもてなし、彼の信頼を勝ち得た。その結果、アントニウスは彼女に心を惹かれ、二人は政治的にも男女としても固い絆で結ばれることとなった。
クレオパトラとアントニウスは「真似のできない生活の会」というサークルのようなものを起ち上げ、豪華絢爛で贅沢三昧な生活を送った。
日夜宴会を開いては酒を飲み、新しいゲームを考えて遊び、時には召使いの恰好に変装してアレクサンドリアの街を練り歩いたという。
クレオパトラとアントニウスは、その後11年間にわたり生活を共にした。
オクタヴィアヌスとの対立
ほとんどの日々をクレオパトラと共に過ごしていたアントニウスは、ローマでの人気が次第に陰りを見せ始める。そのきっかけとなったのが、彼の遺言状が仲間の裏切りにより元老院に渡ってしまったことだった。
遺言状の内容はクレオパトラを贔屓にしており、ローマ人にとって受け入れがたいものであったため、彼への世論は厳しくなっていった。
ローマから見れば、エジプトは東方の属国の一つであり、さらに統治者は女王クレオパトラであった。当時のローマでは、女性の地位は低く、奴隷と同等と見なされていたため、クレオパトラが統治するエジプトを見下していたのだ。
アントニウスを追い込んだのは、三頭政治の有力者でありカエサルの甥であるオクタヴィアヌス(アウグストゥス)であった。

画像:「パクス・ロマーナ」を演出したオクタヴィアヌス(アウグストゥス) public domain
オクタヴィアヌスはクレオパトラを「エジプト女」と揶揄し、アントニウスに対するネガティブキャンペーンの材料に使った。この時期のネガティブなイメージが、現代に伝わるクレオパトラのイメージの元となっていると言われている。
追い詰められたアントニウスは公職を追放され、ついにオクタヴィアヌスと戦火を交えることとなった。もちろん、クレオパトラはアントニウスに加勢し、軍事支援や食料支援、金銭的支援など、あらゆる手を尽くした。
しかし、クレオパトラとアントニウスの連合軍はオクタヴィアヌスに敗北してしまう。
もはや再建の見込みがないアントニウスは白旗を上げ、「クレオパトラを生かしてくれるなら、私は死んでもいい」と交渉するが、オクタヴィアヌスはこれを受け入れなかった。
クレオパトラの最期

画像:クレオパトラの死 public domain
一方、クレオパトラも秘密裏にオクタヴィアヌスと交渉していた。
その内容は「王冠を授けるので許してください」というもので、エジプトの統治権を譲るという意味である。
オクタヴィアヌスは、これに条件付きで応じた。「まずは軍隊と王位を放棄せよ。それからクレオパトラの処遇を決める。アントニウスを差し出せば処罰しない」というものであった。
しかし、オクタヴィアヌスはクレオパトラをローマに連れ帰り、凱旋式で戦利品として見世物にするつもりであった。
クレオパトラはこの要求を拒否した。おそらく彼女は、この局面で自身の死を覚悟したのであろう。それならば、凱旋式でみじめな姿を晒すよりも、エジプト王として最後まで対立姿勢を崩さないことを選択したのだ。
アントニウスが最後の戦いに敗れ、アレクサンドリアの王宮に帰ってきた時、クレオパトラの訃報を耳にした。ショックを受けたアントニウスは、自ら腹に剣を突き立てて自害してしまう。しかし、クレオパトラの死は誤報であり、彼女はまだ生きていた。
瀕死の状態でその真実を知ったアントニウスは、従者に頼んでクレオパトラの元へ運ばれ、彼女の腕の中で息を引き取った。クレオパトラは自身の不幸も忘れ、胸をかきむしりながら彼の死を嘆き悲しんだという。
一方、クレオパトラを生け捕りにしたいオクタヴィアヌスはアレクサンドリアに上陸し、ついにクレオパトラを捕えた。
捕えられたクレオパトラは、オクタヴィアヌスの許可を得て、アントニウスを埋葬することはできた。
そしてローマへ発つ3日前、クレオパトラは「今日しかない」と、ある決意を固めた。
彼女はアントニウスの墓参りをした後、沐浴し、化粧を済ませ、女王の衣装を身に纏い豪華な食事をとった。
そして、毒蛇に身体を噛ませ、39年という短い生涯に幕を閉じたのである。

画像:アントニウスとクレオパトラの出会いを描いた絵画(ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ作)public domain
クレオパトラがオクタヴィアヌスに宛てた最後の手紙には、「遺体はアントニウスの傍に埋葬してほしい」と書かれていた。
おわりに
クレオパトラの死に様は、王として、また女性として、強くも儚いものであった。
彼女の人生を語る際、多くはカエサルとの恋愛関係が取り上げられるが、彼女が本当に愛したのはアントニウスだったのではないだろうか。
黄昏の王朝を引き継ぎ、最期の一瞬まで誇りを捨てなかったクレオパトラは、まさに女王の名にふさわしい人物であった。
また、国家の地盤が緩む原因や政略的な男女関係は、場所や時代が違っても歴史上よく見られる話である。人間は何千年も前から、同じようなことで憂い、苦しみ、そして喜びを感じてきたのかもしれない。
参考文献
『アントニウスとクレオパトラ上下巻』エイドリアン・ゴールズワーシー
『世界史1200人』入澤宣幸























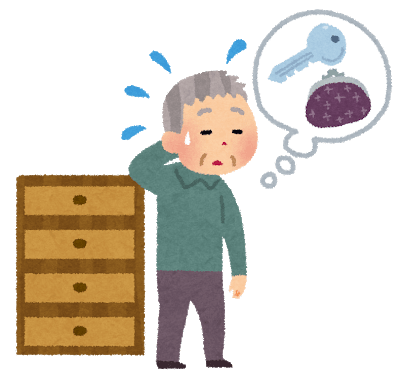

トルコのエフェソス遺跡を訪れた時に、遥か昔にクレオパトラとアントニウスもこの地を訪れていたことを知りました。この時は少し疑心暗鬼でしたが、本当のことだったんですね。