五郎治は始末屋であった。藩の始末をし、家の始末をし、最も苦慮したわしの始末もどうにか果たし、ついにはこのうえ望むべくもない形で、おのれの身の始末もした。
男の始末とは、そういうものでなければならぬ。けっして逃げず、後戻りもせず、能う限りの最善の方法で、すべての始末をつけねばならぬ。(中略)岩井五郎治は最後の武士の一命をもって、千年の武士の時代と刺し違えたのだ。おのが身の始末は、同時におのが世の始末でもあった。(浅田次郎『五郎治殿御始末』より引用)
桑名藩の岩井五郎治という武士は、新政府の命令で、旧藩士のリストラという辛い役目についていた。だが、廃藩置県によって自身も失業してしまった。
すでに戊辰戦争で息子を亡くしている老武士・五郎治は、家財を売り払って家をたたみ、幼い孫を旧知の商人に託した。
浅田次郎氏の短編小説『五郎治殿御始末』には、このように御一新(明治維新)で「失業」した武士の身の始末が書かれている。
江戸から明治へと世の中の価値観が変わる中、武士という生き方に侍たちはどのようにして始末をつけ、時代の垣根を乗り越えたのだろうか。
今回は、激動の世を生きた元幕臣・中條景昭(ちゅうじょうかげあき)を例に紹介する。
武士たちを取り巻く情勢

画像 : ※廃藩置県。wikiより引用
「版籍奉還」、「廃藩置県」により、明治新政府は、幕府や大名が持っていた領地を国家に返納させたが、藩に付随する武士への俸禄はそのままになっていた。
新政府は俸禄を秩禄(※官位や身分などによって支給される俸禄のこと)として払い続けていたが、国家支出の3割にも上っており、明治9(1876)年、秩禄を廃止する代わりに金禄公債を武士に与えた。
金禄公債とは、明治政府が秩禄返上の代償として華族・士族に交付した公債である。
しかし公債の利子は非常に低く、ほとんどの武士は利子だけでは生活できなかった。
新政府での官職を求める武士は多かったが、官職につくことができたのは、全体の16%ほどだった。また公債を売って、古道具屋や団子屋など慣れない商売を始める武士もいたが、ほとんどがうまく行かなかった。
侍の地位が崩壊の一途をたどっていく新しい世の中で、武士たちは自ら生き抜く術を探さなければならない直面に立たされていたのである。
幕臣・中條景昭

画像 : 中條金之助景昭之像
中條金之助景昭(ちゅうじょうきんのすけかげあき)は、文政10年(1827年)、江戸六番町に御小姓組・中條市右衛門景利の子として生まれた。
青年時代に心形刀流、北辰一刀流を習得し、嘉永7年(1854年)より13代将軍・家定に仕えた。
家中の武士たちに武術を指南する剣術・柔術世話心得などを歴任する剣客で、幕府が講武所を開いた際には、剣術教授方に就任している。
慶応3年(1867年)の大政奉還後、景昭は徳川慶喜の身辺警護をする精鋭隊(※後の新番組)の頭に抜擢される。
その後、徳川宗家を継いだ徳川家達や慶喜が駿府(静岡)へ下ることになると、景昭は慶喜に従い駿府へ移住した。
しかし、家達が藩知事になると新番組はその使命を終えて解散となり、景昭ら旧幕臣たちは失業に追い込まれた。
新政府の朝臣となるか、剣を捨てて農民や商人となるか、武士たちは人生の選択という難問に直面したのである。
金谷原(現・静岡県の牧之原台地)の開墾

画像 : 牧之原台地の地形図。wikiより引用】
景昭隊長以下数百名の隊員たちが選んだ道は、「牧之原の開墾」に挑むことだった。
牧之原は水の調達ができない痩せた土地で、地元農民でさえ見放す広大な荒野だった。
景昭の申し出を聞いた勝海舟によると、景昭は
「聞くところによると遠江国の牧之原はギョウカク不毛の土地で、水路に乏しく、民は捨てて顧みざること数百年に及んでいる。若し、我輩にこの地を与えてくださるならば、死を誓って開墾を事とし、力食一生を終ろう」
と述べたという。
明治2年、家達の許可を得た景昭は「金谷原開墾方」として、転住してきた約250戸の元幕臣たちとともに、1,425町歩の開墾を始めることとなった。
新政府が外貨獲得の輸出品に生糸と茶の生産を奨励していたこともあり、景昭らは茶の生産を行うことにしたのである。
苦難の連続
組頭の景昭は、当時42歳。
身分の高い武士から能楽師まで、さまざまな経歴をもった200名あまりを以前の地位身分に関係なく、農耕開拓団として統率していかなければならなかった。開墾作業は熾烈を極め、慣れない農作業と過酷な労働に脱落する者も多かったという。
それでも景昭は必死に仲間をまとめ、励まし、さまざまな取り決めや仕組みをつくり、着々と開拓を進めていった。
明治4年(1871年)、造成した茶園は500ヘクタールに達した。しかし牧之原台地はやせた土地のため木の生育が遅く、わずかな茶芽を初めて収穫できたのは、明治6年(1873年)。開墾から4年も経ってからだった。

イメージ画像 牧之原台地の茶畑
本懐を遂げる
明治7年(1874年)、景昭は明治政府から神奈川県令(知事)就任の誘いを受けたが、「一たん山へ上ったからは、どんなことがあっても山は下りぬ。お茶の木のこやしになるのだ」と一笑に付したという。
明治11年(1878年)には、政府が茶の直輸出に注力していたこともあり、景昭らは「牧之原製茶会社」設立構想を打ち立てた。
残念ながら事業資金の請願は却下され、会社設立の構想は実現しなかったが、社会の動向を見据え、牧之原士族という組織の安定と拡大にまい進する前向きな姿勢がうかがえる。
あらゆる苦難にも負けず、牧之原台地の開墾に一生を捧げた景昭は、明治29年(1896年)、69歳でその生涯を閉じた。
生涯髷を切らず、「最後はお茶のこやしになる」の言葉どおり、牧之原の一番屋敷で息を引きとった。
幕臣から荒野の開墾方へ潔い転身を遂げ、牧之原台地開墾という偉業を成し遂げた中條景昭。
最後まで武士の矜持をもち、本懐を遂げた立派な身の始末だった。
参考文献:『幕末明治剣客剣豪総覧』
関連記事 : なぜ静岡県が「お茶」の名産地になったのか?
























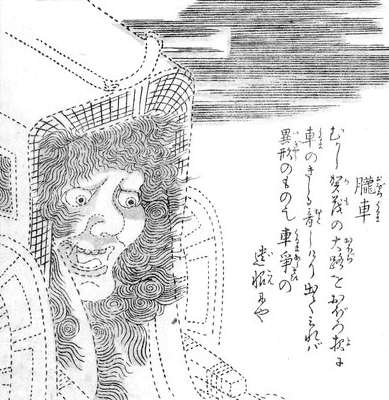
この記事へのコメントはありません。