歴史上「対馬」の名を目にするタイミングとしては、1274年、1281年に起こった二度にわたるモンゴルとの戦「元寇」の話題が多いだろう。
しかしながら、歴史上「対馬」が外国との関わりにおいて重大な局面を迎えたのは元寇だけではない。幕末にロシア帝国軍艦が対馬の一部を占領し、あわや対露戦争の可能性までもが危ぶまれた事件がある。
それが「ロシア軍艦対馬占領事件」、別名「ポサドニック号事件」である。
この記事では、なぜこのロシア軍艦対馬占領事件・ポサドニック号事件が発生したのか、そして幕府はいかにしてこの事件を乗り切ったのかについて解説しよう。
ポサドニック号事件とは?

イメージ画像 : 対馬の景色 photo-ac
ポサドニック号事件とは、軍艦「ポサドニック号」の名に由来する出来事である。
この事件は1861年(文久元年)に起こった出来事であり、当時のロシア帝国海軍中尉、ニコライ・ビリリョフが「ポサドニック号」で突如対馬・尾崎浦に来航し投錨、その後対馬の芋崎に許可なく上陸し、兵舎や工場を建造したり略奪を行ったりした事件である。

画像 : ニコライ・ビリリョフ
この頃は、薩摩藩とイギリスが戦火を交えた「薩英戦争」や、長州藩と列強四国との戦争となった「下関戦争」が1863年に起こるなど、各地で諸外国との間にぎこちない交流と闘争が萌芽してきていた時期でもあった。
なぜポサドニック号は対馬に現れたのか?

画像 : 対馬 public domain
「ロシアの軍艦が日本を訪れる」という話を聞いたら、現代の日本人であれば、おそらく北海道をイメージするだろう。
ペリー提督の来航による開国を契機として結ばれた、日米修好通商条約を含む安政五カ国条約においては、北海道にある函館(箱館)が条約港として開港されていた。
もちろん時のロシア帝国との間にも条約が締結されており、安政5カ国条約のひとつとして数えられる「日露修好通商条約」は安政5年(1858年)7月11日に調印されている。つまり、正規の貿易や外交などにおいては、外国船は条約港を訪れるのが当然である。
ということは、このポサドニック号が正規の目的以外で日本を訪れたというのは自明であった。時のロシア政府は、通年凍結せず使用できる港、「不凍港」を切望していた。その結果として、「南下政策」と言われるように、海が凍ることがない場所に港を設けようとする動きがあったのである。
ロシア艦隊・中国海域艦隊司令官であったイワン・リハチョーフ大佐は、対馬海峡に強引に根拠地を築き、不凍港として利用することを画策した。
ロシア政府は日本との関係悪化を懸念してこの計画を拒絶したものの、海軍大臣コンスタンチン・ニコラエヴィチは、リハチョーフ司令官に対馬への艦隊派遣を指示、この指示に基づき、ニコライ・ビリリョフ中尉らを載せたポサドニック号が突如として対馬近海に現れることとなったのである。
ポサドニック号のロシア兵は対馬で何をしたのか
さて、条約を無視して対馬近海へ突如現れたポサドニック号とロシア兵だったが、彼らが「何をした」のか、という問いに対する答えは、およそ「横行闊歩」や「傍若無人」という表現が当てはまる、まるで条約などなかったかのように行動した、という評価が妥当だろう。
まず、ポサドニック号は尾崎浦(芋崎のやや西方)に投錨し、勝手に測量を始めた。
対馬藩主・宗義和は重臣を派遣し、速やかな退去を求めたが、ビリリョフは船の破損を理由に退去に応じないばかりか、修理工場の設営資材や食料、遊女を対馬藩に要求した。

イメージ画像 : 対馬・浅茅湾
さらにその後、浅茅湾・芋崎へと船を進め、芋崎へ無断で上陸して兵舎、工場、練兵場を建設しはじめたほか、木材や牛馬、食料、薪炭を強奪したり、婦女子をつけ回したりしたという。
対馬の住民は当然激怒し、ロシア軍水兵と衝突した。
藩内は武力による排除と話し合いによる解決とで意見が一致しなかったが、そうしているうちにロシア兵は番所を襲撃して武器を強奪したり、ロシア兵が乗る短艇を制止した対馬の警備兵を拉致して軍艦に連行したりした。これらはロシア軍水兵個々の資質によるものではなく、明らかに艦長の指示であった。
大船越の村に対して、水兵100人あまりもの勢力で押しかけ略奪に及んでいるのは、組織的な行為と見るのが妥当だろう。

画像 : 宗義和の肖像写真 public domain
ビリリョフ艦長は一貫して、藩主・宗義和との面会を要求しており、これは「面会すれば強引に対馬の租借を承諾させられる」とする目論見があったためであった。
それを察した宗義和は、決して自身が面会することなく、食料や薪炭を贈り懐柔を図りつつ、長崎・江戸に使者を派遣し対応の指示を求めたのだった。
事態収拾に奔走した外国奉行・小栗忠順
さて、知らせを受けた長崎奉行・岡部長常は、対馬藩に対して紛争を回避するよう指示したものの、簡単にいえば事態は対馬藩単独どころか、長崎、および周辺の佐賀・筑前・長州藩ら諸侯が集まっても、「お手上げ」の状態であった。
そこで幕府は、箱館に駐留しているロシア総領事ヨシフ・ゴシケーヴィチにポサドニック号退去を要求したうえで、外国奉行・小栗忠順を対馬に派遣した。

画像 : 外国奉行・小栗忠順
小栗がビリリョフと会見すると、ビリリョフは第一声から藩主との面会を強く要求したという。
小栗は一度は藩主との面会を受け入れる旨を回答してしまうが、老中・安藤信正の指示により、藩主との面会は認めないと前言を翻した。
これは、藩主と面会させれば対馬への居留を認めることになるという理屈からである。(※外国船が対馬にいること自体が条約上あってはならず、故にその外国船艦長と藩主が公式に面会するなどあり得ない、ということであろう。)
前言を翻した小栗に対し、ビリリョフは激昂し猛抗議したものの、小栗は「私を射殺しても構わない」と薄氷を踏むやりとりを乗り越え、幕府・老中に対して「対馬を直轄領とし、正式の外交形式で交渉を行うこと」を提案した。
しかしこの提案は却下され、逆に小栗は外国奉行を辞任することとなってしまった。
現代の感覚で言えば、小栗の要請は「不法移民が発生している対馬を国有地とし、国際問題化すること、すなわち国際世論を味方に付けるしかない」という旨の提案であり、理に適っているとも思える。
しかし、老中の判断もあながち不合理とまでは言えなかった。というのも当時の日本は未だ諸外国と平等な扱いではなく、国際紛争の場においても発言力があるとは言えなかったためである。
国際問題化することで、かえってロシア以外の外国勢力の悪意ある介入を招く可能性が否定できなかった以上、老中としてこの提案には慎重にならざるを得なかったのだろう。
イギリスの介入と思惑
小栗が外国奉行を辞任してしまい、交渉に行き詰まった対馬藩は、とうとう藩主自身がビリリョフと面会し交渉せざるを得なくなった。
ビリリョフは芋崎の永久租借を要求し、対馬藩ではこれに対して幕府と直接交渉するよう回答を回避した形だったが、強引に芋崎が租借されるか、あるいは実効支配されるかは時間の問題であったといえよう。
このような対馬の危機に、日露双方にとって予想外の横槍が入った。
それがイギリスであった。
藩主面会のおよそ2ヶ月後、イギリス公使ラザフォード・オールコックと、イギリス海軍中将ジェームズ・ホープは、イギリス艦隊の圧力によってロシア軍を退去させる案を老中に提案した。

画像 : イギリス公使 ラザフォード・オールコック public domain
この提案は受け入れられ、イギリス東洋艦隊の軍艦「エンカウンター(蒸気コルベット)」と「リンドープ(砲艦)」が示威行動を行ったうえで、ロシア側に厳重抗議した。
ロシア領事ゴシケーヴィチは、ビリリョフの行動に対する幕府からの抗議を黙殺していたものの、イギリスの干渉が加わったことで形勢不利と判断、およそ1ヶ月というハイスピードで、ポサドニック号の退去は実現された。
当時の幕府や対馬藩にとっては「イギリスさまさま」だったろうが、これにもウラがある。
イギリス公使オールコックはこのとき、ロシアと同様にイギリスによる対馬占領を本国に提案していたほか、当時の日本における幕府権力の低下に強い関心を寄せていたとされる。
ただし、オールコックが日本という国を(損得抜きに)どのように見ていたかといえば、彼の手記や行動にその片鱗が現れている。
「平和で、実り豊かに満ち足りており、丁寧かつ完璧に耕され維持された農地と、装飾的な木々に溢れたこの国はイングランドでも敵わない」
また、幕府の遣欧使節団の派遣を強力にサポートしたりしているほか、オールコックは外国人として初めて富士登山で登頂を果たすなど、日本という国に強い関心があったことがうかがえる。
本国の指示を受け日本という国をいかにイギリスの利益に資させるかという、職業人としての彼の行動はクレバーであったが、彼自身はむしろ日本や日本人に対し、西欧と交わることにより日本人自身にも大きなメリットがあるという、強い信条に基づく行動を取っていたようにも見えるのである。
おわりに
条約を無視して突如として軍艦を派遣してきたロシアに対して、当時の幕府は独力によって事態を収拾することができなかった。
しかしそれも無理からぬことで、当時の日本はすでに日本人だけが意識する領域ではなく世界の中の日本であり、列強諸国から見れば、未だどの国も直接は手を下していない、「空白地」のひとつだったのである。
ポサドニック号事件は視点を変えれば、他国に先駆けて日本の領域の一部を入手しようとしたロシアに対して、イギリスが異を唱えた事件であり、簡単にいえば当事者であるはずの日本・幕府はそもそも、両国にとっては重要な存在ではなかったのである。
この後、日本は戊辰戦争を経て幕府が倒れ、明治の新体制へと移行することになるが、その戊辰戦争すらも外国の力と無関係ではいられなかった。
関連記事 : 戊辰戦争の裏側では何が起きていたのか?「列強の狭間で植民地化を避けた日本」
https://kusanomido.com/study/history/japan/bakumatu/51597/
「ポサドニック号事件」は、「日本を舞台とした日本の歴史」であると同時に、「世界史の中の日本”での”できごと」でもあり、日本の土地がグローバルな闘争の舞台となった重要な事件のひとつだったのだ。










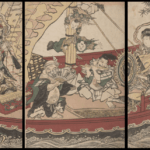









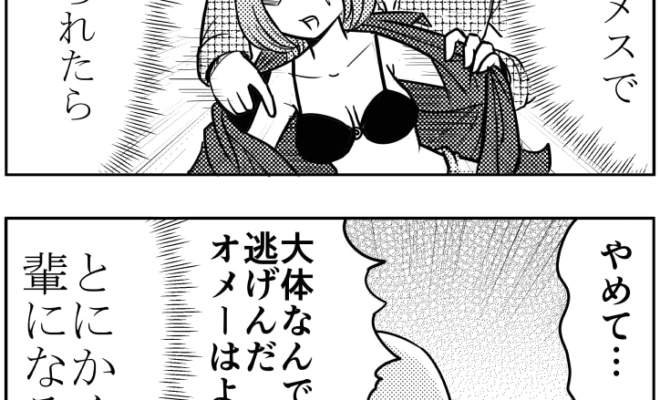



昔から露助は碌な事しない野蛮な奴等という歴史の紹介だな