
「いざ鎌倉」という言葉がある。
「小学館 全文全訳古語辞典」によると、この言葉の意味は
「さあ、一大事が起こった。自分はそれに積極的に対応しなければならない」
という事態をさすことば、であり、
「鎌倉幕府に忠誠を尽くす武士は、国家的大事件があればすぐに鎌倉へ駆け付ける義務を有したことによる」
とのことだ。
今回はこの「いざ鎌倉」という言葉について調べてみた。
1.「いざ鎌倉」という言葉の由来となった話
この「いざ鎌倉」という言葉の由来となったエピソードがある。
江戸時代に井沢蟠竜(いざわばんりょう※神道家)によって書かれた啓蒙の書「広益俗説弁」にはこのようにまとめられている。
最明寺時頼入道、諸国をめぐり、上野(かうづけ)国佐野にいたり、雪にあひてある家に宿す。
主、まづしくて薪なき故、鉢の木をきり、たきてあたためぬ。
時頼、感じて其名を尋ねしかば、
「佐野源左衛門常世(つねよ)なり。一族に所領をおしとられ、かやうの体になり候ひぬ。しかれども、もし明日にも乱出来ば、ちぎれたる鎧を着、さびたる長刀を持ち、痩せたる馬に乗りながら、一番にはせ参り着到(ちやくたう)につき、高名をきはめ候はん」
などかたる。
鎌倉幕府の執権であった北条時頼が、諸国を巡った際に、佐野源左衛門常世(さのげんざえもんつねよ)という者が、大切にしていた鉢の木を切り、燃やして時頼をもてなしたという話だ。その際に常世は
「今は落ちぶれているが、乱が起こるようなことがあれば、真っ先に鎌倉にかけつける所存だ」
との旨を述べる。
かくて最明寺いとまをこひ、鎌倉に帰り、にはかに軍勢を催すに、程なく集まること、雲霞のごとし。
最明寺、二階堂何某に告げて、諸軍勢の中に、ちぎれたる鎧を着、さびたる長刀を持ち、痩せたる馬に乗りたる武者一人あるべし、とてよび出さしむるに、兼ねていひしにたがはず常世(つねよ)なりしかば、時頼大いに感悦し、
「われこそ汝がもとにやどりし修行者なり。かやうに諸勢をあつむること、他の儀にあらず。汝が佐野にていひしことばの真偽(まこといつはり)をしらんがためなり。
然るに、少しもことばをたがへず馳せ参ること神妙なり。汝が本領佐野庄七百余町、もとのごとくかへしあたふるなり。又、大雪にあひてさむかりしに、秘蔵の鉢の木をきり、火に焼ひてあてしこと、其こころざしわすれがたし。其時の鉢の木は梅・桜・松なりしかば、返報に、加賀に梅田、越中に桜井、上野に松枝、三ヶ庄領ずべき」
よし、自筆の状、安堵に添へてあたへしかば、常世(つねよ)、頂戴して国にかへれば諸軍勢も各々国に帰りける。
その後、鎌倉に帰った時頼は、にわかに軍勢を招集する。
言葉の通りに「いざ鎌倉」へと馳せ参じた常世を讃えて、時頼はあの時の鉢の木の返報として、所領を与えたということである。
そう、時頼が軍勢を集めたのは、常世の言葉が真実であるかどうかを試すためだったのだ。
2.「鉢の木」のエピソードの矛盾
なかなか感動的なエピソードであるが、井沢蟠竜はこれを「俗説である」と述べて、「此説、理にあたらず」と否定する。
その理由として「史記」に書かれた故事を引用しながら、このように述べている。
昔、周の幽王、褒姒(ほうじ)を愛す。褒姒笑ふことなし。幽王、笑はせんことを思ひてさまざまにすれども、笑はず。幽王かつて、冦(あだ)いたることあれば烽火をあげて兵をあつむる法を定め置きたり。
あるとき、他国より冦いたりしかば、烽火をあげて兵をあつむ。褒姒、此烽火を見て大いに笑ふ。
幽王よろこびて、また笑はせんことを思ひ、事なきに烽火をあぐるに、諸候ことごとくいたれども、冦なし。褒姒が笑ひのためと聞きてかへりぬ。其後、西夷・犬戎(けんじゅ)おこりて幽王をせむ。
幽王、烽火をあげて兵をもよふしけれども、前のごとく褒姒がなぐさみよと思ひて来たらず。
ついに幽王、驪山(りざん)の下(もと)にころさる、と「史記」に見えたり。これをもって比するに、時頼が軍勢を集めしも、其こころ相にたり。かさねて乱ありて勢を催すとも、また常世のたぐひの者をゑらばん為ならんとて、来るべからず。
時頼、蒙昧なりといふとも、かくのごときにはいたらじ。わきまへしるべし。
周の幽王は、褒姒(ほうじ)という女性を愛して、その女性を喜ばせるために、敵に攻められてもいないのに烽火(「のろし」のこと)をあげて兵を招集した。
その結果、本当に敵が攻めてきた時に、どうせ嘘だろうと思い、兵は駆けつけてくれず、幽王は殺されてしまった、という故事だ。
井沢蟠竜は
「もし本当に、時頼が常世の忠誠心を試す目的のためだけに、非常時でもないのに軍勢を招集したなら、本当にいざ鎌倉に危機が迫った時に、兵が駆けつけてくれることは無くなってしまう。そんなことをするほど時頼も愚ではないはずなので、このエピソードは嘘だろう。」
との旨を述べる。
イソップ寓話の
「狼が出たと言っては大人をだましていた少年が本当に狼が出た時には誰にも信用されなかった」
という話にも通じる論であり、井沢蟠竜が言うのも、もっともである。
3.謡曲「鉢の木」
井沢蟠竜が「俗説である」と片付けたこのエピソードは、実は謡曲「鉢の木」に由来するエピソードである。

ここにその一部を引用する。
シテ「夜の更くるについて次第に寒くなり候。何をがな火に焚いてあて参らせ候ふべきや。思ひ出したる事の候。鉢の木を持ちて候(と作物を見)。これを切り火に焚いてあて申し候ふべし。
ワキ「げにげに鉢の木の候ふよ。
シテ「さん候某世にありし時は。鉢の木に好き数多木を集め持ちて候ひしを。かやうの体に罷りなり。いやいや木好きも無用と存じ。皆人に参らせて候さりながら。今も梅桜松を持ちて候。あの雪もちたる木にて候(と作物を見)。某が秘蔵にて候へども。今夜のおもてなしに。これを火に焚きあて申さうずるにて候。
まさに鉢の木を薪にしようとする場面である。
そして鎌倉に呼び寄せた常世らに時頼が語る言葉も参照しよう。
ワキ(シテに向ひ)「やあいかににあれなるは佐野の源左衛門の尉常世か。これこそいつぞやの大雪に宿かりし修行者よ。見忘れてあるか。(シテワキを見てたらたらと退り辞儀す)いで汝佐野にて申せしよな。今にてもあれ鎌倉に御大事あるならば。ちぎれたりとも其具足取つて投げかけ。錆びたりとも其長刀を持ち。痩せたりともあの馬に乗り。一番に馳せ参るべきよし申しつる。言葉の末を違へずして。参りたるこそ神妙なれ。まづまづ今度の勢づかひ。全く余の義にあらず。常世が言葉の末。真か偽りか知らん為なり。又当参の人々も。訴訟あらば申すべし。理非によつて其沙汰いたすべき所なり。先々沙汰の始めには。常世が本領佐野の庄。三十余郷かへし与ふる所なり。」
謡曲「鉢の木」では時頼は単に、「常世を試す」ということだけではなく、馳せ参じた他の武士達にも
「訴訟があるなら申すがよい、理非によって沙汰しよう」
と述べている。
井沢蟠竜のまとめでは、それが欠落していた。まとめ記事だけを鵜呑みにしてはならないのはいつの世も同じことである。
もし時頼が
「御家人たちの領地は、鎌倉幕府が法的にしっかり守ってやるぞ、この常世のケースのようにな」
という意図で御家人を鎌倉に招集したというなら、まだいくらかまともな話になる。
ちなみに北条時頼が、裁判制度を確立し、御家人の保護につとめたこと自体は事実である。
承久の乱の後、時頼の祖父に当たる執権北条泰時は、有力な御家人や政務にすぐれた人々を「評定衆(ひょうじょうしゅう)」として選び、政務の管理や裁判に当たらせていた。
時頼は評定衆の会議である評定のもとに新たに「引付(ひきつけ)」をおいて、「引付衆(ひきつけしゅう)」を任命し、御家人たちの所領についての訴訟を専門に担当させて迅速で公正な裁判を行おうとしたのであった。
ここに引用した謡曲「鉢の木」のエピソードは、あくまで能の脚本であり、世阿弥が創作したものである。(観阿弥作という説もある。)
だが、歴史的事実そのままではないにせよ、この逸話は、時頼の行った政策のある一面を正しく表現しているものであるとも言える。
一方で、佐野源左衛門常世が、自分の所領を安堵してくれる幕府に対して忠誠を誓う姿もまた、「御恩と奉公」で形成される封建制度のある一面を描いたものとなっている。
ここに描かれた時頼の「御家人の所領保護の姿勢」や、常世の「鎌倉幕府への忠誠」がある種の真実に迫っているとするならば、残されたひとつの論点が浮上することとなる。
それは
「時頼が諸国を行脚したのは本当なのか」
ということである。
4.「増鏡」「太平記」の記述
水戸黄門よろしく時頼が諸国を行脚したという記録は、歴史物語「増鏡」、軍記物語「太平記」に存在する。
まずは「増鏡」の記述を見てみよう。
時頼の朝臣は、康元元年に頭おろして後、忍びて諸国を修行し歩きけり。
それも国々の有様、人の愁へなど、くはしくあなぐり見聞かんの謀にて有りける。
あやしの宿りに立ち寄りては、其の家主が有様を問ひ聞き、理ある愁へなどの埋もれたるを聞きひらきては、
「われはあやしき身なれど、昔、よろしき主を、持ち奉りし、未だ世にやおはすると、消息奉らん。もてまうでて聞こえ給へ」
など言へば、「なでう事無き修行者の、何ばかりかは」とは思ひながら、言ひ合はせて、其の文を持ちて東へ行きて、しかじかと教へしままに言ひて見れば、入道殿の御消息なりけり。
「あなかまあなかま」とて、ながく愁へ無きやうに、はからひつ。仏神などの現はれ給へるかとて、皆額をつきて悦びけり。かやうの事、すべて数知らず有りし程に、国々も心遣をのみしけり。最明寺の入道とぞ言ひける。(「増鏡」巻十一「草まくら」より)
これによれば出家後の時頼は、お忍びで諸国を修行して歩き、人々の愁いの声を詳しく聞き、理に照らしてもっともだと思う事例があれば、書状を書いてあれこれと、とりはからってやっていたということだ。
また「太平記」にもこのような記事がある。
「なほも遠国の守護・国司・地頭・御家人、如何なる無道猛悪の者有りてか、人の所領を押領し人民百姓を悩ますらん。みづから諸国を順て、是を聞かずは叶ふまじ」とて、西明寺の時頼禅門、ひそかにかたちをやつして六十余州を修行し給ふに、ある時摂津国難波の浦に行き至りぬ。(「太平記」巻三十五より)
諸国の守護・国司・地頭・御家人で、極悪なふるまいをして人の所領を奪い、人民を苦しめている者がいるだろう。
その調査のために、身をやつして旅立った時頼は難波の浦に辿り着く。この地で時頼は地頭によって先祖代々の土地を奪われた老尼の話を聞く。
その後時頼は、鎌倉に帰ってから、
押領せし地頭が所帯を没収して、尼公が本領の上に添へてぞ是をたびたりける。
(土地を奪った地頭の財産を没収して、尼のもともとの所領に加えてこれを尼にお与えになった。)
ということである。また時頼の孫である貞時も先例にしたがって同じく諸国を修行して歩いたとも「太平記」は述べている。
おそらく、このような言い伝えをもとにして世阿弥の謡曲「鉢の木」は着想されたものであろう。
そして、この「増鏡」や「太平記」に残っている「時頼の廻国伝説」が、歴史的事実かどうかについては、現代においても様々な学説が論じられている。

※『徒然草』の時頼と大仏宣時/江戸時代『前賢故実』より。画:菊池容斎
5.「北条時頼の廻国伝説」についての諸学説
豊田武の学説
豊田武(※歴史学者)はその著書「英雄と伝説」(塙新書)の中で、時頼の廻国伝説が関東のみならず関西、九州、東北にも伝承されていることを取り上げて
「たしかに時頼が二、三の地方をまわったことはありうる」
と述べた上で、なぜこのような廻国伝説が各地に広がったかについては
「この伝説が北条氏の執権政治を謳歌する立場から作られた」
としている。さらに豊田武は
「時頼が三浦氏をほろぼしてその所領を没収し、これを得宗領(北条氏直轄地)とした。こうしたところから、得宗領に北条時頼の廻国伝説がうまれたのではないか」
と推定する。また
「各地に伝わる廻国伝説には、時頼が得宗領(北条氏直轄地)の拡大をはかったときにおこったものが多く、そこには多く時頼に関する寺院があり、ときに時頼の木像が安置されている」
という点を指摘し、
「得宗領を手がかりとしてこの廻国伝説を考え、廻国伝説を手がかりとして得宗領の問題を深く考えたいと思っている。」
と述べている。
佐々木馨の学説
この豊田武の論を継承し、さらに発展させたのが佐々木馨による「執権時頼と廻国伝説」(吉川弘文館)である。
同書において佐々木は、はっきりと
「時頼の廻国は史実である」
と断言し、その根拠に「廻国を裏付ける二つの史料」として「『鎌倉遺文』の平政連の諌草」と「青森県弘前市の長勝寺の梵鐘」をあげる。
まず「『鎌倉遺文』の平政連の諌草」において、時頼の孫である貞時が
「都と地方に大事を行じしめた」
と述べられていることにふれ、
「大事=廻国」と推定する。
また「長勝寺(当時は護国寺という名称)の梵鐘」の銘文に「崇演=貞時」の名があることを指摘し、ここから
「長勝寺に現存する梵鐘は、紛れもなく、時頼とその護持僧道隆との法交によって営まれた護国寺に遡源するものである。そして、この延長線上に孫貞時が嘉元四年(1306年)護国寺の梵鐘を鋳造し、併せて銘文も刻んだのである」
としている。
石井進の学説
だがこの佐々木の論に対して、石井進から「日本歴史」600号掲載の「新たな北条時頼廻国伝説の提起に思う」という論文において鋭い批判がなされている。
石井は佐々木のあげた二つの史料に対して指摘する。
まず第一の史料である「『鎌倉遺文』の平政連の諌草」について、
「私にはどうもそのように(大事=廻国)には理解できない。あまりにも深読みにすぎる解釈と思われる。」
とし、「太平記」に
「貞時が祖父時頼の先例を追って諸国を修行した」とあるからといって、
「貞時の廻国が時頼のそれの証明になるとするには飛躍に飛躍を重ねる論法ではなかろうか」
と述べている。
また第二の史料である「長勝寺の梵鐘」についても
「推測に推測を重ねた解釈で、とても時頼廻国を裏付ける史料になるとは思われない」
と述べている。
6.まとめ
以上、「いざ鎌倉」という言葉を、様々な史料から検証してみた。
「小学館 全文全訳古語辞典」は「いざ鎌倉」という語を
「鎌倉幕府に忠誠を尽くす武士は、国家的大事件があればすぐに鎌倉へ駆け付ける『義務』を有したことによる」
と述べる。
だが、貴族である私・武蔵大納言はこう考える。
人々が
「さあ、一大事が起こった。自分はそれに積極的に対応しなければならない」
という気持ちを起こすためには、その前提として「為政者による善政」が無ければならないのだ。
むしろ義務を負っているのは我々、為政者側ではないのか。
私も、もし生まれた時代に戻れて、大納言としての職に復帰できた際には、諸国を行脚して、弱き民の声に耳を傾け、立派な政治家となりたい。
そして「武蔵大納言諸国漫遊記」を記して、後世に平安時代の庶民の暮らしぶりを伝えたいとも願っている。
スポンサーリンク








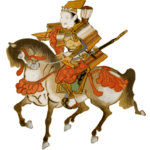

















この記事へのコメントはありません。