
画像:ベッドに座りピエール・サーモンを迎えるシャルル6世 public domain
中世から近世にかけてのヨーロッパ。
豪華な王宮の奥では、現代では信じがたい奇妙な妄想に囚われた人々がいました。
「自分の身体がガラスでできている」と信じ、わずかな衝撃や接触で砕け散ってしまうのではないかと、怯えて暮らしていたのです。
この症状は後に「ガラス妄想(glass delusion)」と呼ばれるようになり、15世紀から17世紀にかけて、一部の王族や知識人の間で報告されました。
壊れやすさや透明さといったガラスのイメージは、精神的重圧や社会不安と結びつき、当時の王侯貴族たちの心を大きく揺さぶっていたのです。
今回は「ガラス妄想」の具体例と、その背景にある文化や心理、文学・哲学への影響、そして現代精神医学との関わりを紹介します。
ガラスに閉じ込められた王、シャルル6世の苦悩

画像:戴冠式の衣装をまとったシャルル6世 public domain
最も有名な「ガラスの王」は、フランス・ヴァロワ朝第4代国王、シャルル6世(1368–1422年)です。
彼は即位当初こそ「親愛王」と称えられましたが、1392年、ブルターニュ遠征の途上で突如錯乱をきたします。
行軍中に槍が地面に落ちて大きな音を立てたことを「裏切りの合図」と誤解し、自軍の騎士たちを敵とみなして襲撃。複数人が死亡する惨事となりました。
この事件をきっかけに、シャルル6世は生涯にわたり精神発作を繰り返すことになります。
とりわけ注目されるのが、彼が「自分の身体はガラスでできている」と信じるようになったことです。
人に触れられることを極端に恐れ、転倒や接触で“砕ける”ことを避けるため、鉄の骨組みを縫い込んだ衣服を着用していたと記録されています。
この様子については、後に教皇となるピウス2世が「王は鉄骨入りの服を着て、触れられることを避けていた」と回想しています。
この妄想は単なる奇行ではなく、王権の重圧や孤独、そして精神医学がまだ未発達だった時代における深刻な病の表れといえるでしょう。
シャルル6世の治世下、フランスは内戦と百年戦争の混乱に巻き込まれ、王の「脆さ」はそのまま王国の不安定さと重なっていました。
なぜ人はガラスになったのか
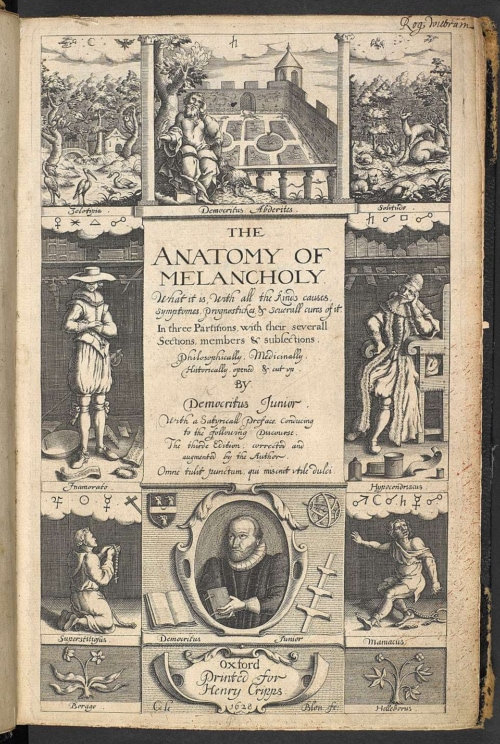
画像:『憂鬱の解剖学』1628年第3版の扉絵 public domain
それではなぜ「自分の身体がガラスでできている」という妄想が広がったのでしょうか。
これは、当時の人々がガラスという素材に抱いていた特別な感覚と深く関係しています。
16〜17世紀のヨーロッパでは、ガラスは高級で神秘的な素材と見なされていました。
透明性や脆さ、美しさ、そして高度な加工技術によって生み出されるその特性から、ガラスは特別な物質として貴族階級に珍重されていたのです。
特に、イタリア・ムラーノ島で生産されたヴェネツィア・グラスは、その象徴的存在でした。
このような背景から、「自分の身体がガラスである」という妄想は、ガラスという素材への畏敬と不安が精神に投影された結果と考えられます。
1621年、イングランドの学者ロバート・バートンは著書『憂鬱の解剖学』で、ガラス妄想を「メランコリー(憂鬱症)」の一症状として紹介し、極度の不安や恐怖がこの妄想を引き起こすと分析しました。
つまり「ガラス妄想」は単なる奇異な症状ではなく、ガラスの壊れやすさや透明さ、美しさと脆さという二面性が、精神疾患と当時の文化観が交わる中で生まれた現象だといえるのです。
文学と哲学に映るガラスの影
この妄想は、医学の領域にとどまらず、文学や哲学にも深い痕跡を残しています。
最も有名な文学的作品は、『ドン・キホーテ』の作者としても知られるスペインの文豪ミゲル・デ・セルバンテスによる短編『ガラスの学士』(1613年)です。
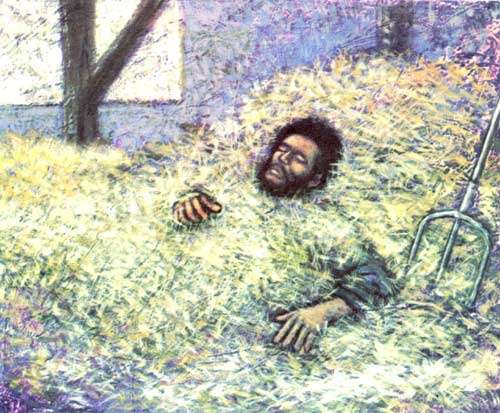
画像 : 『ガラスの学士(El licenciado Vidriera)』 作画:Rosmairy(Trabajo propio)CC BY-SA 4.0
物語の主人公トマス・ロダーハは、媚薬と信じて飲んだ毒によって重い病にかかり、6か月の寝たきり生活を経て精神を病みます。
やがて「自分の身体がガラスでできている」と信じ込み、人に触れられることを極端に恐れ、座ることさえできなくなります。
それでも彼は町を歩きながら鋭い風刺を口にし、知性と狂気の境界に立つ人物として描かれました。
その後2年を経て、奇跡を起こすと噂される僧によって回復する結末となっています。
また、オランダの詩人コンスタンティン・ホイヘンスは、1622年の詩『高価な愚行』で、自分の身体がガラスでできていると信じる男が、椅子に座ることも眠ることも恐れる様子を描きました。
彼はこの狂気を風刺する一方で、人間の存在不安や死への恐怖をも浮き彫りにしています。
哲学の領域でも、ルネ・デカルトが『第一哲学についての省察』(1641年)の中で「自らをガラスと信じる狂人」に触れ、知覚と現実の関係を問い直す材料として、この妄想を引用しています。
17世紀後半には、ジョン・ロックも『人間悟性論』(1690年)で、ガラス妄想を「狂気のモデル」の一例として挙げ、心と認識の関係を考察する手がかりとしました。
妄想の終焉と現代への残響
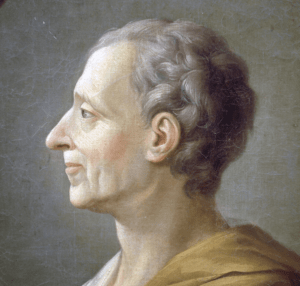
画像:合理的で科学的な態度を進めた啓蒙思想家の一人シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー public domain
18世紀以降、啓蒙主義の広まりとともに精神医療が体系化されると、ガラス妄想の記録は次第に減少していきました。
フランス革命や産業革命を経て、人間観が「魂と身体」から「心理と脳」へと移行し、同時にガラスという素材の象徴性も変化したのです。
かつて神秘性と脆さを兼ね備えた特別な物質だったガラスは、やがて日常生活で一般的に使われる工業素材となり、妄想の投影先としての意味を失っていきました。
しかし「ガラス妄想」が完全に消えたわけではありません。
現代でも稀に症例が報告されており、2015年にはオランダ・ライデンで「自分の体がガラスでできている」と信じる男性患者が確認されています。
また、現代社会ではガラスの代わりに、テクノロジーや監視への恐怖が新たな妄想の対象となりました。
たとえば「脳にチップを埋め込まれている」という陰謀的な妄想は、かつてのガラス妄想に通じる心理的構造を持っていると考えられます。
ガラス妄想は、一見すると突飛で病的な幻覚のように見えます。
しかし歴史の中で、この妄想は王たちの孤独や時代の不安を映し出し、美と脆さの象徴となり、さらには哲学的懐疑の題材にまでなりました。
セルバンテスやホイヘンス、デカルトが描いたガラスの人間は、時代を超えて、繊細で壊れやすい心を抱えながら社会に生きる、私たち自身の姿をも映しているのかもしれません。
参考文献:
『A Body of Glass:The Case of El licenciado Vidriera,Elena Fabietti』
『思わず絶望する!? 知れば知るほど怖い西洋史の裏側』他
文 / 草の実堂編集部



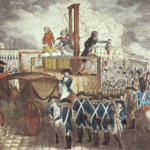






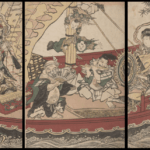









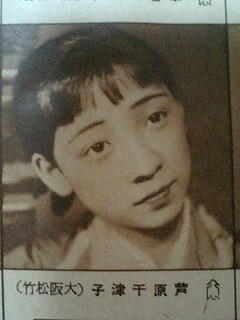



この記事へのコメントはありません。