
『江戸の蕎麦っ食い』
なんとも粋な感じの言葉である。
落語「そば清」のなかで「そばっ食いの清兵衛」、略して「そば清」という男が登場するが、江戸時代において蕎麦は町人から将軍家まで広く浸透した国民食だった。
では、その時代の中心であった江戸の蕎麦事情はどのようなものだったのか?
蕎麦の変遷とともに調べてみた。
江戸の名物はうどん?!
やはり蕎麦には「食う」というより「手繰る(たぐる)」という動詞が似合う。手元へ引き寄せるといった意味だが、蕎麦の場合は口元へ引き寄せるといったところか。
しかし、江戸時代の初期まで、町人は蕎麦を手繰ることができなかった。麺状の蕎麦が食べられるようになったのは、室町から江戸時代の初期といわれているからだ。それまでは、蕎麦粉を蕎麦掻き(そばがき)として食べていたのである。

※蕎麦掻き
蕎麦掻きこそ、日本で古来から食べられてきた食べ方であり、蕎麦粉を熱湯でこねて餅状にした食べ物である。
蕎麦料理そのものは縄文時代から食べられていたが、蕎麦がきは鎌倉時代には存在し、石臼(いしうす)の普及とともに広がったと見られる。餅状の蕎麦を箸でちぎっては、汁につけて食べていた。
(日本での蕎麦の歴史は「蕎麦(そば)の歴史について調べてみた」にて読むことができる)
蕎麦といわれてイメージする麺状の蕎麦は「蕎麦きり」と呼ばれるが、蕎麦を手繰るにはこの蕎麦きりが登場するまで出来なかったのである。
さらに麺といえば、江戸時代の前半までは蕎麦よりうどんが主流だったこともある。蕎麦も食べられてはいたが、あくまでうどん屋がうどんを売る傍ら、蕎麦も売っている程度の扱いだった。
二八蕎麦

江戸時代の後期には、蕎麦粉と小麦粉を混ぜた蕎麦が広く出回り、現在のように茹でる蕎麦が主流となった。
耳にする機会も多いが「二八蕎麦(にはちそば)」である。蕎麦粉8:小麦粉2で打った蕎麦のことで、名称の由来は粉の割合であるという説や、値段が16文(約320円)であったことから2×8=16の符丁からきたという説がある。
対して十割蕎麦は、蕎麦粉を糊化させたものをつなぎとして、蕎麦粉だけで使った蕎麦のことを指す。二八蕎麦よりも切れやすく、蒸籠に乗せて蒸し、そのまま客に供する形の蕎麦が主流だった。現在も「盛りそば」を「せいろそば」と呼ぶのはその名残である。
しかし、二八うどんという言葉もあったことなどから、蕎麦きりが普及しても蕎麦そのものがうどんを上回るにはまだ時間が必要であった。
蕎麦の普及

※深大寺
江戸の町において蕎麦がうどんより食べられるようになったのは、18世紀中頃からだといわれている。「江戸八百八町(はっぴゃくやちょう)に蕎麦屋は数え切れないくらいあるが、うどん屋は万に一」といわれるほどになった。
明治8年に北尾重政により出版された「絵本三家栄種(えほんさかえぐさ)」のなかには、江戸の葺屋(ふきや)町にあった福山そばの店先が描かれており、蕎麦猪口を片手に蕎麦を手繰る男が鮮明に描かれている。
この時代、調布の深大寺では、土地が米の生産に向かないために小作人は蕎麦を作り、米の代りに蕎麦粉を寺に納めたのを起源として、参道に蕎麦を振舞う店が立ち並ぶようになった。やがて、深大寺蕎麦の人気が高まり「献上蕎麦」と呼ばれるまでになる。
一説には徳川第3代将軍家光が、鷹狩りの際に深大寺に立ち寄って、蕎麦を食べほめたからだともいわれている。
江戸の三大蕎麦

※神田やぶそば
江戸も中後期になると、町には数え切れないほどの蕎麦屋があったが、そのなかでも代々続いている「老舗御三家」、俗にいう「江戸の三大蕎麦」は現在も人気だ。
「藪(やぶ)」「更科(さらしな)」「砂場(すなば)」が三大蕎麦の系譜である。
「藪蕎麦」の由来は、諸説あるが雑司ヶ谷近くに藪があり、その中の農家で食べさせてくれる蕎麦がうまいと評判で、雑司ヶ谷の名物になり、藪蕎麦と呼ばれるようになったというのが有力だ。1750年ぐらいには美味しい蕎麦の代名詞になっていた。
特に「かんだやぶそば」は、2013年(平成25年)2月19日 夜間に発生した火災により、取り壊しになるも2014年(平成26年)10月20日には新築の店舗で営業を再開。オープン直後には待ちわびた「蕎麦っ食い」が連日並んだ。
「更科」は、蕎麦の産地である信州更級から1字を頂きお店を出した麻布に屋敷を構えていた保科家から1字を頂き「信州更科蕎麦処 布屋太兵衛」の看板を掲げたのが最初である。
「砂場」の由来は、大坂城築城に際しての資材置き場のひとつ「砂場」によるものとされる。大阪が発祥のはずだが江戸に進出して江戸で発展していった。
それぞれが暖簾分けをしており、直系が絶えた店もあるが、「暖簾御三家」とも呼ばれて今でも親しまれている。
蕎麦の食べ方

『鬼平犯科帳』『剣客商売』などの著者である池波正太郎は、根っからの江戸っ子である。また食通でもあり、蕎麦についても彼なりの流儀があった。池波は著書「男の作法」のなかで、こう述べている。
『そばを口に入れてクチャクチャかんでいるのはよくねえな。東京のそばでね。かむのはいいけど、クチャクチャかまないでさ、二口三口でかんで、それでのどに入れちゃわなきゃ。クチャクチャかんでたら、事実うまくねえんだよ』
彼が言いたいのは、蕎麦も喉腰を楽しむこと、いつまでも口の中に入っているのはみっともない、といったところだ。つまり、二口三口で噛んで、飲み込めるくらいの量が程よいということである。
さらに、
『そばのつゆにしても、ちょっと先だけつけてスーッとやるのが本当だと言うけど、これだって一概には言えないんだ。つゆが薄い場合はどっぷりつけていいんだよ。ちょっとつけるというのは、どっぷりつけたら辛くて食べられないからちょっとつける。たとえば東京の「藪」のそばなんかは、おつゆが濃いわけだから、全部つけられないわけだよ。だから先にちょっとつけてスーッと吸い込むと、口の中でまざり合ってちょうどよくなるわけ』
というくだりもあるが、江戸っ子からすると蕎麦をどっぷりつけて食べるのは粋ではない。だが店によって食べ方も違ってくるというわけだ。
このように江戸の町人によって、蕎麦の食べ方も決まっていったのである。たかが蕎麦なれど、食べ方まで決まっているというのは粋じゃあないか。
最後に
江戸時代の蕎麦がかなり時間をかけて人々に浸透したのだとわかった。その後は、池波のように「蕎麦が茹で上がるまでに酒を飲む」という習慣ができた。
今でも蕎麦屋には「抜き」だの「板わさ」「天たね」などがあるのは、酒とともに楽しむ文化が定着した証だ。


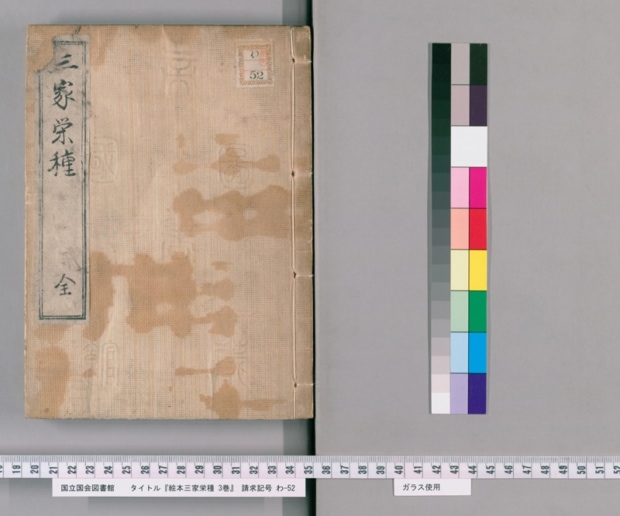









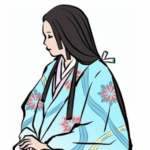













この記事へのコメントはありません。