
画像:池波正太郎。婦人生活社『婦人生活』3月号(1961年)より wiki.c
京都を愛した文人は数多く、京都を舞台とした名作も多く誕生した。そうした作品の中には、文人の視点を通して、いきいきと京都の情景や味覚が描かれている。
名所旧跡が多い京都だが、文人たちが残した足跡と、その作品の中に登場する情景や味覚を訪ねて周るのは、またひと味違った旅の醍醐味を味わえる。名作を手に、京都を訪ねてみてはいかがだろう。
今回は、『鬼拝犯科帳』『剣客商売』『真田太平記』など、江戸・戦国を舞台とした時代小説を残した池波正太郎の愛した京都を紹介しよう。
京都に残る江戸の情景が池波を足繁く通わせた

画像:京都花街・宮川町の夜(撮影:高野晃彰)
時代小説を得意とした池波正太郎にしては、意外に感じられるかもしれないが、その作品で京都を舞台にしたものは、それほど多くはない。しかし、池波は月に一度は京都に足を運んでいた時期があったほど、京都という街に傾倒していた。
このことについて池波は、エッセイ集『食卓の情景』で次のように述べている。
「私が書いている時代小説というものは、いうまでもなく何百年前のむかしの時代に生きていた人々を描くわけだから、平安・鎌倉の時代はもとより、戦国のころから江戸時代におよぶ日本の文化風俗を、およばずながらもさぐり探るために、京都という町は欠くべからざるものなのだ。江戸はもういけない。(中略)畢竟は、京の町に[江戸]を見るからであった。」

画像:杉本家裏の膏薬図子(撮影:高野晃彰)
ここで池波が言う[江戸]とは、江戸時代のことであり、京都や金沢などに残る古い街並みと、そこに色濃く残るその手の匂いに強く惹かれていた。
だから京都の中にあって、江戸時代の情景を色濃く残す社寺や旧跡、そして町並みをこよなく愛したのだ。
食通・池波の舌を唸らせた洗練された京都の味覚

画像:ウェスティン都ホテル京都の佳水園庭園 wiki.c
池波正太郎が初めて京都を訪れたのは、まだ17歳か18歳の頃、株式の仲買店で働いていた時である。
池波が悪友と称する井上留吉が一緒だった。宿は蹴上の[ウェスティン都ホテル京都](当時は都ホテル)だった。
「実はこのときはじめて本格的なホテルというものへ泊まったのだ。京都の都ホテルだった。(中略)井上が店の電話で都ホテルへ予約をし、『おい、波さん、ホテルが引き受けてくれたよ。ふしぎだなあ』そういったのを、いまもおぼえている。このとき、はじめて見た洋式バスルームで弥次喜多さながらの醜体を演じたことを思い返してみると、われ知らず笑いがこみあげてくる」『むかしの味』
[ウェスティン都ホテル京都]は、1890年創業という歴史を誇るホテル。京都を代表するホテルとして、国内外の要人・文化人が訪れている。東山蹴上の高台に広大な敷地を要し、フレンチ・鉄板焼きなどのレストラン・バーがあり、宿泊客でなくても利用ができる。
敷地内には、佳水園庭園などの創造美溢れる庭園や、野鳥の森などの自然探索路もあるので、訪ねた折は園内の散歩もおすすめだ。
池波が、京都に惹かれたのは情景だけではなかった。
「食べること」に大いに関心を示した池波は、『食卓の情景』『むかしの味』『散歩のときに何かたべたくなって』などの食に関するエッセイを残している。そうした作品の中には、必ず贔屓にしていた京の味が登場する。
京都市内有数の繁華街・河原町通と木屋町通の間は、江戸時代には土佐、長州などの藩邸が並び、それ故、幕末には、坂本龍馬をはじめとする志士たちの隠れ家が点在していた。
今でも、雑然とした細い路地のいたるところに、そうした史実を記した碑を見ることができる。

画像:古高俊太郎邸跡の石碑(撮影:高野晃彰)
そんな勤王の志士・古高俊太郎のアジト跡に店舗を構えるのが、池波が贔屓にした[志る幸]だ。
「まだ、時間が1時半ほどある。そこで、四条河原町東入ルところの[志る幸]へ行くことにした。(中略)出す物がいささかもむかしに変らず、うまい。その安心感があって、今度も裏切られなかった。黒ぬりの盆に、五・六種のとりざかなを盛って、まぜ飯を型でぬいたものを添え、これに豆腐の白味噌椀がつく。(中略)今日は、先ず鯛の刺身と野菜のごま和えを注文し、酒三本をのみながら、さらにスグキのつけものを追加した。」『食卓の情景』

画像:「志る幸」の利休弁当・鯛の刺身は単品(撮影:高野晃彰)
ここの名物は、利休弁当と味噌汁。季節のかやくご飯に、鳥と魚の焼き物、フキの煮物などの味噌汁が付く。味噌汁は単品でも注文でき、赤・白好みの味噌と、湯葉・蛤などの具が選べる。池波は、利休弁当に、必ず鯛の刺身を付け、さらに単品を数品注文し酒を飲んだという。
「明石鯛の、プリプリするような刺身であった。これを半分残して置き、これで熱い飯を一杯、さらにおとし芋の赤味噌椀とスグキで二杯目を食べと、これで酒の二本ものめば私などは満腹」と言いながら、かなりの健啖振りを発揮している。
江戸前鮨の名店[すきやばし次郎]の創業者で鮨名人の小野次郎は、「本当にタチのいいタイは、東京の築地には来ない確信があるから」という理由で、白身の握りに鯛を用いなかった。

画像:「志る幸」の鯛の刺身(撮影:高野晃彰)
池波が感激した[志る幸]の鯛の刺身を賞味してみると、その理由に納得できる。天然の明石鯛とは、こういうものかということを実感できるからだ。[志る幸]を訪れたら、鯛の刺身をお忘れなく。
池波が初めての京都の旅の際、夜行列車で早朝の京都駅に着いた時、空腹を覚え駅前の食堂で朝食をしたためる。
「私は親子丼、井上は肉うどんを食べた。『ふうん……こういつはうまい。このうどんはたまらねえ』と、いう。『うどんなんか、うまいわけがねえ』『いや、波さん、そうじゃない。京都のうどんは東京のとちがうぜ。ま、食べてごらんよ』(中略)まさに、うまい。薄味の汁が、なめらかなうどんにぴったりと似合っている。」『むかしの味』
この章では、祇園石段下にあったうどん屋[初音]の他に、同じく惜しまれつつ閉店した祇園の北京料理店[盛京亭]などを取り上げている。
幼少の頃から、関東風の味付けに馴れていた池波にとって、京都を代表する花街・祇園の洗練された味覚は、新鮮な衝撃を与えるに十分であった。

画像:イノダコーヒ本店 wiki.c
池波が惹かれた京都の味覚ついては、あげればきりがないが、最後に室町の旦那衆をはじめ京都人に愛され続ける[イノダコーヒ本店]について触れた記事を紹介しよう。
「昼近くになり、私たちは荷物を俵屋にあずけ、近くのコーヒー店イノダに出かけた。『イノダのコーヒーをのまないと、自分の一日がはじまらない』と、京都のイノダ・ファンがいうほどの店である。」『よい匂いのする一夜』
[イノダコーヒ本店]の朝は早い。早朝の7時から店を開ける。常連客は定位置について、イノダでの朝のひと時を楽しむ。コーヒーの味、店に流れる空気。そうしたものが一体となって、ごく自然にゆったりと時間が過ぎてゆく。
池波は、イノダでサンドウィッチをテイクアウトしてから、帰りの新幹線に乗り、冷えた缶ビールとともに味わうのを無上の楽しみにしたという。
池波作品から素晴らしき京都を読み取る

画像:取り壊しが進む室町界隈に健在の京町家(撮影:高野晃彰)
京都市の人口は約147万人。いうまでもなく、関西圏における大阪・神戸と並ぶ中枢都市だ。そんな街だから、池波が亡くなった30年前にはすでに近代化の波は押し寄せていた。
現在の京都は、インバウンドによる観光公害と、それに伴うホテル・マンションなどの建築ラッシュが続く。その代償として、貴重な町家が次々に取り壊され、古い街並みが破壊されつつある。
もし池波が生きていたら、こんな京都の現状を大いに嘆くに違いない。本当に今の京都は、ただのありふれた街になるかどうかの正念場に差し掛かっているといっても過言ではない。
京都は、その歴史的な資産があってこそ、価値のある観光地といえる。池波正太郎のエッセイを読んで、一昔前の「素晴らしき良き京都」の情景を心に焼き付けてから、訪ねて欲しいと願ってやまない。





















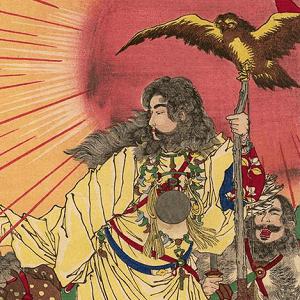



この記事へのコメントはありません。