古今東西、後継者選びは重要な問題であり、その選択によって一族や事業が栄えるか、滅びるかが決まると言っても過言ではないでしょう。
しかし、大切であるがゆえに私情が入り込んで判断を鈍らせ、禍根を残してしまった事例は枚挙に暇がありません。
今回はそんな一例として、匈奴の英雄・冒頓単于(ぼくとつ ぜんう。生年不詳~紀元前174年没)の下剋上エピソードを紹介したいと思います。
厄介払いとして殺されかけるも、みごと脱出!
匈奴(きょうど)は紀元前4世紀から紀元5世紀にかけてモンゴルを中心に勢力を築いた騎馬民族で、しばしば中原(ちゅうげん。中国歴代王朝の支配地域)の北方を脅かしていました。

暴れ回る匈奴たち(イメージ)。
冒頓はそんな匈奴の指導者である頭曼単于(とうまん ぜんう)の嫡男として生まれ、幼少時から利発で逞しく成長。単于の位を継ぐ者(太子)として申し分ない資質を備えていたと言います。
実に末頼もしいばかりですが、ある時、頭曼単于の愛妾に子供(冒頓にとっては異母弟)が生まれると、そっちに単于の位を継がせたくなるのが親バk……親心というもので、たちまち冒頓の存在が邪魔になってしまうのです。
何か言いがかりをつけて追い出したいところですが、優秀で人望もある冒頓を太子の地位から引きずり下ろすだけの材料がなく、対して、新しく生まれた子はちょっと病弱っぽい……これで太子を交代させたら、みんなの反感を買うことは間違いありません。
何かよい方法はないものか……考えた頭曼単于は、冒頓を西方の騎馬民族・月氏(げっし)へ人質に出すことを決定します。
「えっ!太子を人質に出されるのですか?」
「……そうじゃ。月氏とは永らく争って来たが、状況はこちらに不利……そこで、我が大切な跡取りである太子を人質に出せば、奴らも『よもや攻めて来るまい』と油断しよう。その間に力を蓄え、機(とき)が満ちれば太子を連れ戻し、一気に攻め滅ぼすのじゃ」
確かに、普通に考えれば「殺されたら困る」からこそ人質には効果があるのですが、頭曼単于が近ごろ冒頓を疎み始めていることを、家臣たちは薄々感じていました。
(これは絶対、冒頓様を月氏に殺させるおつもりなのであろうな……)
とは言え、単于の命令は絶対です。
「……との仰せにございます……太子。くれぐれもお気をつけなされませ……」
「解っている。そなたの心遣い、決して無駄にはするまいぞ」
かくして月氏への人質に出されてしまった冒頓ですが、みんなの予想通り、頭曼単于は「冒頓が奴隷のように扱われている」などと言いがかりをつけて兵を起こし、さっそく月氏に攻めかかります。
となれば当然、人質となっている冒頓は殺される運命にあるのですが、ここで冒頓は勇敢にも大立ち回りを演じて駿馬を奪い、みごとに月氏の包囲を突破。自力での帰還を果たしたのでした。

月氏より駿馬を奪い、無事に帰還した冒頓(イメージ)。
せっかく月氏が殺してくれると思ったのに、帰って来たばかりか、ますます人気を高めてしまった冒頓を忌々しく思う頭曼単于でしたが、
(まぁ、とりあえずは「優秀な跡取り息子」を手許に置いておくか……)
ということで冒頓の辛苦をねぎらい、裏切ってしまったことに対して適当な言い訳でお茶を濁した頭曼単于ですが、そんな戯れ言を冒頓が心から信じた訳でないことは、言うまでもありません。
(此度は無事に切り抜けたが、このままでは再び火の粉が降りかかろう……今に見ておれ……!)
復讐を誓う冒頓は、ある計画を進めていくのでした。
「我が射るもの、すべてを射よ」苛烈を極めた鏑矢の訓練
「冒頓様、これでようございますか?」
職人から渡された鏑矢(かぶらや。矢の先端に蕪状の笛を装着し、射ると音が鳴るもの)を手にとり、その独特なデザインを満足げに眺めました。そして試しに射てみると、ピィィィ……ッとよく澄んだ、鋭い音が響きます。
「上等だ……礼を言うぞ」
冒頓は、この特注の鏑矢を持って家臣たちを集めました。
「皆の者、よく見よ。これは我が鏑矢だ。これより狩りに出るが、わしがこの鏑矢を射たら、全員がわしの射たものを射よ。必ず射よ。もし射ぬ者があれば、その場で殺す!」
「「「ははあ」」」
いったい何でそんな事を言い出したのかと思いながら、家臣総出で狩りに出たところ、一頭の鹿がいました。

鏑矢を射る冒頓(イメージ)。
冒頓が真っ先に鏑矢を射たところ、家臣たちも一斉に鹿へ射放ちましたが、中には矢を射ない者がいました。冒頓はその者たちを問い質します。
「そなたらは、何ゆえ我が射たものを射なんだか!」
「いえ、既に多くの矢が放たれ、あれだけ射れば十分かと……」
確かに、鹿には数十という矢が突き立ち、既に絶命していました。しかし、冒頓が求めていたのはそういう事ではありません。
「ただ鹿を射止めるなら一矢で事足りる。わしの求めておるのはそう言うことではない!」
冒頓は抜刀するなり、射なかった者たちを全員斬り殺してしまいました。
「……今後も同じことを致すゆえ、我が命に従わぬ者は斬る。よいか!」
「「「ははあっ……!」」」
冒頓が求めていたのは、自分の命令を聞く必要があるか否かといった(余計な)自己判断をせず「とにかく盲従すること」であり、その意味を理解した家臣たちは、冒頓が鏑矢を射たものは、必ず射るようになりました(射るのが遅れた者、若干でも躊躇いを見せた者など、どんどん斬られていきました)。
……と、ここまではまだ序の口。家臣たちがすっかり「鏑矢の命令」に慣れてきたところで、冒頓は次の段階へ進みます……ある日、冒頓は家臣たちの目の前で、自分の愛馬を鏑矢で射たのです。
騎馬民族にとって、馬は単なる家畜を越えた家族であり戦友であり財産であり(そして最後には非常食)……まさに生命線ともいえる存在。いくら主君の命令とは言え、決して徒(いたず)らに射殺してよいものではありません。
これまで冒頓は「射て(殺して)も支障のないもの」ばかり射て来ましたが、これからは「射るのを躊躇ってしまうもの」「常識的に射てはいけないもの」にハードルを上げたのです。
この世のどんなものよりも、我が命令をこそ最優先せよ……冒頓の訓練は苛烈を極め、ついには冒頓の愛妾さえ血祭りに上げてしまいました。
「これでよし」
今や命令とあれば何でも射るようになった家臣たちを引き連れ、冒頓は総仕上げとして頭曼単于の愛馬を射ると、もはや全員が一瞬の躊躇いもなくそれを射殺しました。ついにクーデターの始まりです。
下剋上、そして一大遊牧国家へ
自分の愛馬を冒頓が射殺したと聞いて、頭曼単于はカンカンに怒り狂いました。
「冒頓、血迷うたか!」
父の問いかけに冒頓は口を開かず、ただ鏑矢をもって答えると、家臣たちの矢が一斉に射放たれ、頭曼単于は全身に矢を突き立てられて息絶えます。
「逆らう者は皆殺しじゃ……者ども、かかれ!」
冒頓はすかさず継母と異母弟を粛清して単于に即位。その後30年以上(在位:紀元前209年~紀元前174年)にわたって匈奴に君臨、大いに暴れまわりました。

冒頓(メテ)をデザインしたトルコの切手。その末裔と呼ばれるメテ姓の人々も。
その後も月氏や東胡(とうこ)など諸民族を圧倒し、中原を統一した漢(かん)の皇帝・劉邦(りゅう ほう)さえ追い詰めるなど、北アジアに一大遊牧国家を築き上げることになるのですが、その物語はまたの機会に。
※参考文献:
司馬遷『史記7 列伝三 (ちくま学芸文庫)』ちくま学芸文庫、1995年7月1日
林俊雄『スキタイと匈奴 遊牧の文明 (興亡の世界史)』講談社、2007年6月16日
沢田勲『匈奴―古代遊牧国家の興亡 (東方選書)』東方書店、1996年12月1日














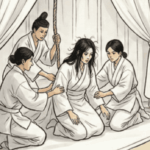








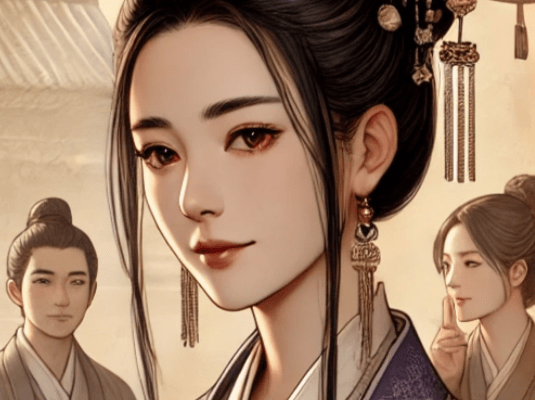

この記事へのコメントはありません。