
画像 : 毛利輝元 public domain
関ヶ原の戦いは、石田三成が率いた西軍と、徳川家康が率いた東軍との決戦、というイメージが一般的である。
しかし、石田三成は西軍の総大将ではない。名目上、西軍の総大将に据えられていたのは、毛利家当主の毛利輝元であった。
実際、西軍に属した諸勢力の中には、毛利氏と主従・縁戚・同盟関係を持つ武将や家が数多く含まれており、関ヶ原合戦は毛利氏の動向を抜きにして語ることができない戦いである。
にもかかわらず、輝元自身は関ヶ原の戦場に姿を見せず、毛利本隊も本戦で決定的な戦闘行動を取ることはなかった。
毛利輝元はどのような立場で西軍に関与し、なぜ主力を動かさぬまま敗北を迎えるに至ったのだろうか。
毛利家のなりたちと毛利両川

画像 : 毛利元就、晩年の肖像画。 public domain
毛利家を中国地方の大勢力へと押し上げた人物が、輝元の祖父・毛利元就である。
戦国大名としての毛利家の基礎は、ほぼこの元就一代で築かれたと言ってよい。
元就は、多くの言葉や教えを残した人物としても知られているが、なかでも毛利家の性格をよく表している教えが二つある。
一つ目が、有名な「三子教訓状」である。
いわゆる「三本の矢」の逸話のもとになった書状で、「兄弟が力を合わせて毛利家を支えよ」という内容であった。
実子である毛利隆元、吉川元春、小早川隆景の三人に向けて書かれたものである。
この教えの通り、隆元が宗家を継ぎ、元春と隆景は分家でありながら宗家を支える立場に回った。
こうして吉川・小早川の両家は「毛利両川」と呼ばれ、毛利家の屋台骨となっていく。
もう一つが「天下を競望せず」という教えで、無理に天下を狙えば家を危うくするという意味である。
中国地方をほぼ制圧するまで勢力を拡大しながらも、元就はそれ以上の野心に慎重であった。
無理に中央へ打って出れば、家そのものを危うくする。そうした現実的な判断を、子孫に言い残していたのである。
この二つの教えは、毛利家が拡大よりも存続を重んじる家であったことを、端的に物語っていると言えるだろう。
各自でやっていた外交活動
関ヶ原の直前、毛利輝元の立場は不安定な状況にあった。
輝元を長年支えてきた叔父の吉川元春と小早川隆景はすでに世を去り、輝元の実子である秀就はまだ幼少であった。
とりわけ大きかったのが小早川家の変化である。
隆景の死後、その跡を継いだのは豊臣秀吉の親族である小早川秀秋だった。
かつて毛利宗家を支えてきた「毛利両川」は次第にその機能を失い、代わって毛利元就の孫にあたる秀元が、宗家を支える一門の中核的存在となっていく。
秀元は元就四男・穂井田元清の子で、豊臣秀吉との対面を経て輝元の後継候補として位置づけられた人物であり、関ヶ原前後には毛利一門を代表して軍事行動の前面に立つ立場にあった。
こうした状況の中で輝元を特に支えていたのが、僧侶でありながら政治・外交の要でもあった安国寺恵瓊と、元春の子である吉川広家であった。

画像 : 安国寺恵瓊「教導立志基三十三:羽柴秀吉」(月岡芳年) public domain
豊臣秀吉の死後、輝元は石田三成と歩調を合わせ、台頭する徳川家康を牽制しようとする。
しかし三成は「三成襲撃事件」によって失脚し、政局の前面から姿を消した。
これにより家康の影響力は一気に拡大し、輝元の危機感はさらに強まっていく。
安国寺恵瓊は、そうした輝元の思いを汲み取り、反家康勢力と水面下で連絡を取り続けた。
一方で、吉川広家は黒田官兵衛・長政父子と親しく、彼らを通じて徳川方とも接触していた。
立場の異なる二人が並立していたことは、毛利家内部に微妙な温度差を生み、そのズレはやがて関ヶ原の戦局に影を落とすことになる。
西軍総大将と内部分裂した毛利家

画像 : 吉川広家の肖像 public domain
安国寺恵瓊を通じて石田三成と密に連絡を取っていた輝元は、やがて三成の動きに同調する。
三成が挙兵すると、輝元はほどなく大坂城に入り、西軍の総大将という立場に就いた。
その後、西軍は徳川方の要衝である伏見城を攻撃する。
この戦いには、毛利秀元と吉川広家という新たな形の「毛利両川」も加わったが、広家の動きは終始消極的だった。
実際、広家はこの出陣について、やむを得ず参加したにすぎないという趣旨の弁明書を、徳川家康宛てに送っている。
8月17日には、黒田長政から、家康の書状の写しを添えた手紙が広家に届けられた。
『吉川家文書』によれば、長政はその中で、広家が家康と敵対する意思は薄いこと、輝元の動きは安国寺恵瓊の主導として処理したい意向があることを踏まえつつ、態勢を整えるよう促したとされる。
こうして広家は、主君である輝元の決断と、長政を通じて示される家康側からの説得との間で、板挟みの状態に置かれることになる。
その後も広家は、西軍として戦いに関わりながら、同時に黒田長政との連絡を絶やさず、輝元を翻意させようと動き続けていた。
関ヶ原本戦でのバラバラの動き
関ヶ原本戦の前日、徳川直臣の本多忠勝と井伊直政から、毛利方に書状が届けられた。
そこには「毛利輝元や吉川広家を見捨てるつもりはなく、もし従うのであれば所領の安堵も考慮する」といった趣旨が記されていた。
この書状をどう受け止めるかについては解釈が分かれるが、少なくとも輝元が吉川広家の説得を受け入れ、毛利勢として積極的に決戦する意思を失ったことは確かである。
ただし輝元は、明確に「東軍へ寝返った」というわけではなく、実態としては「戦わない選択」を取った、という表現の方が近いだろう。
この動きを、安国寺恵瓊は把握していなかったとされる。

画像 : 関ヶ原の戦い布陣図を元に作成(草の実堂)public domain
そして迎えた関ヶ原本戦当日、毛利軍は家康本陣の背後にあたる南宮山に布陣していた。
毛利秀元は山を下りて徳川軍の背後を突く構えだったが、先陣に立つ吉川広家が出撃に応じず、毛利軍は動けないまま時間を失っていく。
このとき、長束正家の使者が戦闘参加を求めて南宮山に駆けつけたが、広家の兵に前を塞がれて動けなかった秀元は、仕方なく「兵卒に兵糧を取らせている最中だ」と応じ、時間を稼いだと伝えられる。

画像 : 毛利秀元 public domain
のちに、この言い分は吉川広家の消極姿勢と結びつけられ、「宰相殿の空弁当」と皮肉を込めて語られるようになった。
南宮山に布陣していた毛利勢は、結局最後まで動かず、秀元の軍勢も出撃の機会を失う。
その後、小早川秀秋が東軍へ寝返り、西軍の陣形は内側から崩された。
南宮山の毛利勢が動かないまま、小早川の裏切りが決定打となり、西軍は急速に瓦解していく。
こうして関ヶ原の戦いは、わずか半日ほどで東軍の勝利に終わったのである。
西軍が敗れた理由は一つではないが、「動かなかった毛利」と「裏切った小早川」が、最も戦局に影響を与えたことは間違いないだろう。
毛利家に言い渡された処分

画像:東照大権現像(狩野探幽画、大阪城天守閣蔵)public domain
本来であれば、戦後、毛利家は所領安堵を受けるはずだった。
実際、吉川広家らを通じて、徳川家康からその含みを持たされた形跡も史料に見える。
ところが東軍の勝利が確定すると、家康の態度は一変した。
問題視されたのは、毛利家の行動があまりにも曖昧だった点である。
関ヶ原方面に兵を出していながら本戦では動かず、その一方で、阿波をはじめとする四国方面へも軍を動かしていたことが明らかになった。
これは「関ヶ原の戦局を見ながら、西での領土拡張を狙っていた」と受け取られても仕方のない動きだった。
その結果、毛利家は周防・長門二国のみを安堵され、石高は約120万石から約30万石へと大幅に削減されることになる。
毛利家にとっては、事実上の敗北処分であった。
関ヶ原の戦い以後、多くの記録において、安国寺恵瓊は厳しい評価を受けている。
『陰徳記』『芸備国郡志』『慶長記』などでは、恵瓊を専横的で無責任な人物として描く記述が目立ち、地元での評判も芳しくなかったとされる。
もっとも、こうした評価の中には、戦後処理の過程で責任を一身に押し付ける意図が含まれていた可能性も否定できない。
特に吉川家が残した史料には、恵瓊を強く批判する内容が多く見られるが、後世の自己正当化や政治的意図による脚色が含まれていると指摘されることも多い。
恵瓊像については、史料の性格を見極めたうえで、慎重に読み解く必要があるだろう。
おわりに

画像 : 関ヶ原跡地(徳川家康最終陣地)草の実堂編集部撮影
では、毛利輝元は、関ヶ原にあたって何を目指していたのだろうか。
安国寺恵瓊と吉川広家という、性格も志向も異なる側近の間で判断を迫られ、結果として輝元自身の意思は前面に出ないまま、多くの所領を失う結末を迎えた。
西軍総大将という立場にありながら、天下を奪う明確な意思があったとも言い切れず、その行動は一見すると優柔不断に映る。
しかし輝元にとっては、毛利家という巨大な「家」を背負う当主として最悪の事態を避けようとした結果が、あの曖昧な態度だったとも考えられる。
加えて、関ヶ原で主力を温存しつつ、西国で勢力を拡大し、戦後を見据えた基盤固めを図ろうとした可能性もあるだろう。
戦後、安国寺恵瓊は石田三成、小西行長とともに六条河原で斬首され、生涯を終えた。
結果的に毛利家は、恵瓊に多くの責任を負わせることで、家そのものの存続を選び取った形となる。
その後も、毛利家と吉川家の関係は、江戸時代を通じて微妙な緊張をはらみ続けた。
毛利側からすれば、吉川広家の説得を信じて「戦わない」という選択をしたにもかかわらず、本領安堵が反故にされたという思いが、心のどこかに残り続けていたのかもしれない。
関ヶ原における毛利輝元の行動は、英雄的でも痛快でもない。
だが、滅亡を免れ、家を次代へとつないだという結果だけを見れば、あの選択を単純に失策と断じることもできない。
その評価は、見る立場によって大きく分かれるのである。
参考:『毛利家文書』『吉川家文書』『萩藩閥閲録』他
文 / 草の実堂編集部
















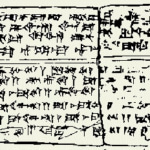








この記事へのコメントはありません。