どれほど科学が進歩した現代であっても、突如として襲いかかる天変地異に対抗するすべはない。
とりわけ大規模な火山噴火は、地球環境を揺るがすだけでなく、人類史そのものにも深い爪痕を残してきた。
今回は、ニュージーランド北島に位置する「タウポ火山の大噴火」をめぐる一つの説を紹介しつつ、弥生時代末期における歴史の転換点との関わりを見ていきたい。
「倭国大乱」はなぜ起きたのか

画像:伊都国との闘いに備え、兵士達を鼓舞する女王卑弥呼 public domain
邪馬台国の成立やその所在地については、現在に至るまで数多くの説が唱えられているが、決定的な結論には至っていない。
一方で、中国の史書である『後漢書東夷列伝』や『魏志倭人伝』には、2世紀後半の倭国が深刻な混乱に陥っていたと記されている。
それらによれば、倭国では当初、男性の王が立てられていたものの、その後およそ70〜80年を経るうちに国々が互いに争うようになり、長期にわたる混乱状態に陥ったという。
この争乱を収めるため、諸国は一人の女子を共立して王としたとされる。
その人物こそが卑弥呼であり、鬼道を用いて人々を治めた女王として知られている。
これが、一般に「倭国大乱」を経て、邪馬台国が成立したとされる経緯である。
しかし、この倭国大乱がなぜ起きたのかについては、現在でも明確な結論は出ていない。
従来は、大陸や朝鮮半島との交易によって優位に立っていた北部九州勢力に対し、出雲・吉備・タニハ(京都府北部)といった日本海側の勢力が台頭し、さらに畿内や尾張などの勢力も加わった結果、列島規模の対立へと発展したと考えられてきた。
その根拠としては、吉備の楯築墳丘墓、出雲の大型四隅突出型墳丘墓、タニハの大型長方形墳丘墓といった有力首長墓の出現や、畿内・東海地域で独自に発展した銅鐸文化などが挙げられている。
もっとも、こうした勢力争いだけで、倭国全体を揺るがすほどの「大乱」が引き起こされたのかについては、疑問の余地も残る。
タウポ火山大噴火と異常気象をめぐる一つの説

画像:タウポ火山帯のナウルホエ火山 public domain
弥生時代末期に倭国大乱が起きたとしても、単に九州北部・日本海・畿内といった地域勢力の競合だけによって引き起こされたと考えるのは、やや単純に過ぎるという見方もある。
そこには「大乱」と呼ばれるものが発生せざるを得なかった、もっと強い要因が存在したとみる方が自然であろう。
そうした視点から注目されてきたのが、ニュージーランド北島に位置する「タウポ火山の大噴火」である。
この噴火は、過去数千年の火山活動史の中でも最大級の規模を誇り、地球環境そのものに大きな影響を及ぼした可能性が指摘されてきた。
このような規模の巨大噴火が発生した場合、噴煙とともに放出された火山灰や火山ガスは成層圏に達し、地球規模で拡散する。
その影響はアジアにも及び、日本はもちろん、中国大陸や朝鮮半島にも広がったと推定される。
冷夏や日照不足、旱魃といった異常気象が重なれば、稲作を基盤とする社会が大きな打撃を受けるのは避けられない。各地で不作や飢饉が起こり、社会不安が広がった可能性は十分に考えられるだろう。
近年の自然科学的な研究では、このタウポ火山の噴火は3世紀前半、概ね230年前後に起きたとみられている。
ただし、この年代には一定の幅があり、2世紀後半、具体的には181年ごろに起こったと見る説も存在している。
ここではあくまで一説ではあるが、もし噴火が2世紀後半(181年ごろ)に起きたと仮定した場合、当時の列島社会はどんな影響を受けたのか、という視点から見ていきたい。
中国・朝鮮半島の流民が北部九州へ押し寄せた?

画像:清代の書物の黄巾の乱 public domain
タウポ火山の噴火が、仮に2世紀後半(181年ごろ)に起きていたとした場合、中国ではどのような影響が生じたのだろうか。
その象徴的な出来事として挙げられるのが、後漢王朝の衰退を決定づけた184年の「黄巾の乱」である。
黄巾の乱の根本的な要因は、後漢末期の深刻な政治腐敗と苛政に対する民衆の不満であった。
そこに、異常気象による凶作や飢饉が重なり、不満と混乱が一気に噴き出したとみることもできる。
『魏志韓伝』には、こうして難民となった農民が大量に朝鮮半島南部へ流入したことが記録されている。
彼らはそこでも安住できず、さらにドミノ式に北部九州へと移動していった可能性も指摘される。
難民流入による混乱が「倭国大乱」に発展?

画像:北部九州(伊都国)の王墓とみられる平原遺跡・1号墓 public domain
タウポ火山の大噴火による異常気象の影響で、仮に多くの難民が流入したとすれば、北部九州はその対応に追われたに違いない。
現代社会においても、生活習慣や文化の違いから地元住民との摩擦が生じる例は少なくない。
まして弥生時代の北部九州は稲作への依存度が高く、冷夏による凶作や飢饉の打撃は深刻だったと考えられる。
そのような状況下で、大量の難民が朝鮮半島から雪崩れ込むように流入すればどうなるだろうか。
政治的・経済的に優勢であった北部九州の勢力は、こうした混乱の中で徐々にその優位性を失い、出雲・吉備・タニハ(京都府北部)・畿内・尾張など、各地の勢力との衝突が生じただろう。
その争いには、食料の確保だけでなく、当時もっとも重要な資源であった鉄の争奪も含まれていたはずである。
こうした連鎖的な混乱こそが、倭国大乱と呼ばれる事態の実像だったと見ることもできる。
共生の道を模索し「邪馬台国」が誕生する

画像:纏向遺跡居館跡(撮影:高野晃彰)
異常気象による打撃を受けていたのは、九州北部だけではなく、出雲・吉備・タニハ(京都府北部)・畿内・尾張といった各地も同様だったと考えられる。
つまり、当時の諸勢力には、これ以上軍事的な争いを続ける余力はほとんど残されていなかったと考えるのが妥当である。
そのため、彼らは互いに争うのではなく、共生の道を模索した。
それが、女王・卑弥呼を擁立した邪馬台国、すなわち邪馬台国連合の成立だったのではないだろうか。

画像:纏向石塚古墳(撮影:高野晃彰)
邪馬台国の有力候補地として知られる奈良県桜井市の纏向(まきむく)遺跡は、3世紀前半に突如として出現する。
その立地は四方を山に囲まれ、風水害が少ない奈良盆地内に位置し、自然災害の影響を受けにくい点でも政治的中心地として適していたといえるだろう。
さらに、纏向遺跡では他地域から搬入された土器が全体の約15%を占め、その出自は九州から関東にまでおよんでいる。
また、纏向石塚古墳をはじめとする纏向型前方後円墳や、のちの前方後円墳の規範となる箸墓古墳には、吉備地方に起源をもつ特殊器台が採用されている。
これらの考古学的事実は、纏向地域が広域的な交流を掌握しうる政治的中心地であり、邪馬台国連合の首都にふさわしい性格を備えていたことを示している。
そして同時に、大噴火による異常気象という外的要因が、新たな政治秩序の形成、すなわち邪馬台国誕生を後押ししたと考えられるのではないだろうか。
※参考文献
Piva, S. B. et al., Volcanic glass from the 1.8 ka Taupō eruption detected in Antarctic ice, Scientific Reports(2023)
瀧音能之監修 『発掘された日本神話』 宝島社新書
『魏志倭人伝』他
文・写真(一部)/ 高野晃彰 校正 / 草の実堂編集部













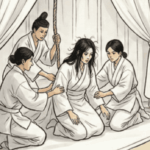











この記事へのコメントはありません。