京都は、北・東・西の三方を山々に囲まれた盆地の町です。
その地形ゆえ、四季の移ろいが際立ち、昼夜の寒暖差も大きいという特徴を持っています。
なかでも、京都の冬は厳しい寒さで知られます。
盆地特有の放射冷却や昼夜の寒暖差が重なり、実際の気温以上に冷たさを感じさせるためです。
肌を刺すような冷気が、じわじわと身体の芯へと染み込む。
まさに京都の冬は、「底冷え」という言葉がぴったり当てはまる寒さを人々に実感させます。
そんな京都では、毎年小正月にあたる1月中旬(14日・15日)頃、市内各地の社寺で「どんど・左義長」と呼ばれる神事が行われます。
役目を終えたしめ縄や門松を焚き上げ、神前の鏡餅を焼いて氏子や参拝者に授与するこの行事を境に、京都には遅い春の気配が、そっと忍び寄ってくるのです。
新たな年へ心を引き締める神事「左義長(どんど)」

画像:左義長の炎で焼かれる餅
「さぁ、どんど、やるぞーッ」
そんな合図とともに、町に火入れの時が訪れます。
むかし御所では、正月十五日に吉書初めや短冊などを焚き上げる行事があり、これを「左義長(さぎちょう)」と呼んでいました。
やがて民間でも、これにならって正月の松飾りなどを焼くようになったといいます。
「左義長」は、日本全国で行われていますが、京ではこれを「どんど」と呼んだのです。
「お注連縄、くうだんせ、くりくりだんせ、くうだんせ、どんどや左義長(さぎっちょ)、餅のかけ、ないかいな」
こんな俚謡(りよう)を囃しながら、子どもたちは町内を巡りました。
「どんど」の火は見る間に勢いを増して燃え盛り、白い煙が、真っ青な大空へ舞いのぼります。

画像:左義長の炎で焼かれる餅(撮影:高野晃彰)
この火で焼いた餅を食べると病気にならないという言い伝えがあり、子どもたちは盛んな炎に手を合わせて拝みました。
そして大人たちは、「どんど」を境に正月気分を一新し、新たな年へと心を引き締めたのです。
京都の冬の風物詩の一つであるお漬物「すぐき」
冬の京都に欠かせないお漬物といえば、「千枚漬け」と「すぐき」です。
いずれも、京都の伝統野菜である聖護院かぶら、そしてすぐきかぶらを使った逸品として知られています。
お正月、「千枚漬け」のほのかな甘さに慣れた舌も、今度は「すぐき」の酸味で引き締まると、京都に暮らす人々は語ります。

画像:すぐき(御すぐき處 京都なり田)
「すぐき」とは、洛北・賀茂の特産である酸茎菜(すぐきな)を漬けたもの。
乳酸菌の働きによって生まれる、独特の強い酸味が特徴のお漬物です。
その漬け込み作業もまた独特で、長い丸太棒の先に重しを吊るし、この原理を応用して強い圧力をかけます。
この漬け込み風景は冬の季節の風物詩として知られ、もともとは上賀茂神社の社家において、公家の奥向きに漬けられていたとされる、由緒ある高貴な食べものだったとも伝えられているのです。
焼いても良しお造りでもよし京の冬を代表する魚「グジ」
この時季の京を代表する魚といえば、やはり「グジ」に勝るものはないでしょう。
「グジ」とは上方での呼び名で、実は「甘鯛」のこと。
なかでも「赤甘鯛(アカアマダイ)」を指します。

画像:若狭ぐじ/赤甘鯛(ふくいドットコム)
この「グジ」は、焼きものでいただくなら、ウロコをつけたまま焼くのがならいです。
遠火でじっくり焼き上げると、ウロコが鎧(よろい)の小札(こざね)のように美しくそろい、狐色に色づきます。
このように調理すると、不思議なほど身が皮からほろりと離れるのです。
また「グジ」は、生で味わっても格別で、その食べ方には2種類あります。
一つは、地甘(じあま)と呼ばれる生の「グジ」で、獲れたてのものに氷を詰め、京都の市場へと送られてきます。
もう一つが、一汐(ひとしお)の「グジ」です。
こちらは浜で揚がるとすぐに背を開き、内臓を取り除いたうえで、身に薄く塩を振り、氷詰めにして京都の市場へ運ばれます。

画像:グジの焼き物と細造り(平八茶屋)
京都らしい食べ方といえば、後者の一汐ものによる細造りでしょう。
塩を振って一昼夜置くことで身から余分な水分が抜け、もっちりとした食感が生まれます。
真夏の魚が「鱧(はも)」なら、真冬の魚は「グジ」。
まさに京都を代表する、双璧の味覚と言っても過言ではないでしょう。
松ノ内を過ぎると、やがて古式ゆかしい節分会、香り花やぐ梅花祭……。
たまにドーンと大雪に見舞われることもありますが、京都の人は驚きません。
表へ出て北の空を仰げば、雲はゆっくり動きはじめています。
「もうじき比良八講(ひらはっこう)や。八荒が吹いたら、底冷えも終わりやし」
八荒とは、春を告げる荒風のこと。
このひところを境に、京の冬はゆき、春がそっと近づいてくるのです。
※参考文献
京あゆみ研究会(高野晃彰)著 『京都 ぶらり歴史探訪ガイド 今昔ウォーキング』メイツユニバーサルコンテンツ刊
文 / 高野晃彰 校正 / 草の実堂編集部


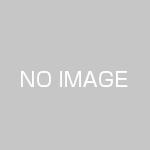












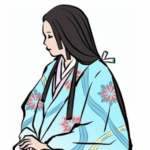









この記事へのコメントはありません。