人類史において、現在のところ記録に残る最古の「馬にまたがる」騎兵は、おおそ紀元前883年の記録だ。
それ以降、人間は馬に乗って槍や剣、弓、そして銃と、武器は変わりながらも騎兵を運用し続けてきた。日本ではおおむね古墳時代の4世紀末から5世紀にかけて、すでに騎兵が運用されていたと推測される記録がある。
騎馬武者や流鏑馬といった日本の騎兵運用はよく知られているが、大砲や機関銃を使うようになった「近代戦」において、騎兵を巧みに使い、「日本騎兵の父」と呼ばれた人物がいる。それが、日露戦争において騎兵部隊を率いた「秋山好古」(あきやま よしふる)という人物である。
この記事では、秋山好古とはどのような人物だったのか、彼はどのように騎兵を運用したのかについて解説してみよう。
秋山好古とはどのような人物だったのか

フランス留学中の秋山
秋山好古は、安政6年(1859年)に、伊予松山城下(現在の愛媛県松山市」に生まれた。
秋山好古が騎兵の道へ進んだのは、明示12年(1879年)、陸軍騎兵少尉として東京鎮台に配属されてからとなる。以降、騎兵科の教官を務め、明示18年には参謀本部へ勤務している。
明治20年には、フランスへ留学、騎兵戦術を学んでいる。興味深いのは、当時の日本陸軍は基本的にドイツ式を採用していたが、騎兵だけはフランス式を採用している。これには秋山の尽力があったとも言われる。なお、このフランス留学時のエピソードとして、後に旅順攻略戦、奉天会戦で重要な役回りを演じた「乃木希典」と親交を深めていたというものがある。
秋山の個人的な性格を示すエピソードとしては、「酒好き・風呂嫌い・医者嫌い・だが”イケメン”」である。
酒によって大事な土産物を亡くしたり、風呂嫌いで日露戦争従軍中はわずか2回しか風呂に入らず、身体からは異臭を放っていたというエピソードがあるなど、なかなか一筋縄ではいかない人物だったようだ。しかし、高く通った鼻筋と長身、大きな目は当時の人々からも特徴的であり、陸軍大学校時代に教官として訪れていたドイツ人のメッケルから、ヨーロッパ人と間違えられたという話もあるほどだ。
ちなみに、秋山好古は陸軍・騎兵の道へと進んだが、弟・秋山真之は海軍へ進む。
真之は日露戦争の海上での決戦となった「日本海海戦」において、第一艦隊旗艦「三笠」に作戦担当参謀として乗艦している。
当時の「騎兵」の扱いについて

「騎兵」といえば、実は歴史的には洋の東西を問わず軍の中ではエリート集団である。
ヨーロッパでは騎士、日本では武士と、「従者を連れて戦場に赴く」うえでのその小集団のリーダーのような位置づけである。歴史書などで、軍勢の数を「○騎」と表記する場合には、「馬に乗った人物が○人(そこに3~4人の徒歩の従者・兵卒が続く)」という意味合いで書かれていることもある。しかし、銃や大砲といった大火力の武器が登場し、さらに騎兵最大の武器である「機動力」を実質的に封じられてしまう「機関銃」の登場によって、騎兵の立場は一気に危ういものとなった。

騎兵というのは、その機動力と衝撃力によって敵に痛撃を与える役割を持つ、いわば「攻めるため」の兵科であるのだが、機関銃という新兵器の前では、騎兵の突撃も歩兵の突撃も、ほとんど意味をなさなかった。
その理屈で考えれば、歩兵であれば機関銃による損害は「歩兵1名」だが、騎兵の場合は「兵1、馬1」の損害となる。また、馬を養うためのコストも無視できなかっただろう。しかし、そのような情勢下で、秋山は「騎兵科」の創設に心血を注いだ。
その念頭にあったのは、当時世界最強と謳われたロシア騎兵、「コサック騎兵」との戦いであろう。
「騎兵とは、これだ!」

「秋山好古」という名前を聞いて、「騎兵とは、これだ!」というエピソードを思い浮かべる人もいるかもしれない。これは、司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」に登場するエピソードである。
秋山が陸軍大学校で、学生たちに騎兵とはどのような兵科かを教える際に、素手で窓ガラスを叩き割り、「騎兵とは、これだ」と示したというエピソードである。この説話が意味するところとはすなわち、窓ガラスを素手で叩けば手は傷を負うものの、ガラスは割れることから、騎兵の高い攻撃力と、反面、皆無といってもよい防御力の低さ、損害の大きさを説明したというものである。
このエピソードの真偽は不明であるが、確かに当時の騎兵という兵科の特徴をよく表しているといえよう。
秋山は騎兵をどのように運用したのか
秋山は、騎兵の高い攻撃力と、皆無に等しい防御力という特徴をよく理解していた。
かつての発射間隔の長い火縄銃やマスケット銃の時代とは異なり、威力の高い榴弾砲や、戦場を「屠殺場に変える」と表現されるほどの連射速度を持つ機関銃の前では、騎兵が従来の戦術で生き残り、かつ戦果を挙げることは困難だったのである。
そこで、秋山は、騎兵をこれまでのように機動力のみを頼りとして使うのではなく、他の兵科と連動して運用することにした。

特筆するべきは「機関銃の配備」と、「拠点防衛」という、騎兵という兵科からは考えにくい運用であった。
また、それとは別に、騎兵の機動力を生かして敵地奥深くへ侵入して破壊工作や後方撹乱を行う、「挺身騎兵」の構想も立てられ、実行されている。
これらの騎兵戦術の改革は、日露戦争における日本軍側の危機となった「黒溝台会戦」で活かされることとなった。
10倍とも言われる敵を押し留めた「黒溝台会戦」

日露両軍の布陣(日本軍の左翼、ロシア軍の右翼部分)、黄色の破線は意図された露西亜軍の進行経路 wiki c
日露戦争において、初戦は日本軍がロシア軍を撤退させることに成功するなど、順調に進軍を続けていた。
しかしこれは、ロシア満州軍総司令官アレクセイ・クロパトキンが慎重な性格であったことに加え、日本の継戦能力の低さを突くために、あえて大きな損害を出さずに撤退戦を行っていたためだった。
しかし、ロシア軍首脳はこれに苛立ち、新たにグリッペンベルク大将を送り込み、ただちに第二軍を率いて南下させ日本軍への攻撃を始めた。これが、1905年1月25日から起こった黒溝台会戦である。
このとき、日本軍は東西に広く布陣していた。このうち、秋山の率いる部隊は「秋山支隊」と呼ばれる騎兵支隊で、わずか8000人の兵力で40kmにわたる戦線を防御しなければならなかった。
秋山は、かねてから研究していた拠点防御方式をとった。秋山支隊は騎兵支隊でありながら、騎兵・歩兵・砲兵を備えた複合集団だった。秋山支隊は塹壕を掘り、軍馬をそこに隠して機関銃を据え付け、襲いくるコサック騎兵に対して頑強に抵抗した。
この結果、日本軍は辛くもロシア軍の攻勢をしのぎきり、参加兵力全体では2倍以上、秋山支隊のエリアについては10倍ともいわれる敵を撤退させることに成功したのである。
騎兵は防御を捨てて敵を叩くもの、とした自身の説話にもある戦い方にとらわれることなく、騎兵に塹壕戦をさせるという発想の転換、そして、他日、本当に必要となる騎兵の機動力を無傷で温存するという勇気ある決断ができた秋山が「日本騎兵の父」と呼ばれることも、うなずけるものだ。
おわりに

騎兵運用といえば、源義経の「鵯越」や、武田信玄の騎馬隊などが思い浮かぶ。
また海外に目を向けても、騎士がランスを抱えて突撃をしたり、騎馬民族によるパルティアンショット、ポーランドのフサリアなど、戦場の状況を一変させる華やかな活躍が多い。それこそ、騎兵が持つ「機動力」や「攻撃力」を最大の武器として敵方に衝撃を与えるという運用がなされてきたことを示すものといえるだろう。
しかし、秋山好古は騎兵という存在を、「窓ガラスを素手で割る」のではなく、他兵科と連動することで損害を最小限に押し留め、本当に必要なタイミングで機動力を用いるという構想をし、それを実行できる人物だった。
従来の「騎兵」という概念にとらわれなかった秋山はまさに、「日本騎兵の父」と言ってよいだろう。













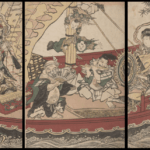










この記事へのコメントはありません。