ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインは、オーストリア・ウィーン出身の哲学者・言語学者で、日本でも人気の高い哲学者である。
彼の哲学は前期と後期に分かれており、彼の執筆した哲学書『論理哲学論考』は前期の彼の思想が書かれている。
哲学書と言うよりは数学や言語学の論文といった書かれ方をしており、回りくどい言い回しの多い哲学書の中でも特に変わった構成の本である。
生まれ

ウィトゲンシュタインは、1889年4月26日オーストリア・ハンガリー帝国に生まれる。
ウィトゲンシュタインは4歳まで言葉を話す事が出来なかった。
更に重度の吃音症であり、両親は学校に通わせずに家庭教育で育てていく事にした。
8人兄弟の末っ子である刺激の多い家庭であり、芸術の分野で高い教育に触れる機会の多い文化的な家庭環境でもあったようだ。
特に音楽は彼の哲学にも影響を与え、書籍の中にも音楽の比喩が用いられている。
しかしながら彼の家系は鬱病と自殺者が多い家系でもあり、兄4人のうち3人が自殺しており、彼自身も常に自殺の衝動との戦いの人生でもあった。
学生時代

大学生時代のウィトゲンシュタイン(1910年)
彼は1903年以降、リンツにある高等実科学校に入学し、3年間の教育を受ける。
この時、同学校にはアドルフ・ヒトラーが在学していた。
ウィトゲンシュタインはこの時期にカトリック信者としての宗教の信仰心を失っており、心配した姉のマルガレーテは、アルトゥル・ショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』を勧めている。
この書物はウィトゲンシュタインが哲学を学び始める前に読んだ唯一の哲学書であり、ウィトゲンシュタイン自身も影響を受けていると語っている。
その後、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学で機械工学を学び、工学の博士号を取得するために、マンチェスター大学工学部へ入学。そしてバートランド・ラッセルの『数学原理』を読んで数学基礎論に興味を持ち、ラッセルを訪れ彼に師事し、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学。
ラッセルやジョージ・エドワード・ムーアの元で論理の基礎に関する研究を始め、マクロ経済学で有名なケインズともこの頃に知り合った。
第1次世界大戦
1914年に勃発した第1次世界大戦で、オーストリア・ハンガリー帝国の志願兵として戦争に参加。
ロシア軍の猛攻に対して、引かずに退けた事により勲章と伍長への昇進という功績をあげる。
戦争中に兄のパウロが重傷を負ってピアニストとして活動できなくなったことをきっかけに、ウィトゲンシュタインは哲学に対して無意味さを感じ自殺を考えるようになる。
ある時、本屋へ立ち寄るとトルストイが著した福音書の解説本があり、この本を貪るように読み信仰を取り戻し、周りにも勧めたことで「福音書の男」とあだ名された。
その他にもドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』も読み耽り、10回以上読んだと言われている。
1918年の終戦間際、イタリアの前線へと移動したウェトゲンシュタインはイタリア軍の捕虜になってしまう。はじめはコモ、のちにカッシーノの捕虜収容所へ送られることとなった。
この時期に論理哲学論考の構想がほぼ固まったようである。
交友のあったマクロ経済学者のケインズの力を借りる事により、収容所から解放される事になる。
論理哲学論考発表
1919年、ウィーンに戻ったウィトゲンシュタインは、さっそく論理哲学論考の出版を目指して行動を開始する。
しかし当時無名の学者であった彼の論文を出版してくれる出版社はなく、更に彼の論文を理解できる人間が少なかった事で、上手く話は進まなかった。
ウィトゲンシュタイン自身も失意の状態にあった。
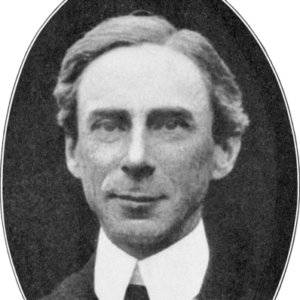
1916年のラッセル
そんな中、師のラッセルが、自分が序文を書く事で論理哲学論考が出版できるのではないかとウィトゲンシュタインに提案した。
しかし既にウィトゲンシュタインはやる気を失っていて出版に関してどうでも良くなっていた。彼はラッセルに『ご自由にどうぞ』と伝え、自分は田舎の小学校の教師に転職してしまった。
ラッセルはその後も論理哲学論考を出版するために各所に働きかけ、ウィトゲンシュタインに構成や意見を聞きながら、1922年ついに『論理哲学論考』は世の中に発表される事になる。
教師としてのウィトゲンシュタイン
論理的かつ明快に答えを出して哲学を終わらせてしまう結論に至ったウィトゲンシュタインは、哲学者としてではなく小学校の教師としての人生を歩んで行くこととなる。
ウィトゲンシュタインは小学校の教師としては非常に優秀であり、紙と黒板で行う授業ではなく「外に出て昆虫の標本を作る」など実体験の中での学びと教育に重きを置いていたが、体罰をしばしば行っていたことから生徒の家族には理解してもらえず、しだいに周りの人達からも疎まれるようになっていった。
その後、教師を辞職し聖職者を目指したが叶わず修道院の庭師になり、建築家として活動した後、ラッセルに推されてケンブリッジ大学で『論理哲学論考』を博士論文として提出。
この頃にはウィトゲンシュタインは天才哲学者として名を馳せており、1939年にケンブリッジ大学の哲学教授となった。
その後、哲学への熱が再燃し『哲学探究』を発表。1951年に前立腺癌で死去した。(満62歳没)
最後の言葉は「素晴らしい人生だったと伝えてくれ」だったという。
論理哲学論考の哲学

『論考』出版の頃のウィトゲンシュタイン(右から2番目に座っている人物・1920年)
論理哲学論考は全7つの命題からなっており
1.世界とは、起きている事、全てのことである。(物ではなく、事実の総体であるとする)
2.起きている事、つまり事実とは、幾つかの事態が成り立っていることである。(事態+成立=>事実)
3.事実の論理上の像が、思想(思惟されているもの、思考対象、思想内容)である。(事実/思想がパラレル。事態と思想ではない)
4.思想は、意義を持つ命題である。
5.命題は要素命題の真理関数である。(要素は、自分自身の真理関数である。)
6.真理関数一般は[p―, ξ―, N (ξ―)]である。
7.語りえないことについては、沈黙するほかない。
となっている。
「論理哲学論考では人間の思考の限界は言語の限界である」
と言い切っている。
例えば、目の前にドーベルマンがいたとする。
この場合は
「この犬は、名前は何で、Aさんに飼われていて、犬種はドーベルマンである」
と具体的な説明が出来る『事実の総体』である。
また、
「この犬が空を飛んで宇宙に飛び出し、月にたどり着く」
というのは現実ではありえないがイメージは可能で、言語的、論理的矛盾はない。
こうした現実的には不可能だが、言語的、論理的にたどり着ける思考空間を「論理空間」と呼ぶ。
また、
「この犬が勲章でコンビニと疲れて絵画と褒めた太陽」
のような文になると、同じ言葉といえどもイメージは不可能である。これは論理空間の外にあると言え、人間の思考と言語には限界地点があることを示唆した。(※但しこの場合は事象の意味を成さないダダイズムという芸術もある)
それまでの形而上哲学は、まずこういった論理空間の定義が曖昧であったことと、論理空間の外にあることについては人間がたどり着くのは不可能であるので、論じても意味がないと言い切ったのである。
論理哲学論考の名言
およそ語られうることは明晰に語られうる。そして、論じえないことについては、ひとは沈黙せねばならない。
定義とは、ある言語から他の言語への翻訳規則である
だがもちろん言い表しえぬものは存在する。それは示される。それは神秘である。
〜『論理哲学論考 序』から引用 〜
筆者的には、ウィトゲンシュタインは無神論者ではなく、哲学の最も主要な主題である真理や神について人間が思考でたどり着けるギリギリの地点まで達し、その前でただひたすら絶句(沈黙)していたように見える。
彼の哲学は分析哲学と呼ばれ、現在も主要な分野の一つになっている。








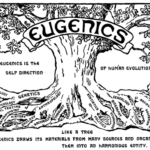








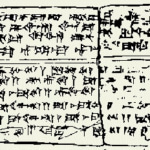







この記事へのコメントはありません。